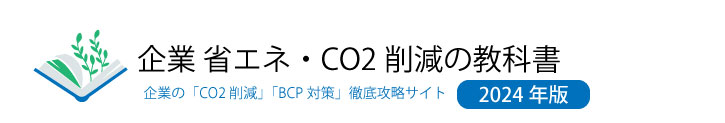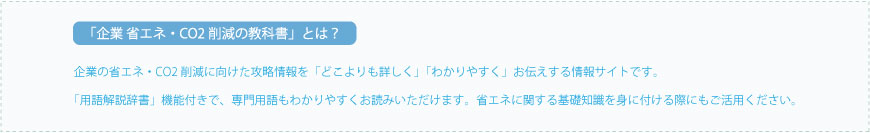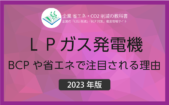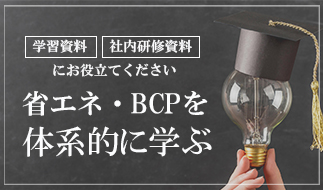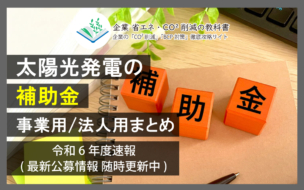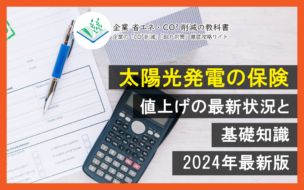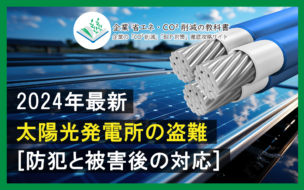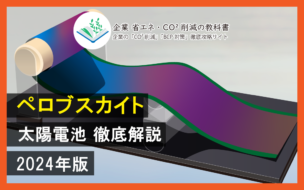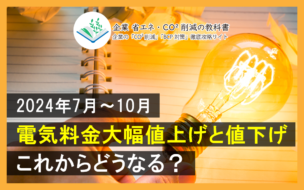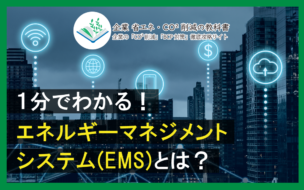※2023年4月11日:2023年の最新情報に更新しました。
2018年以降、大型台風や豪雨などの大規模災害が頻発しています。
長期にわたる停電も起こり、非常用電源の重要性が再注目されています。
「緊急時のための非常用電源導入は、他人事では無くなって来ています」
非常用電源にもディーゼル発電機や産業用蓄電池など様々なものがあります。
「どれを選べば良いのか?」
判断に困っている方も多いのではないでしょうか?
このページでは、BCP対策 における非常用電源について、分かりやすく説明していきます。
・なぜ非常用電源が必要か?
・非常用電源で備えるべき期間はどれくらい?
・非常用電源の種類と特徴
・業種別:対応すべき電気機器
ぜひ御社の非常電源検討材料にお役立てください。
※BCP対策 の基本的な内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
非常用電源の必要性が高まっている背景
近年、大規模自然災害による企業への影響が大規模かつ多様化し、
「自然災害に直面した際にも事業を継続する」BCP対策 の重要性が高まっています。
2018年~2022年の自然災害と停電期間
まずは近年の自然災害についておさらいしてみましょう。
| 年 | 名称 | 災害分類 | 発生 |
| 2022年 | 茨城県南部地震 | 地震(震度5強) | 2022年11月9日 |
| 福島県沖地震 | 地震(震度5弱) | 2022年10月21日 | |
| 大隅半島東方沖地震 | 地震(震度5弱) | 2022年10月2日 | |
| 北海道宗谷地方北部地震 | 地震(震度5弱) | 2022年8月11日 | |
| 東北北部 大雨 | 豪雨 | 2022年8月9日 | |
| 宮城県 局地的大雨 | 豪雨 | 2022年7月15日 | |
| 埼玉県 局地的大雨 | 豪雨 | 2022年7月12日 | |
| 熊本地震 | 地震(震度5弱) | 2022年6月26日 | |
| 能登半島地震 | 地震(震度6弱) | 2022年6月19日 | |
| 茨城県沖地震 | 地震(震度5弱) | 2022年5月22日 | |
| 福島県中通り地震 | 地震(震度5弱) | 2022年4月19日 | |
| 岩手県沖地震 | 地震(震度5強) | 2022年3月18日 | |
| 宮城・福島地震 | 地震(震度6強) | 2022年3月16日 | |
| 日向灘地震 | 地震(震度5強) | 2022年1月22日 | |
| 父島近海地震 | 地震(震度5弱) | 2022年1月4日 | |
| 2021年 | 和歌山県北部地震 | 地震(震度5弱) | 2021年12月3日 |
| 山梨県東部・富士五湖地震 | 地震(震度5弱) | 2021年12月3日 | |
| 東京・埼玉地震 | 地震(震度5強) | 2021年10月7日 | |
| 青森県沖地震 | 地震(震度5強) | 2021年10月6日 | |
| 令和3年8月 集中豪雨 | 豪雨 | 2021年8月11日 | |
| 令和3年7月 集中豪雨 | 豪雨 | 2021年7月1日 | |
| 宮城県沖地震 | 地震(震度5強) | 2021年5月1日 | |
| 宮城県沖地震 | 地震(震度5強) | 2021年3月20日 | |
| 和歌山県北部地震 | 地震(震度5弱) | 2021年3月15日 | |
| 2021年の福島県沖地震 | 地震(震度6強) | 2021年2月13日 | |
| 2020年 | 令和2年7月豪雨 | 豪雨 | 2020年7月3日 |
| 石川県能登地方 | 地震(震度5強) | 2020年3月13日 | |
| 2019年 | 令和元年台風第19号・21号 | 台風 | 2019年10月6日 |
| 令和元年台風第15号 | 台風 | 2019年9月5日 | |
| 令和元年8月の前線に伴う大雨 | 豪雨 | 2019年8月27日 | |
| 令和元年台風10号 | 台風 | 2019年8月15日 | |
| 令和元年台風8号 | 台風 | 2019年8月5日 | |
| 令和元年台風5号 | 台風 | 2019年7月18日 | |
| 令和元年6月29日からの大雨 | 豪雨 | 2019年6月29日 | |
| 山形県沖地震 | 地震(震度6強) | 2019年6月18日 | |
| 令和元年5月18日からの大雨 | 豪雨 | 2019年5月18日 | |
| 北海道胆振地方中東部地震 | 地震(震度6弱) | 2019年2月21日 | |
| 熊本県熊本地方地震 | 地震(震度6弱) | 2019年1月3日 | |
| 2018年 | 北海道胆振東部地震 | 地震(震度7) | 2018年9月6日 |
| 平成30年台風21号 | 台風 | 2018年9月4日 | |
| 西日本豪雨 | 豪雨 | 2018年6月28日 | |
| 大阪北部地震 | 地震(震度6弱) | 2018年6月18日 |
近年の自然災害の傾向
2018年以降、台風や水害による被害が多発しています。
さらに2021年、2022年と大型地震の数も増えています。
水害においても、地震においても、
最大で2~3週間に及ぶ停電が起こっています。
停電に備えるには非常用電源が必要
こうした背景から、停電時に備える「非常用電源」の需要が高まっています。
非常用電源はなぜ必要?
次に「非常用電源はなぜ必要なのか?」確認してみましょう。
1.生命にかかわる問題
病院や介護施設
言うまでもなく、病院や介護施設においては医療機器が停止してしまうと
大きな命の危険があります。
※詳細はこの記事内で機器別に後述します。
本記事内:業種別:BCPで優先する機器を考える>医療機器(病院、医療施設)
空調の停止による生命の危険
空調停止により、熱中症で亡くなる方が出たことも大きく報道されています。
近年は猛暑が続いており、空調も生命にかかわる設備になっています。
東京新聞:冷房の余力なし 82歳死亡
台風被害としては異例の長期にわたる停電が続く千葉県では、
十二日に君津市の特別養護老人ホーム(特養)「夢の郷(さと)」に入所していた女性(82)が、熱中症の疑いで亡くなった。この施設は停電直後から国や県へ電源車の配備を求めたが、実現したのは十三日未明で、
九日から四日間にわたって非常用の自家発電機だけでしのぐことを強いられた。
2.「通信手段確保」にも電源は必要
BCP対策 で特に重要視されるのが「通信手段の確保」です。
なぜ通信手段の確保がそこまで重要なのでしょうか?
1.責任者からの指示伝達
BCP を実行するためには、
まずは責任者からのアナウンス、状況把握のため「円滑な情報連携」が必要です。
2.従業員の安否確認
言うまでもなく、企業の責任として最重要です。
被災した従業員の安否確認、支援や指示を行う必要があります。
3.取引先との連絡手段の確保
「取引先との連絡手段確保」は、特に企業の事業継続に大きく影響します。
4.2.2.2 情報発信
不測の事態に直面したとしても、企業・組織の活動が利害関係者から見えない、
何をしているのか全くわからないといった、いわゆるブラックアウトを起こすと、
取引先が代替調達に切り替えるなど、自社の事業継続に不利な状況が進む。
非常事態に陥った際には、取引先の信用を損なわずに継続して取引できるよう
まずスピーディな「情報発信」が必要です。
これらを初動段階で行うため「通信手段の確保」は必須です。
通信機器には電源が必要
そして通信手段確保の為には、PCや電話、FAX等さまざまな通信機器の電源が必要になります。
※詳細はこの記事内で機器別に後述します。
本記事内:業種別:BCPで優先する機器を考える>全業種共通:通信機器
3.消防設備用の発電機は使えない
「うちには確か非常用電源があったから大丈夫」と思う方も注意が必要です。
消防設備用にしか使えない非常用電源もあります。
御社の非常用電源も必ず確認しておきましょう。
非常用自家発電設備の一般負荷への電力供給としての使用
| 防災用専用機 | 防災用・保安用共用機 | 保安用専用機 | |
| 使用 | 不可 | 条件付き可 | 可 |
| 理由 | 防災設備のみを対象に電力を 供給するもので、一般負荷へ の電力供給には使用はできない。(注1) | 防災電源として必要な運転時間 及び燃料保有量が常に確保され ていることを条件に、一般負荷 への電力供給にも使用できる。 | 設置者が自主的に設けた電源 であることから、本来の目的 以外の一般負荷への電力供給 にも使用できる。 |
出典:一般社団法人日本内燃力発電設備協会「内発協ニュース12月号 通巻第201号」
注1)下記の条件下では一部使用できる旨の留意事項が示されました
Q1.電力不足解消のため、消防用設備等の非常電源である自家発電設備を
一般負荷にも活用してよいか。A1.消防用設備等の非常電源にあてる燃料や電力容量が常に確保されていれば差し支
えないが、以下の点には注意すること。・ 電力需給対策に活用するため、自家発電設備を手動で起動させる設定に変更し
た場合、使用後速やかに元の設定に戻し、常用電源が停電したときに自動的に起
動し、消防用設備等に電力供給される状態にしておくこと。・ 長時間に及ぶ連続運転に適していない構造の自家発電設備は使用しないこと。
出典:消防庁「自家発電設備を電力需給対策に活用する場合の留意点について」
非常用電源にはどんなものがある?
それでは非常用電源にはどのようなものがあるのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。
化石燃料を使用する発電機
「ディーゼル発電機」のように
「非常用電源」として広く取り入れられているのが「化石燃料を使用する発電機」です。
使用する化石燃料には、軽油の他にも「ガソリン」「LPガス」などがあります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
ディーゼル発電機
昔から非常用電源として広く活用されてきたのが「ディーゼル発電機」です。
特徴
軽油を燃料として使い、稼働することで発電します。
メリット
・機種が大型から小型まで豊富
・LPガス 発電機と比べれば省スペース
・発電効率が良い
・燃料単価が安い
デメリット
・排気ガスが出る
・振動による騒音が出る
・燃料の備蓄が必要
・貯蔵量により危険物になる場合、貯蔵設備が必要
・燃料が劣化する
軽油の保管期限はおよそ6ヶ月
石油連盟によると、軽油の保管期限はおよそ6ヶ月が目安とされています。
長期保存すると酸化が進み、不完全燃焼などの不具合が生じる危険性があります。
定期的な確認と買い替えが必要です。
要注意!いざという時に動かなかったケースも。
点検を行っていなかった為、いざという時に非常用電源が動かなかった事例も
大阪北部地震の際に大きく報道されています。
参考:日本経済新聞「病院、地震後あわや一大事 自家発電に不備・診療休止も」
まずは点検と備蓄燃料の確認を。
上記のようなケースが懸念されますので、まずは点検が実施されているかどうか?
また燃料は備蓄されているかどうか?
既にディーゼル発電機を導入している企業様は確認しておきましょう。
ガソリンエンジン発電機
特徴
ガソリンでエンジンを稼働し発電します。
小型で持ち運びができるタイプが主流になってますので、野外などでも使用できます。
メリット
他の非常用電源での電源確保が難しい箇所や、
被災で施設が損傷し大型非常用電源からの電気供給が困難な場所に使うなど
小回りが利く点がメリットです。
デメリット
災害時に燃料の入手が困難。
大型はあまり存在しない為、大規模な非常用電源としては活用しにくい。
定置式LPガス発電機
続いて、LPガス を使用する定置式発電機です。
特徴
LPガス はガスシリンダー やバルクで貯蔵できる燃料です。
さまざまなメリットから、近年非常用電源として注目され始めています。
メリット
・燃料が長期間劣化しない。
・環境にやさしい
・連続運転時間が長い
・供給が途絶えるリスクが少ない
デメリット
・ガソリンやディーゼルと比較して燃費が高い
・製品の種類が少ない
燃料の劣化が少ない
特に燃料の劣化が少ない点が他の燃料式非常用電源と比較して大きなメリットです。
液体燃料のように保管期間を管理し、買い替えなどを行う面倒さを省けることはもちろん
「いざという時に劣化していて使えない」という大きな問題を防ぐ事にもなります。
供給が途絶えるリスクが小さい
LPガスは、下記の近年の大型災害においても供給途絶や二次災害が起こっていません。
平成28年8月 台風10号
平成29年7月 九州北部豪雨
平成30年2月 北陸豪雪
平成30年6月 大阪北部地震
平成30年7月 西日本豪雨
平成30年9月 台風21号
平成30年9月 北海道胆振東部地震
出典:一般社団法人全国LPガス協会「LPガス業界における大規模災害の取組について」
燃料の備蓄・調達に強い非常用電源
そうした点から、燃料の備蓄や調達に強い燃料型非常用電源と言えるでしょう。
定置式LPガス発電機について詳しくはこちら
定置式LPガス発電機については、こちらの記事でより詳しく解説しています。
可搬式LPガス発電機
LPガスを使った可搬式の発電機もあります。
上記同様 LPガスのメリットを持ちつつ、定置式より低コストで導入できます。
産業用蓄電池
続いて産業用蓄電池について見ていきましょう。
産業用蓄電池の種類
産業用蓄電池には、材質によって4つの種類が存在します。
産業用蓄電池それぞれの特徴とメリット・デメリット
| 産業用蓄電池以外の 代表的な用途 | 使用可能年数 | 蓄電可能回数 | メリット | デメリット | |
| 鉛蓄電池 | 自動車のバッテリー | 17年 | 3,150回 | ・安価で使用実績が多い。 ・使用年数が長い。 | ・過放電をしてはいけない。 |
| ニッケル水素電池 | 充電乾電池 | 5~7年 | 2,000回 | ・急速充放電ができる。 ・過充電/過放電に強い。 | ・寿命が短い。 |
| リチウムイオン電池 | ノートパソコン 携帯電話 | 10年 | 4,000回 | ・残存容量が把握しやすい。 ・現在最も技術開発が推進 されている。 | ・使用可能時間が少し短い。 |
| NAS電池 | 主に産業用 | 15年 | 4,500回 | ・寿命が長い。 | ・安全性を不安視する声も。 ・価格が高い。 ・Naや硫黄が含まれ危険物 指定されている。 |
経済産業省の発表による数値を参考にあげると上記のようになっていますが、
メーカーによってはこの数値を大きく上回っているものもあります。
特殊な機能を持った蓄電池として、エネルギーマネジメントシステム が搭載されて
ピークカット が可能になっている産業用蓄電池もあります。
エネルギーマネジメントシステム/ピークカットについて詳しくはこちら
エネルギーマネジメントシステム の付蓄電池の例
東芝:リチウムイオン蓄電システム VPCS-LIB-R200
エネマン:⾼性能オフグリッドシステム「eneman(エネマン)」
産業用蓄電池の特徴
停電直後から短時間使用する用途では、蓄電池は手間がかからず便利です。
但し電気を使い切ってしまうと、活用できなくなる弱点があります。
その為、後述する太陽光発電との組み合わせが効果的です。
導入費用が高い点がデメリット
非常に便利ではありますが導入費用が高く、
蓄えておく電力量によっては場所を取ることが難点です。
どれほどの電気を蓄えておくべきか?費用とどこまでの規模にすべきか?
を踏まえて他の非常用電源と比較しましょう。
EV(電気自動車)を蓄電池として活用する
EV(電気自動車)やハイブリッド自動車を蓄電池の代わりに活用する手法は、
家庭用非常用電源としても注目されています。
同様に企業においても、社用車をいざという時の蓄電池として活用する方法が注目されています。
V2H(=クルマに蓄えた電気を家で使う)
「V2H」とは「Vehicle to Home」の略で、電気自動車やハイブリッド自動車のバッテリーを家庭などに使うことを意味しています。
家庭や企業で車を非常用電源として使用する場合、この「V2H」に対応した車である必要があります。
「V2H」対応車種の例
| メーカー | 車種 | エンジン停止中も 電力供給できるか? | バッテリー容量 | ガソリン込の電力供給量 |
| トヨタ | プリウスPHV | 〇 | 4.4kWh | 40kWh |
| トヨタ | MIRAI | × | 1.6kWh | 60kWh ※ガソリンではなく水素 |
| 日産 | リーフ | 〇 | 30kWh | 30kWh |
| 日産 | e-NV200 | 〇 | 24kWh | 24kWh |
| 三菱 | i-MiEV/MINICAB-MiEV | 〇 | 16kWh | 16kWh |
| 三菱 | アウトランダーPHEV | 〇 | 12kWh | 100kWh |
ポイント1:エンジン停止中も給電できるか?
「エンジン停止中にも給電できるか?」は重要なポイントになります。
エンジンをかけた状態でしか使えない場合、
災害時には「危険性」と、治安悪化に伴う「防犯面」に注意が必要です。
こうした面から「停止中も給電できる」自動車の方が非常用電源には向いていると言えます。
ポイント2:発電にガソリンは必要か?
「バッテリーだけで給電するのか?」「ガソリンでの発電も考慮するか?」
ここも重要なポイントです。
例えば上の表で最も電気供給量の多い「三菱のアウトランダーPHEV」ですが、
ガソリンで発電してバッテリーに充電している際には、
外部電源として電力を供給することができません。
ガソリンでエンジンをかけ、充電することを考慮しないのであれば、
バッテリーのみでの容量は日産のリーフの方が多くなります。
ポイント3:燃料の調達に注意
おさえておかなければならないのは、バッテリーの電気やガソリンが無くなった場合には、燃料を調達しなければならない点です。
災害時にはガソリンスタンドも混雑し、供給が難しくなります。
また電気についても、そもそも停電に備えるわけですから、給電は難しい可能性があります。
12kWhでおよそ家庭の電気消費量1日分
家庭で換算すると、1日の電気使用量は12 kWh が目安とされています。
つまり、リーフなら4日間、アウトランダーPHEVなら10日間の非常用電源として
家庭用では使用できる計算になります。
企業の施設とは異なりますが、ご参考になさってください。
「V2H」に関する各自動車メーカーサイト
日産:リーフのV2H
三菱:「SMART V2H」はココが違う
太陽光発電
続いて、太陽光発電について解説していきます。
文字通り太陽光で発電した電気を非常用電源に活用します。
燃料がいらない。ライフラインに影響されない。
太陽が出ていれば発電するため燃料は必要ありません。
ライフラインにも影響されず、長期的な電力確保が可能です。
電力供給が不安定。
太陽が出ていなければ発電されないため、安定した電力確保が困難。
また、電気を貯めておく機能はありません。
産業用蓄電池との組み合わせで弱点克服
産業用蓄電池と組み合わせて使用すると、これらの弱点を補うことができます。
昼に発電した電気を蓄電池に貯めておくことで、
電力供給も安定し、短期しか使えない産業用蓄電池の弱点もカバー。
長期使用可能で燃料も不要な非常用電源にすることが可能です。
太陽光発電+蓄電池という選択
こうした形で非常用電源を用いる企業は、近年は特に燃料式発電機よりも多い傾向があります。
上記に上げたようなメリットに加え、CO2削減や CSR といったメリットもあり、
省エネや BCP に大きな付加価値が加えられます。
太陽光発電について、詳しくはこちら
非常用電源の目安は「72時間」
非常用電源で確保すべき電源の目安は「72時間」とされているのが一般的です。
なぜ72時間が目安になるのでしょうか?
「72時間」の根拠は?
2.阪神淡路大震災の際に救出された方の生存率が72時間を超えると激減した。
上記から、災害医療分野で生死を分けるタイムリミットとして「72時間の壁」という言葉が広まり、
非常用電源としても当てはめられるようになりました。
「72時間」はどこで定められている?
上記を元に、政府から各庁舎に求められている最低限度の基準がこの「72時間」です。
総務省「地方公共団体における業務継続性確保のための非常用電源に関する調査結果」
※人命救助の観点から重要な「72 時間」は、外部からの供給なしで非常用
電源を稼働可能とする措置が望ましい。
出典:総務省「地方公共団体における業務継続性確保のための非常用電源に関する調査結果」
その公共機関の基準を元に、民間でも72時間を目安にしています。
72時間は「人命救助のための時間」
つまり、72時間は「人命救助のための時間」であり
初動の BCP対策 において維持しておく基準になります。
この72時間は現在、一般的な基準になっていますので、CSR の上でも目安になってきます。
上記の「通信機器の維持」と併せて「非常用電源の目安は72時間」と覚えておきましょう。
災害時にも事業を継続するには?
それでは、災害時における「事業継続」について考えてみましょう。
災害時に操業を維持する電源確保は難しい
台風などでの水害で最大3週間、地震で1週間の停電が
近年の停電期間になっています。
しかしながら、それらの期間を非常用電源で
通常通りの操業を維持していくことは可能なのでしょうか?
何億という膨大な設備費用をかければ、操業を止めない非常用電源を確保することは可能です。
しかしながら、そこまでの費用をかけることができる企業は少ないでしょう。
施設別:非常用電源での事業継続の難易度
比較的難易度の低い施設
・オフィス(自社ビル)
・店舗(自社所有/路面店)
・介護施設
・自社ビル
難易度の高い施設
・工場
・医療施設
・オフィス(テナント)
・店舗(テナント)
設備に大規模な電源を要する施設や、
テナント等に入っており自社だけでは設備を変えられない施設は、
事業継続に充分な非常用電源を確保するのは難しいと言えます。
事業継続はBCMで考える
非常用電源での操業継続が困難な場合、BCM(事業継続マネジメント)で考える必要があります。
BCMは事業継続の「マネジメント」を意味します。
被災した事業所があった場合、その補填を他の事業所で行う等
組織体制などのマネジメントで事業継続を考えておきます。
方法1:事業継続に欠かせない事業を限定しておく
すべての事業を継続させるのではなく、企業の存続に欠かせない事業を限定し、
その事業を継続するため必要最低限な非常用電源を用意しておく。
内閣府の 事業継続ガイドライン はじめ様々な BCP対策 でも推奨されています。
方法2:他の事業所に業務を移管する
被災した事業所の業務を、他の事業所で賄う方法もあります。
こうした際にも、被災状況素早く把握し伝達する為、
「通信機器の維持」が重要になります。
まずは「72時間」を目安に「生命を守る」「通信を維持する」
BCM で事業継続を図る場合でも、従業員の生命を守ることや、
通信手段を維持することができなければ実現できません。
そうした意味でも「72時間」を維持する非常用電源を確保しておくことは
非常に重要になってくるのです。
業種別:BCPで優先する機器を考える
それでは、BCP においてどのような機器の電源確保を考えておくべきなのでしょうか?
動かすべき機器を業種別に確認してみましょう。
生命にかかわる機器(全業種共通)
1.照明
災害による停電が夜や天候の悪い日に起こった場合、
避難が困難になり、従業員やお客様の生命に危険が及びます。
避難経路の確認と非常用電源の適用範囲
まず避難経路を確認し、緊急時に照明が必要な個所を確認しておく必要があります。
非常用電源と同時に考えておくべきLED
非常用電源は照明以外の機器にも使用されます。
容量を考えた際に、照明の省エネも同時に考えておくと、非常用電源を他でも活かすことができます。
日々の省エネにもなるので、LEDの導入も同時に検討しておくと良いでしょう。
2.空調
近年は猛暑の影響で、災害時の空調停止による死亡者も出ています。
特に病院や介護施設においては、お年寄りや病気の方に大きな危険が及びます。
空調における非常用電源確保の問題点
空調の消費電力は大きい
空調機器の消費電力は非常に大きなものです。
それを72時間、または停電が長引いた際に維持するのは非常に困難です。
省エネも同時に考えておくと良い
非常用電源の導入費用を削減する為には、照明と同じく省エネを同時に考えておくと効果的です。
とはいえ買い替えには、大きな費用がかかります。
消費電力を90%カットするガスヒートポンプ(GHP)
LPガス でエンジンを稼働し、ヒートポンプによって冷暖房を行う空調です。
日本LPガス協会によると、使用電力を90%削減することが可能です。
また「LPガス発電機」の項でもご説明した通り、
LPガス は備蓄しやすく、供給も途絶しにくい為、非常用燃料として最適です。
ガスヒートポンプ(GHP)について詳しくはこちら
3.エレベーター
閉じ込められてしまうリスク
急な停電で中に閉じ込められてしまった場合、生命の危険に関わります。
車いす・ベッドでの移動
医療施設や介護施設において、車いすやベッドでの移動が必要な方の避難や、医療処置における移動の為、エレベーターが不可欠となる場合があります。
どこまでの範囲で稼働すべきか?
エレベーターの稼働には大きな電力消費が伴います。
どこまでエレベーターに非常用電源の電力を割り当てるかも考えておくべき課題です。
4.通信機器
通信機器も従業員の状況確認など、生命にかかわる機器と言えます。
※通信機器は次の項に詳しくまとめます。
通信機器(全業種共通)
続いて全業種共通で重要になって来るのが「通信機器」の維持です。
前述の通り、BCP 発動初期の通信機器の維持は、事業継続の上でも非常に重要です。
電話機・PC・FAX
言うまでもなく、通信機器維持の為には、電話機や携帯電話、PCの電源を確保する必要があります。
FAXも企業によっては取引先とのやり取りの為、電源を確保しておく必要があります。
通信回線
モデムやルーターといった、通信を維持するための機器の電源も必要です。
非常用の通信回線
BCP対策 として、非常用の回線を用意しておく場合、その電源確保も必要です。
社内データベース
オフィスワークを中心に、業務に必要なシステムを動かす必要があります。
そうした業務に不可欠な社内システムを維持するための電源確保も念頭に置いておく必要があります。
医療機器(病院、医療施設)
2種類の電気系統に要注意
病院における電気系統には「単相100V」と「単相200V」という電力供給方法があり、
稼働できる機器も異なる為注意が必要です。
※上記は「単相3線式」の場合です。
「三相4線式」の場合には「三相200V」を供給する為、稼働する機器に影響はありません。
※下記はあくまで傾向です。機器によって異なる場合もありますので、
それぞれ実際に導入している機器を確認しておきましょう。
単相100Vが供給される主な医療機器
特に生命維持に深くかかわる機器については、「単相100V」で稼働でき、
さまざまな非常用電源から供給される電力で稼働するものが多いです。
・人工呼吸器
・人工心肺装置
・補助循環装置
・保育器
・透析用監視装置
・輸液ポンプ
・シリンジポンプ
・セントラルモニタ
「単相200V」が供給される主な医療機器
対して、「単相200V」で稼働する機器については、
「単相200V」に対応した非常用電源で動かす必要がありますので注意が必要です。
・透析用RO装置
・多人数用透析液供給装置
・X線装置
・CT
・MRI
・吸引システム
・混合空気システム
色分けされたコンセント
また、医用コンセントは非常用電源に対応した用途を使い分ける為に色分けされています。
停電時に優先すべき医療機器に合わせて、必要なコンセントに繋がれているか確認が必要です。
色ごとのコンセントの特徴
白
商用電源(電力会社から供給される電気)専用のコンセント
赤
一般非常電源、特別非常電源、瞬時特別非常電源から供給されるコンセント
緑
瞬時特別非常電源から供給されるコンセント
茶色(チョコ)
上記以外に、区別された電源から供給されるコンセント
一般非常電源、特別非常電源、瞬時特別非常電源とは?
一般非常電源
商用電源が停止した際に、40秒以内に電力供給を回復しなければならない電源。
特別非常電源
商用電源が停止した際に、10秒以内に電力供給を回復しなければならない電源。
瞬時特別非常電源
商用電源が停止した際に、0.5秒以内に電力供給を回復しなければならない電源。
通信環境にも要注意
医療機器の中には、通信を必要とする機器もあります。
機器そのもだけでなく、通信に関わる機器にも予め注意しておきましょう。
より詳細はこちら
「公益社団法人日本臨床工学技士会」計画停電における医療機器の安全使用マニュアル
介護施設の設備
医療機器
入所者の方の使用している医療機器の電源確保は重要です。
病院の項で上げたように、非常用電源では動かないものもあります。
予めご使用の非常用電源との相性を確認しておきましょう。
・酸素濃縮器
・喀痰吸引装置
・ナースコール
調理関連
介護施設の場合、調理などが必要になってきます。
この周辺機器についても、確認しておきましょう。
・給湯
・調理設備
・冷凍冷蔵設備
非常用電源を導入するには?
このように、非常用電源には「優先すべき機器の選択」や「非常用電源の種類」など
さまざまな要素があります。
さらに施設の状況によって最適な設備が変わってきます。
専門家の現地調査や機器の選定を相談
非常用電源を導入する際には、専門家に現地調査や機器の選定を依頼すると
スムーズで最適な導入が可能になります。
電気やガス設備に精通している企業に依頼
また、電気やガス設備に精通している企業に依頼することも大切なポイントです。
稼働すべき機器や施設、予算などを元に相談しながら決めていくと良いでしょう。
依頼する側としても知識を身に付けておく
専門家を疑うというわけではありませんが、
御社にとって最適な非常用電源を導入するためにも、
おおよその知識を身に着けておくことは大切です。
本記事の内容もそうした面でお役立て頂ければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
BCP を考える上で、非常用電源の役割がご理解頂けたのではないかと思います。
最後に、この記事のおさらいをしてみましょう。
停電期間が2~3週間に及ぶことも。
・非常用電源は、生命を守るために重要。
・また「通信機器の維持」の為の電源確保も重要な課題。
・燃料式発電機や蓄電池、太陽光発電に加え
EV活用やハイブリッド電源等、非常電源には多くの選択肢がある。
・非常用電源の目安は「72時間」
・操業を止めないためには、BCM も重要。
・限られた電力の中で、優先すべき機器を予め決めておく必要がある。
災害時に従業員やお客様の命を守る。
事業を継続していく為に、非常用電源の役割は重要です。
本記事が御社の非常用電源の検討のお役に立てれば幸いです。