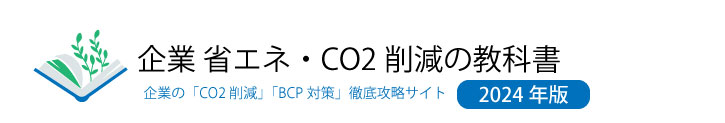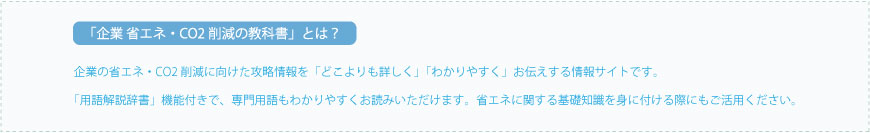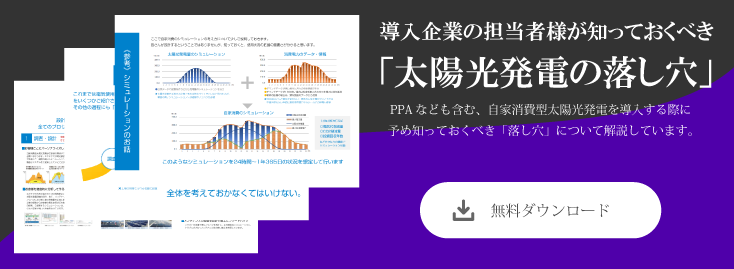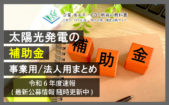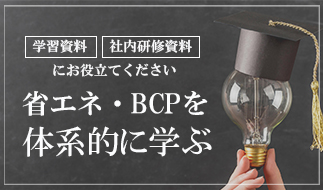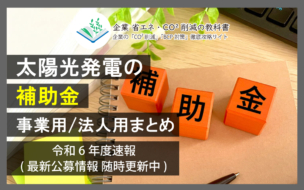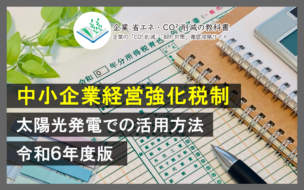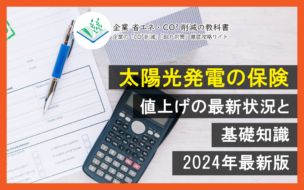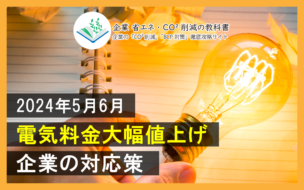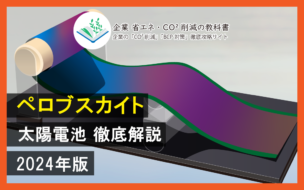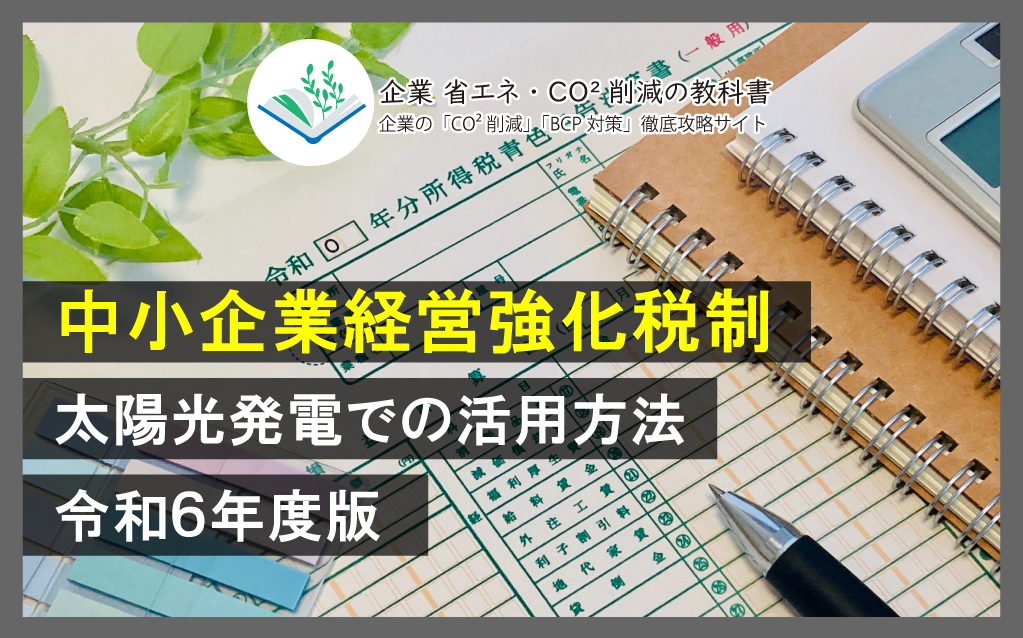
※2024年04月17日:最新情報に更新しました。
近年深刻になっている「電気料金の値上り」や「CO2削減」の流れから
「自家消費型太陽光発電」の導入を検討する企業が増加しています。
その「自家消費型太陽光発電」において、
多くの中小企業が受けている税制優遇が「中小企業経営強化税制(設備投資減税)」です。
この制度の名前を聞いたことがある人の中でも、
どんな制度なのかよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では「自家消費型太陽光発電」を導入しようとしている中小企業の方に向けて、
令和6年(2024年)4月時点での中小企業経営強化税制について解説します。
「期日に関する注意点」も多いので、この記事を参考に余裕をもって準備を進めましょう
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
[速報]令和6年度の改定版が公開
2024年4月16日に「中小企業経営強化税制 の手引き[令和6年4月15日版]」が公開されました。
中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
例年、4月上旬にこの手引きは更新されますが、
今回の改定では、太陽光発電に関連する「A類型」「B類型」は昨年度までの内容と変更はありません。
(太陽光発電とは関連しない「D類型」には、今後変更があるようです)
中小企業経営強化税制とは?
まず 中小企業経営強化税制とは、どのような制度なのでしょうか?
中小企業経営強化税制とは、簡単に言ってしまえば、以下のような制度です。
「税額控除」か「即時償却」の支援が受けられる制度
「中小企業経営強化税制」という呼び方以外にも「設備投資減税」と呼ばれることもあります。
どんなメリットがある?
2. 即時償却(初年度の節税に繋がる)
のいずれかを選択して適用できるため、企業の金銭的負担を大きく減らすことができます。
対象は「自家消費型」と「余剰売電型(自家消費率50%以上)」
・全量自家消費
・余剰売電型(自家消費率50%以上)
発電した電気をすべて自家消費する「全量自家消費」
一部を売電する「余剰売電型」の場合には、自家消費率50%以上の発電所が対象になります。
上記の発電所は対象外になりますので注意が必要です。
「自家消費率50%未満」なら「中小企業投資促進税制」
中小企業経営強化税制 と名前も内容もよく似た制度として
「中小企業投資促進税制」という税制優遇制度もあります。
こちらは、受けられる優遇措置は少し下がりますが、
余剰売電型の自家消費率は問いませんので「自家消費率50%未満」で税制優遇を受ける場合には
こちらを選択する方法もあります。
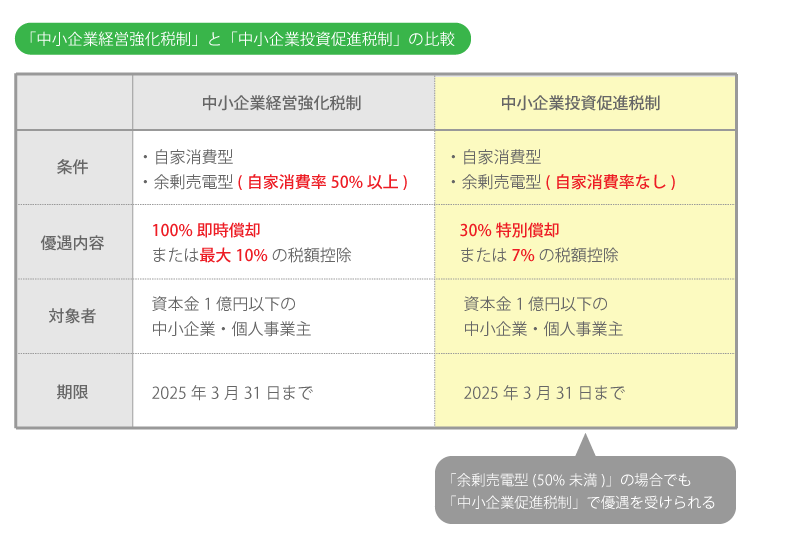
「中小企業投資促進税制」について、詳しくは下記リンク先をご参照ください。
中小企業庁「中小企業投資促進税制」
期限はいつまで?
現行の 中小企業経営強化税制 については、
の期限になっています。
この期限については、注意すべき点がありますので後半で詳しく解説します。
「税額控除」と「即時償却」
それでは、中小企業経営強化税制 で受けられる
「税額控除」と「即時償却」について詳しく見て行きましょう。
選択肢1.「税額控除」
それでは、具体的に「税額控除」の内容を見て行きましょう。
税額控除は、設備費用に対する税金を控除してもらえる税制優遇です。
企業の資本金額によって受けられる優遇の内容が異なります。
資本金3,000万円以上1億円以下の企業→「7%の税額控除」
また、税額控除が受けられる上限は、
その年の法人税額・所得税額の20パーセントまでとなっているので注意しましょう。
選択肢2.「即時償却」
続いて「即時償却」について見て行きましょう。
即時償却とは?
即時償却 とは、該当設備の設備費用をその年の経費に全額計上することです。
経費をまとめて計上することで、その年の節税につながります。
通常、こうした設備投資の費用は、減価償却 で計上しますが、
中小企業経営強化税制で選択できる
即時償却 ではそれらを初年度に一括で計上します。
減価償却のしくみ(従来の課税方法)
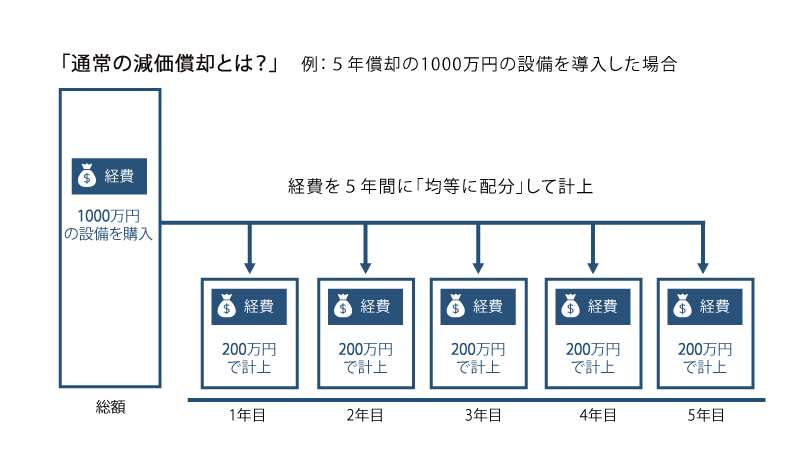
減価償却 では上記のように、設備費用を耐用年数に応じて、毎年分割して経費に計上します。
自家消費型太陽光発電 を導入する際には、通常の課税方法では、この「減価償却」になります。
即時償却ではこうなる
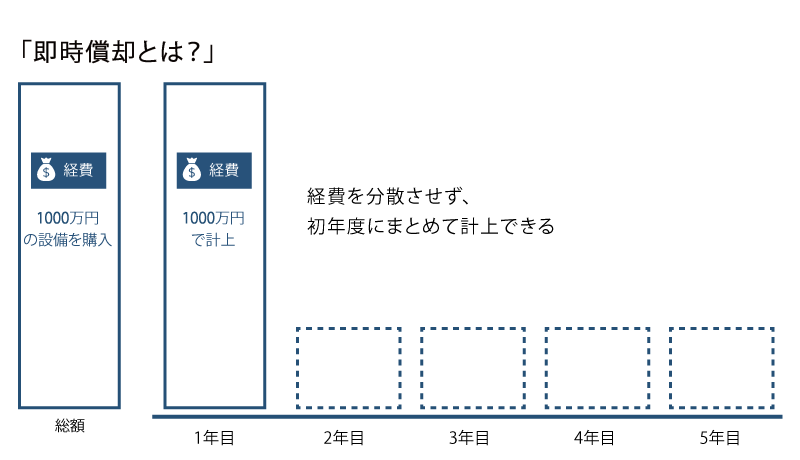
即時償却 を選択した場合、上記のように「1年目に」一括で計上することができます。
即時償却のメリット
即時償却のメリットは簡単に言ってしまえば、
経費を多く計上して利益を圧縮することによって、初年度に支払う税金額を減らせることです。
「回収した資金をすぐさま別の設備に投資したい」
といった目的での活用方法が考えられます。
税額控除と即時償却どちらを選ぶ?
先ほども解説した通り、中小企業経営強化税制 では
「税額控除」と「即時償却」のいずれかを選択して適用できます。
下記にそれぞれのメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | デメリット | |
| 税額控除 | 支払う税金の総額が減る | すぐに節税効果は得られない |
| 即時償却 | 節税効果を短期間で得られる | 支払う税金の総額は減らない |
基本的には「長期的に考える場合は税額控除、短期的に考える場合は即時償却」といったように選択すると良いでしょう。
対象となる「企業」の条件
続いて「適用される企業の条件」を見て行きましょう。
中小企業経営強化税制が適用されるための条件は、以下の3つです。
これらの条件を具体的に確認していきましょう。
1.青色申告者 であること
青色申告 は確定申告の種類の1つです。
白色申告よりも申請内容は複雑になりますが、特別控除などさまざまな利点を受けられます。
中小企業経営強化税制では、この青色申告を行っている「青色申告者」であることが条件になります。
2.個人事業主または中小企業者であること
「個人事業主」とは?
個人事業主は、開業届を提出しているものの、会社を設立せずに事業をおこなう人を指します。
こちらはいわゆる「自営業」と言えば、イメージしやすいでしょう。
「中小企業者」とは?
中小企業者は下記の条件を満たす企業を指します。
・資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するもの)
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
ただし以下の場合は対象外
2.2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
3.前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人
規模の大きな法人から出資を受けている企業の方は、詳しくチェックしておきましょう。
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
3.対象業種であること
中小企業経営強化税制には対象業種も指定されています。
以下に一覧表を記載するので、貴社がそれに該当するかどうかのチェックにお役立てください。
〇対象業種一覧
中小企業経営強化税制の対象業種は以下の通りです。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業
鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業
小売業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業
料理店業その他の飲食店業
(一定の類型を除き、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ
その他これらに類する事業を除きます。)
海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業
損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業
不動産業、物品賃貸業、広告業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業
医療、福祉業、社会保険・社会福祉・介護事業
教育、学習支援業
映画業、協同組合(他に分類されないもの)
他に分類されないサービス業
(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業
その他の事業サービス業)
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
×対象外業種一覧
その反対に、対象外業種は以下の通りです。
水道業
鉄道業
航空運輸業
銀行業
娯楽業(映画業を除く)
性風俗関連特殊営業
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
注意が必要な対象外業種「娯楽業」
前述の一覧表にも記載されている通り、娯楽業は映画業を除き、中小企業経営強化税制 の対象とならないので注意してください。
ちなみに娯楽業の分類については、総務省が作成する『日本標準産業分類』に細かく記載されているので、こちらもあわせてチェックしましょう。
対象となる「設備」の条件
次に「対象となる設備の条件」を確認して行きましょう。
「対象となる設備の条件」は、下記のようになります。
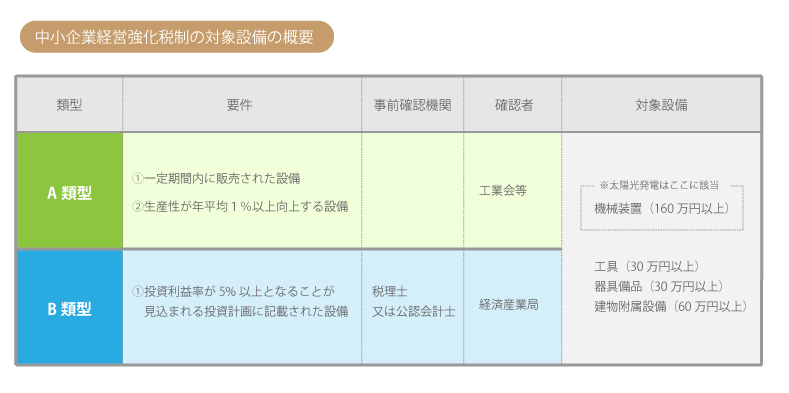
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
順番に解説していきます。
A類型とB類型
中小企業経営強化税制では、該当設備を導入する目的によって
本来「A類型/B類型/C類型/D類型」の4つに分類されます。
太陽光発電が該当するのはA類型とB類型になります。
2020年にコロナ禍を受けて、デジタル化設備導入強化の為新設された「C類型」
2021年にM&Aにおける経営資源集約化への設備投資の為に新設された「D類型」
もありますが、これらは太陽光発電とは関連性がないので
本記事では詳しい説明は省略します。
太陽光発電が該当するのは「機械装置」
中小企業経営強化税制 には機械装置や工具、器具備品といった対象設備がありますが、このうち太陽光発電は「機械装置」にあたります。
これを踏まえたうえで、機械装置におけるA類型とB類型それぞれの取得条件を確認しましょう。
A類型とB類型それぞれの取得条件
A類型の取得条件
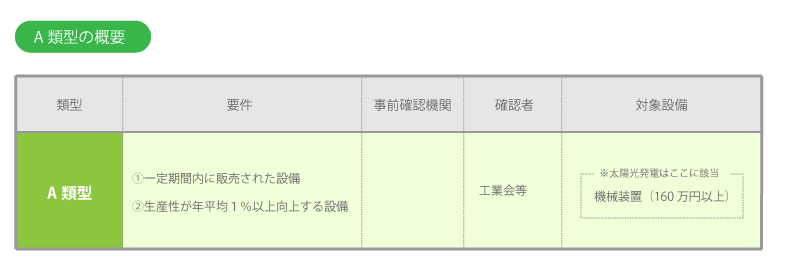
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
要件
1.一定期間内に販売された設備
一定期間内に販売された設備である必要があります。
設備の種類によって期間は異なりますが、
太陽光発電が該当する「機械設備」は「10年以内」に販売されたものである必要があります。
2.生産性が年平均1%以上向上する設備
経営力の向上に資するものとして(生産効率、エネルギー効率、精度など)
が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備である必要があります。
確認者
上記の「要件」を満たすことについて
工業会等の証明を受ける必要があります。
申請の流れ
A類型の申請の流れは下のようになっています。
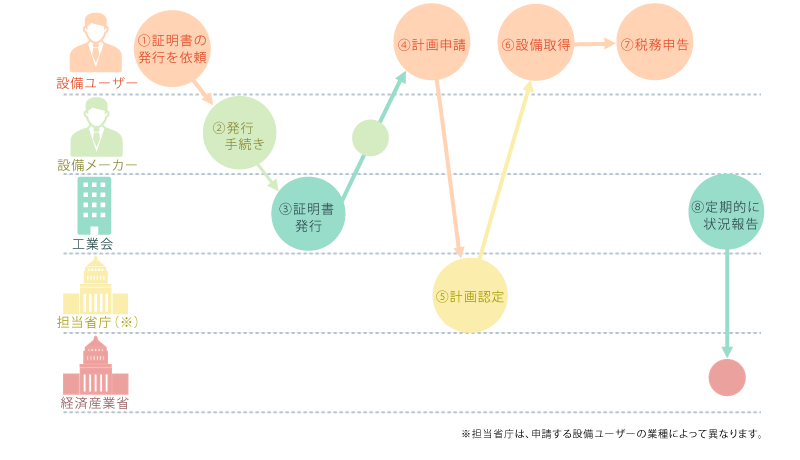
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」を元に作成
上記の通り、作業の大部分はメーカーや工業会がおこなっているため、事務作業が少なく済みます。
手間が少なくなるため「B類型よりも手続きが楽」です。
B類型の取得条件
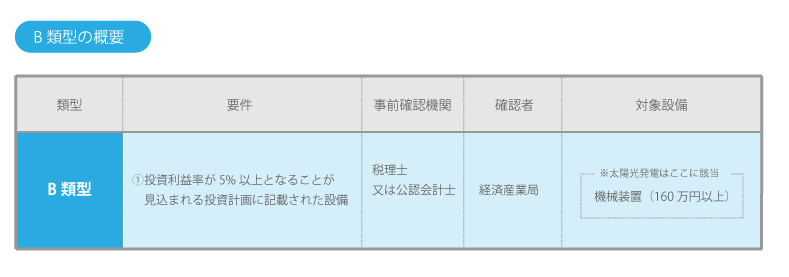
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」
要件
投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備が対象になります。
販売開始時期は求められていない
A類型では定められていた販売開始時期が、B類型では特に定められていません。
事前確認機関
「A類型」にはありませんでしたが、
「B類型」には、提出前に「税理士または公認会計士」の事前確認が必要になります。
確認者
上記の「要件」を満たすことについて
経済産業局の確認を受ける必要があります。
申請の流れ
B類型の申請の流れは下のようになっています。
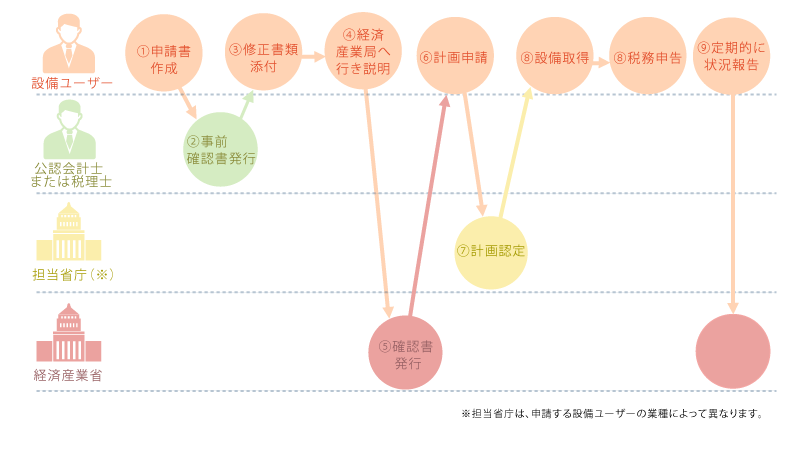
引用元:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和6年04月15日版)」を元に作成
「B類型」は、事前確認や経済産業局への説明など、設備ユーザーが行う手続きが
「A類型」よりも多いことが分かります。
A類型とB類型どちらを選ぶ?
10年以内に販売開始された設備ならA類型
基本的に、中小企業経営力強化税制を受ける際は、A類型を選ぶのがおすすめです。
A類型の方が自社で行う手続きが少なくて済むため、手間がかかりません。
10年以上前に販売開始された設備ならB類型
該当設備が10年以上前に販売されたものであった場合、必然的にB類型を選ぶことになります。
※期限に要注意
現在受付中のの中小企業経営強化税制は、2025年3月31日までの期限になっています。
しかし、この期限には注意しなくてはならないポイントが2つあります。
2.設備取得と事業開始まで完了させておく必要がある
この2つのポイントから、準備を早めに行っておく必要があります。
1.期限は申請ではなく「認定」までの期間
中小企業経営強化税制 における期限は、
ことに要注意です。
たとえば、目安として「工業会証明書」は発行までに約2か月、
「経済産業局による確認書」は発行まで約1か月掛かると言われています。
さらに担当省庁における計画申請から計画認定までにも約1か月かかります。
そのため、期限である2025年3月31日の直前に準備し始めると、
認定が間に合わなくなってしまうのです。
A類型の申請期間の目安
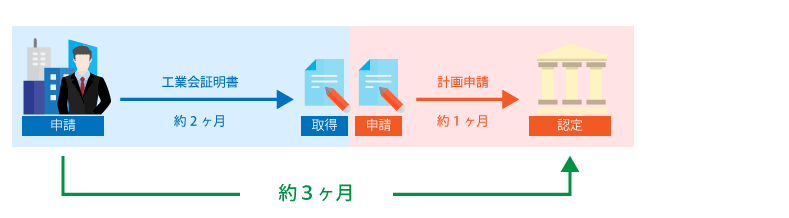
図のように、A類型の場合には申請から認定までに約3か月かかる目安になります。
B類型の期限目安
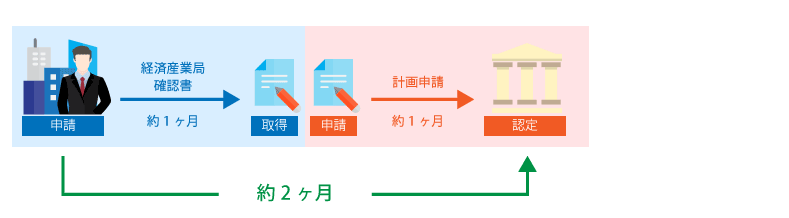
B類型の場合には申請から認定までに約2か月かかる目安になります。
A類型は手間はかからないが時間がかかる
前述の通り、A類型は中小企業者の手間はかかりませんが、
B類型に比べて、申請~認定までに時間がかかる傾向がありますので注意が必要です。
差戻しになる可能性も視野に入れておく
ただし、上記の期間は差戻しが無く円滑に審査が通った場合の例です。
当然、差戻しや再申請になる可能性もありますので、早めに動いておく必要があります。
2.設備取得と事業開始を完了させておく必要がある
期限について、もうひとつ注意しておくべき点は、
「期限までに設備取得と事業開始まで完了させておく必要がある」点です。
設備の取得時期
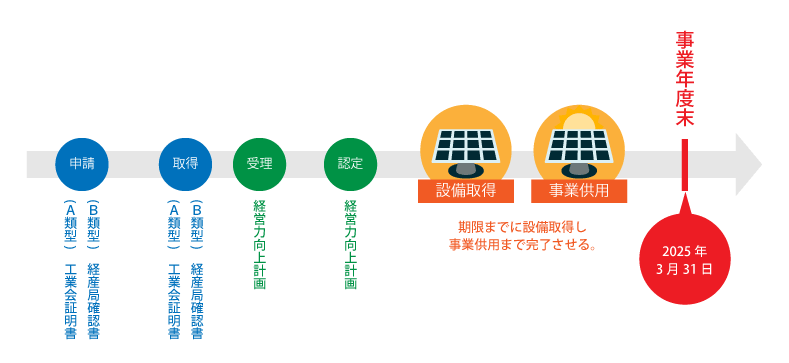
設備の取得時期は、事業年度末(2025年3月31日)までに完了しておく必要があります。
図のように、設備取得および事業開始は、原則的に計画認定の後に行います。
設備取得後に経営力向上計画を申請する場合
例外として、設備取得後に経営力向上計画を申請することもできますが、
図のように、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
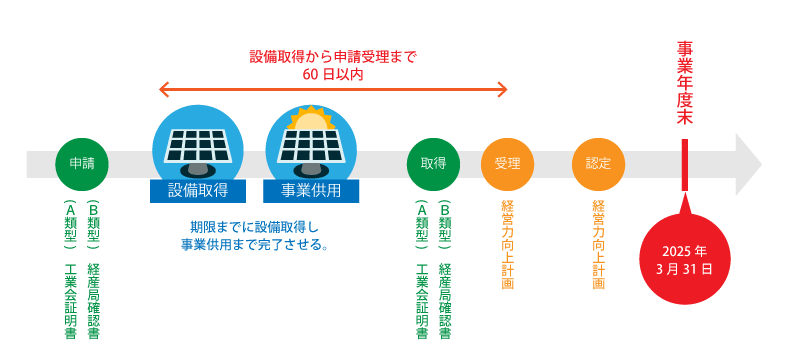
申請にかかる時間と設備導入にかかる時間に注意
このように、申請から認定にも時間がかかり、
設備取得と事業開始まで行っておく必要がありますので、
期限までのスケジュールを予め見積もって準備しておくことが重要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
中小企業経営強化税制 を理解するうえで、抑えておくべきポイントは以下の5つです。
2.自家消費型が対象。投資型は対象外
3.税額控除または 即時償却 を選択できる
4.A類型のほうが手間が少なくおすすめ
5.期日とは「申請までの期限」ではなく、
「認定までの期限」であるため、余裕をもって準備を進める必要がある。
いずれも見落としやすいポイントばかりなので、この機会にしっかり確認をおこないましょう。