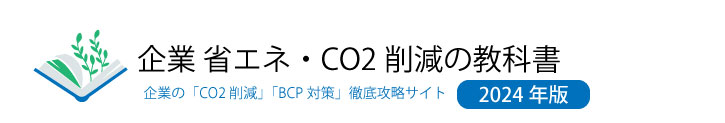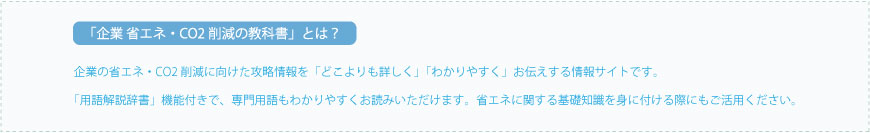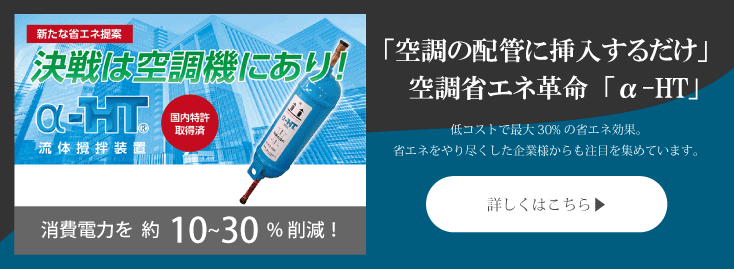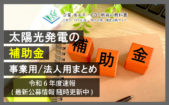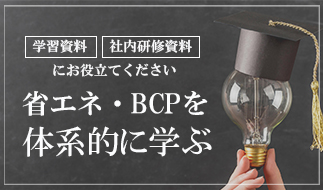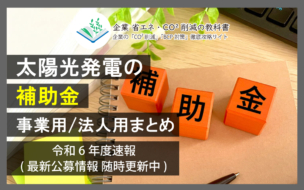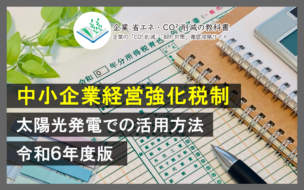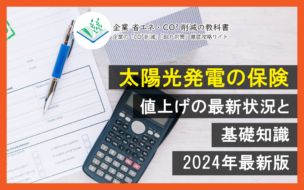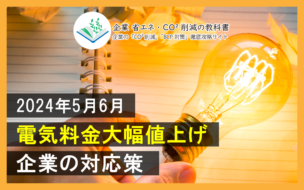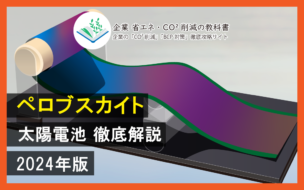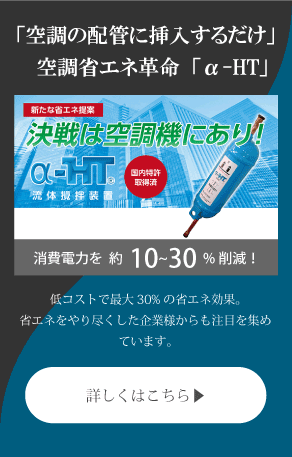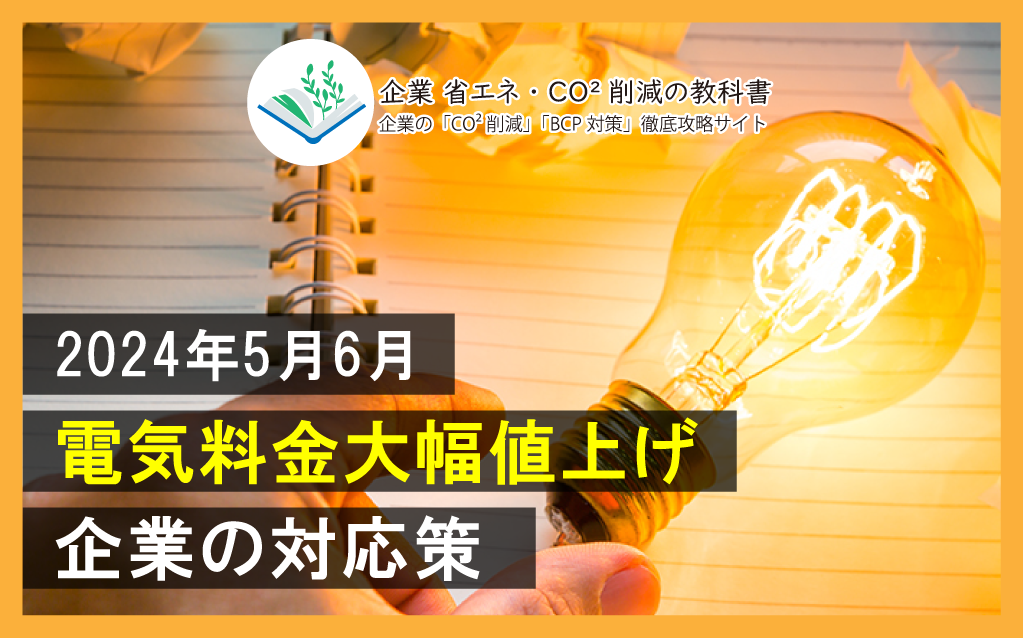
※2024年3月28日:政府の補助制度終了と再エネ賦課金値上げの最新情報を受け、更新しました。
原油価格高騰やウクライナ情勢などの様々な要因を受けて続いてきた電気料金も
昨年1月をピークに値下がり傾向になり、現在は少し落ち着いています。
しかし、「再エネ賦課金 の値上り」が決まっており、
その影響で5月の電気料金から値上がりすることが分かっています。
さらに、3月28日の最新情報では、
現在行われている補助政策を終了する方針で、政府が最終調整に入ったことも分かり、
6月からは更なる大きな値上がりになる可能性が高くなっています。
電気料金はこの先、どうなっていくのでしょうか?
この記事では、
・再エネ賦課金 の値上り
・2024年4月~6月の値上がりの見通し
・2025年まで、2050年までそれぞれの電気代の見通し
・これまでの電気料金の推移
・値上がりの要因
・企業の対応策
などについて、図やグラフを交えて、2024年3月時点の最新情報をわかりやすく解説していきます。
本記事をお読みいただければ、電気料金の値上がりに関する情報はひと通り網羅できるかと思います。
御社の「電気料金値上がり対策」のお役に立てれば幸いです。
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
目次
【速報】政府の補助政策が5月までで終了
3月28日の最新情報として、現在行われている政府の補助政策「激変緩和措置」を
5月までで終了する方向で最終調整に入っていることが分かりました。
NHK「電気 ガス料金の負担軽減措置 5月使用分でいったん終了へ 政府」
「激変緩和措置」については、後ほど本記事の中でも詳しく解説しますが
現在補助制度で優遇されている補助が無くなることで、電気料金も大きく値上がりになる見通しです。
↓詳細:本記事内「短期予測:2024年~2025年の電気料金の見通し」
↓詳細:本記事内「政府による補助制度「激変緩和措置」」
2024年度の再エネ賦課金の値上りが決定
さらに、2024年3月19日に経済産業省から、2024年度の 再エネ賦課金 単価が発表され、
「3.49円/kWh」になる事も決まっています。
現在、再エネ普及のために、再エネで創った電気を「優遇された価格」で買い取るFIT(固定価格買取制度)が実施されています。
その FIT(固定価格買取制度)で買い取られる電気に必要な費用を負担するために電気の使用者から集められる料金のことを「再エネ賦課金」と言います。
(再エネ賦課金 は、電気料金に加算されて支払われています)
再エネ賦課金の推移
再エネ賦課金 のこれまでの推移は、以下のようになっています。
(2012年度のみ8月分~4月分の期間になります)
新電力ネット「再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移」、経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します」を元に作成
グラフのように、2023年度は「1.4円/kWh」に大きく値下りしたのですが
2024年度は、値下り以前の価格より上がることになりました。
これにより、1kWhあたり「2.09円」値上りすることになるので、
標準的な家庭(1か月400kW使用)に換算すると、負担額が年間約10,000円増えることになります。
この「再エネ賦課金 の値上り」は、5月の電気料金からになりますので
「5月からは電気料金が上がる」ことになります。
前述の「激変緩和措置の終了」も合わせて、5月6月には電気料金が大きく値上がりになる見通しです。
短期予測:2024年5月6月、2025年の電気料金の見通し
これらの情報も踏まえて、直近の「2024年4月~6月」の大手電力会社10社の電気料金の見通しを見て行きましょう。
簡単に概要をまとめると、以下のようになる見通しです。
5月:10社値上げ(補助政策の縮小・再エネ賦課金の値上り)
6月:10社値上げ(補助政策の終了)
4月については、燃料価格の影響により、各社の値上げ・値下げの価格が報道されています。
結論から申し上げますと、4月の値上がりに関してはそこまで大きなものではありません。
しかしながら、5月6月は大きな値上りになってしまう見通しです。
2024年4月の値上げ・値下げ
まず「2024年4月の値上げ・値下げ」について見て行きましょう。
2024年4月については、大手電力会社の電気料金の見通しが公開されています。
※一般家庭(低圧)の1か月の電気代における値上げ金額になっています。
(電気料金単価ではありませんのでご注意ください)
東北電力:52円値下げ↓
東京電力:16円値上げ↑
中部電力:93円値上げ↑
北陸電力:50円値下げ↓
関西電力:65円値上げ↑
中国電力:53円値下げ↓
四国電力:62円値下げ↓
九州電力:20円値上げ↑
沖縄電力:46円値下げ↓
出典:gooニュース「4月電気代6社値下がり ガスは大手全4社上昇」
6社が値下げ
北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力の6社は
「値下げ」になる予定です。
最大で1.3%ほどの値上げ
値上げとなる4社の内で最も値上げ金額の多い、中部電力の93円の値上げでも
一般家庭の1か月の電気料金を7,000円ほどとすると「最大でも1.3%ほど」の値上げであることが分かります。
最大1.3%%の値上がりが大きいかどうかは、解釈が分かれるところかと思いますが
これまでの値上がりと比較すると、そこまで大きな値上がりではないと言えます。
2024年5月の値上り
さらに、2024年5月は「大手電力会社10社全社」で電気料金が値上がりする見通しで、
値上り幅もとても大きくなる可能性があります。
これは、政府による電気料金の補助政策「激変緩和措置」が縮小することと、
冒頭でご紹介したように「再エネ賦課金 が値上がりする」ことが大きな要因です。
※激変緩和措置 については、のちほど詳しく解説します。
政府の補助政策の縮小
現在、政府による補助政策「激変緩和措置」によって、下記のような補助が実施されています。
高圧:1kWあたり1.8円の値引き
(特別高圧は補助の対象外)
この補助額は4月使用分までとなっており、5月はその半額となる下記の補助額になることが決まっています。
高圧:1kWあたり0.9円の値引き
この「補助額の縮小」を
前述の4月の値上げと比較するために、1か月の一般家庭の電気料金に換算すると
月540円~720円の値上がりになる見通しになります。
出典:東京都環境局公式サイト「平成26年度東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 報告書」
再エネ賦課金の値上り
さらに、前述のように、5月からは 再エネ賦課金 も値上がりします。
1か月の一般家庭の電気料金に換算すると「月627円~836円」の値上りになる見通しです。
「補助額の縮小」と合わせると、
5月は4月に比べて「月1,167円~1,556円」の大きな値上がりになる見通しです。
2024年6月の値上り
そして、冒頭でご紹介したように、2024年6月には政府の補助政策が終了する見通しです。
終了となった場合には、5月に半額になった分の補助額がそのまま無くなるので
2024年5月と比較して月540円~720円の値上がりになる見通しになります。
5月6月を合わせると、大きな値上がりに
5月6月の値上りを合わせると、4月と比較して
の値上りとなるため、非常に大きな値上がりになると言えます。
2025年頃まではこの状況が続く見通し
さらに、この電気料金の値上りの大きな要因となっている「天然ガスの値上り」は
2025年頃まで続く見通しとなっています。
ウクライナ情勢から、ロシア産以外の天然ガスの需要が増えていますが、
同時に世界的に脱炭素の流れが大きくなっているため、ガス田などへの開発・投資が減っており、
足りない天然ガスを増やすこともなかなか難しいのが現状です。
そのため、2025年頃までは天然ガスが世界的にソールドアウト状態になると考えられています。
後半に詳しく解説いたします。
参照元:日テレニュース「2024年 どうなる電気料金~5月から補助金縮小で値上げに備えよ」
長期予測:2050年までの電気料金の見通し
さらに、2050年までの長期的な電気料金の見通しも見て行きましょう。
2050年までの燃料価格の長期的な見通し
まず「2050年までの燃料価格」の長期的な見通しについて、EIA(米国エネルギー省エネルギー情報局)による長期予測から見て行きましょう。
このように、天然ガスも石炭も、2050年まで値上がりが続いて行くと予測されています。
天然ガスと石炭による火力発電は、日本の電源構成の大半を占めているため、
天然ガスと石炭の値上りは、そのまま日本の電気料金に直結します。
他の電源で賄えばいいのでは?
となると、火力発電以外の発電の電源構成率を上げて行くのが解決策になると考えられます。
その「火力発電以外の発電方法」で特に有力視されているのが
「再生可能エネルギー」と「原子力発電」です。
再生可能エネルギー
日本政府は、2030年までの電源構成における再エネの割合を36~38%とする目標を掲げており
また、2050年までには50~60%とする目標を掲げています。
この達成は現状から見ると非常に難しい目標であるのですが、
仮に達成したとしても、まだまだ火力発電への依存は残る見通しです。
参照元:自然エネルギー財団「2050年エネルギー戦略はどうあるべきか」
原発再稼働
もうひとつの発電方法が、原子力発電です。
しかしながら、原子力発電所の再開には、安全性の面から国内からも反対の声が多いなど
簡単に規模拡大することはできません。
2050年における電気料金の展望については、正確に予測することはできませんが
このような状況を加味すると、まだ燃料価格高騰の影響を受けている可能性もあり、
この先も電気料金の値上りが継続する可能性があると考えるのが自然です。
政府による補助制度「激変緩和措置」
2024年の電気料金には、政府の補助政策「激変緩和措置の終了」が大きく関わってきます。
この「激変緩和措置」とはどのような制度なのか解説していきます。
「激変緩和措置」とは?
激変緩和措置 とは、1kwhあたり定められた金額が
燃料調整額 から値引きされる、政府による補助制度です。
発電の燃料費に応じて、電気料金を調整する数値で、
電気料金の目安にすることもできます。
(火力発電などで使用される燃料費などが該当します)
燃料調整額 は、燃料の価格変動に応じて、電気料金に反映され
プラスだけでなく、燃料費が安い時期にはマイナスにもなります。
燃料費の価格変動の3~5カ月後に、電気料金に反映されます。
2023年2月~2023年10月
激変緩和措置 は、開始当初は「2023年2月~2023年10月」での実施予定でした。
その内、2023年2月~2023年9月までは、下記のような値引き幅で行われていました。
高圧:「3.5円/kWh分」
※特別高圧は、補助の対象外になっています。
最終月の9月は、上記の半額の値引き幅で、下記のような金額になりました。
高圧:「1.8円/kWh分」
「激変緩和措置」が2024年5月まで延長決定
そして、2023年10月で終了予定だった「激変緩和措置」は
2024年1月使用分まで延長されることになり、さらにのちに5月まで延長されることになりました。
ただし、延長となった2023年11月から2024年4月使用分までの値引き率は、2023年10月と同じ
(2023年9月までの補助の半分)になります。
高圧:「1.8円/kWh分」
そして前述のように、2024年5月は補助額がさらに半額になります。
高圧:「0.9円/kWh分」に半減
2023年10月~2024年4月までの値引き率
延長も含めて、激変緩和措置の補助額をまとめると、下記のようになります。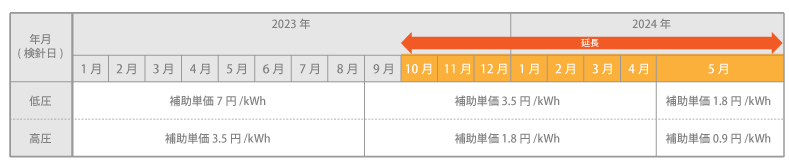
2024年5月から値上がり
このように「激変緩和措置」は2024年5月に減額され、6月からは補助が無くなる見通しですので
2024年5月6月に電気料金が値上がりになると考えられます。
電気料金の推移
続いて「電気料金のここ数年の推移」について
「低圧」「高圧」「特別高圧」それぞれ、全国平均と電力会社ごとでご紹介します。
(2024年3月現在公開されている、2023年12月までの電気料金の推移をご紹介します)
低圧には「従量電灯」と「低圧電力」の2種類の電気料金があります。
「従量電灯」
「使用した電気量によって毎月の電気料金が決まる電気料金プラン」のことです。
一般家庭で使用される家電製品など、電力をあまり使用しない機器に対して使われています。
「低圧電力」
「従量電灯よりも多くの電気を使用する、業務用機器向けの電力プラン」です。
業務用の使用電力が大きい機器(エレベーターや業務用エアコンなど)に使用されます。
三相式200Vを使用し、コンセントの形状も異なるため一般的な家電を使用することはできません。
法人はどちらを使う?
法人の場合には、このどちらかを契約している場合もあり、
また両方を契約しているというケースもあります。
「低圧(従量電灯)」の電気料金の推移
まずは家庭で使用する電気料金と同じ「低圧(従量電灯)」から見て行きましょう。
全国平均の推移
全国の平均値で見ると、下記のような推移になっています。
(電力市場の平均販売単価の推移になります)
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
ただし、特に2023年5月頃を境に、電力会社によって推移が異なってきています。
電力会社ごとの推移も見てみましょう。
電力会社ごとの推移
下記は、電力会社ごとの電気料金の推移です。
「凡例」をクリックして頂くと各電力会社のグラフの表示/非表示が切り替えられます。
ご契約の電力会社の推移を確認してみてください
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
低圧(従量電灯)の推移の特徴
低圧(従量電灯)の推移の特徴を見てみると、下記のようなことが言えます。
2.電力会社によっては、2023年6月頃から大きく値上がり
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
4.2023年10月に大きく値上がり
順番に解説していきます。
1.2023年2月に大きく値下がり
全国平均も各電力会社も共通して、2023年2月に大きく値下がりしています。
これは前述した、政府の「激変緩和措置」による値下がりが主な要因です。
2.電力会社によっては、2023年6月頃から大きく値上がり
また、電力会社によっては2023年6月以降に大きな値上がりの傾向が見られます。
北海道電力、東北電力、北陸電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
これは2023年6月の大手電力会社各社の値上げによる影響が大きいと見られます。
ただし、電力会社によっては横ばいや値下がりになっているケースもあります。
<2023年6月の値上げについて、詳しくはこちら>
参照:日本経済新聞「家庭の電気代、6月から14〜42%値上げ 電力7社発表」
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
ほとんどの電力会社において、2023年7月頃から値下がりの傾向になっています。
これは、天然ガスなどの燃料価格の値下がりが主な要因であると考えられます。
4.2023年10月に大きく値上がり
2023年10月には、どの電力会社も大きく値上がりしています。
これは前述した政府の補助「激変緩和措置」の補助額が半額になった影響です。
「低圧(低圧電力)」の電気料金の推移
続いて、業務用機器向けの電力プランである「低圧(低圧電力)」の推移も見て行きましょう。
全国平均の推移
全国の平均値で見ると、下記のような推移になっています。
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
低圧(従量電灯)と同様に、電力会社ごとの推移も見てみましょう。
電力会社ごとの推移
下記は、電力会社ごとの電気料金の推移です。
「凡例」をクリックして頂くと各電力会社のグラフの表示/非表示が切り替えられます。
ご契約の電力会社の推移を確認してみてください
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
低圧(低圧電力)の推移の特徴
低圧(低圧電力)の推移の特徴を見てみると、下記のようなことが言えます。
2.電力会社によっては、2023年6月頃から大きく値下がり
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
4.2023年10月に大きく値上がり
1.2023年2月に値下がり
低圧(従量電灯)と比べると月ごとのアップダウンは大きくなりますが、
傾向として値上がりし続け、2月から値下がりしていることが分かります。
2.電力会社によっては、2023年6月頃から大きく値下がり
ほとんどの電力会社において、同じような推移をしていますが
関西電力と九州電力は、2023年6月頃から大きく値下がりしています。
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
低圧(低圧電力)の場合、月のアップダウンが激しいので分かりにくいのですが、
低圧(従量電灯)同様に、ほとんどの電力会社において、2023年7月頃から値下がりの傾向になっています。
これは、天然ガスなどの燃料価格の値下がりが主な要因であると考えられます。
4.2023年10月に大きく値上がり
低圧電力も、従量電灯と同様に2023年10月に大きく値上がりしています。
これも「激変緩和措置」の補助額が半額になった影響もあるのですが
低圧電力は、例年10月は値上がりする傾向にありますので、そのふたつの要因から
大きくグラフも跳ね上がっています。
「高圧」の電気料金の推移
続いて、高圧の電気料金の推移を見て行きましょう。
全国平均の推移
全国の平均値で見ると、下記のような推移になっています。
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
低圧と同様に、電力会社ごとの推移も見てみましょう。
電力会社ごとの推移
下記は、電力会社ごとの電気料金の推移です。
「凡例」をクリックして頂くと各電力会社のグラフの表示/非表示が切り替えられます。
ご契約の電力会社の推移を確認してみてください
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
高圧の推移の特徴
高圧の推移の特徴を見てみると、下記のようなことが言えます。
2.電力会社によっては、2023年4月頃から値上がり
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
4.2023年10月に大きく値上がり
順番に解説していきます。
1.2023年2月に値下がり
高圧も低圧と同様に、2023年1月まで値上がりが続いていますが
2023年2月からは値下がりしています。
ただし、値下がり幅は低圧ほど大きくはありません。
これは前述したように、政府による補助の金額が、高圧は低圧に比べて安いことが要因です。
(低圧は7円/kWh、高圧は3.5円/kWhの補助額)
2.電力会社によっては、2023年4月頃から値上がり
また、2023年4月以降に、高圧の価格改定を行った電力会社は値上がりしています。
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
ほとんどの電力会社において、2023年7月頃から値下がりの傾向になっています。
これは、天然ガスなどの燃料価格の値下がりが主な要因であると考えられます。
4.2023年10月に大きく値上がり
高圧も、激変緩和措置の補助額が半額になったことで、2023年10月に大きく値上がりしています。
ただし、2023年2月の値上りと同様に、補助額が低圧の半額であることから
値上がり幅は低圧より少なめになっています。
「特別高圧」の電気料金の推移
次に、特別高圧の電気料金の推移を見て行きましょう。
全国平均の推移
全国の平均値で見ると、下記のような推移になっています。
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
同様に、電力会社ごとの推移も見てみましょう。
電力会社ごとの推移
下記は、電力会社ごとの電気料金の推移です。
「凡例」をクリックして頂くと各電力会社のグラフの表示/非表示が切り替えられます。
ご契約の電力会社の推移を確認してみてください
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」
特別高圧の推移の特徴
特別高圧の推移の特徴を見てみると、下記のようなことが言えます。
2.電力会社によっては、2023年4月頃から値上がり
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
4.2023年10月も大きな変化はなし
順番に解説していきます。
1.2023年2月も大きな変化はなし
低圧や高圧では、2月に大きく値下がりしていましたが、
特別高圧に関しては、そのような傾向はみられません。
これは、政府による補助「激変緩和措置」が、特別高圧は対象外となるためです。
2.電力会社によっては、2023年4月頃から値上がり
また高圧と同様に、2023年4月以降に特別高圧の価格改定を行った電力会社は値上がりしています。
3.2023年7月頃から値下がり傾向に
低圧や高圧と同じように、ほとんどの電力会社において、
2023年7月頃から値下がりの傾向になっています。
これは、天然ガスなどの燃料価格の値下がりが主な要因であると考えられます。
4.2023年10月も大きな変化はなし
こちらも2月同様に「激変緩和措置」の対象外であるため、
低圧や高圧にあったような大きな変化はありません。
電気料金が上下する「3つの要因」
ここまで、電気料金の推移の解説をしてきましたが、
そもそも近年の電気料金の値上がりは、何が原因で起こっているのでしょうか?
より掘り下げて電気料金が上下する「3つの要因」について解説していきます。
近年、電気料金が上下する要因は、主に下記の3つであると言われています。
順番に解説していきます。
1.天然ガス(LNG)と石炭の価格変動
まずひとつめの要因が「天然ガス(LNG)と石炭の価格変動」です。
天然ガス(LNG)と石炭の「価格推移」
初めに、天然ガス(LNG)と石炭の価格がどのように推移しているか見てみましょう。
天然ガス(LNG)価格の推移
出典:一般社団法人エネルギ―情報センター「天然ガス価格の推移」
燃料調整額とのの比較
前章で解説した、燃料調整額 と比較するため、燃料調整額(低圧/東京電力)の推移(※)も並べています。
ご覧いただくとお分かりの通り、天然ガスの価格の上下の数か月後に
燃料調整額 も上下していることが分かります。
※燃料調整額の推移のみを比較するため、激変緩和措置 による値下げは含まれていません。
冒頭でも解説した通り、
燃料調整額 は、燃料価格の変動の数か月後に反映されるしくみになっていますが、
こうして推移を見ると、そのようになっているのが分かります。
天然ガスの推移の特徴
1.2022年10月まで価格が上昇
天然ガス(LNG)の価格は、上下しながら高騰し続け、
2021年4月と2022年10月を比較すると「3倍近く」の価格に高騰しています。
2.2022年11月から値下がり
また、グラフを見ると2022年11月から値下がりし続け、
2023年6月には、2年前の高騰直後くらいの水準に落ち着いています。
3.2024年1月から値上がり
2024年1月から少し値上りしていますので、3月~4月頃の電気料金に影響してくる可能性があります。
天然ガス(LNG)の価格は、3ヶ月分の原油価格をベースに変動するしくみになっています。
つまり、原油価格の上下は、そのまま天然ガス(LNG)の価格の上下に直結します。
ここでは原油価格の推移まではご紹介しませんが、
「原油価格が変動した」際には、同時に天然ガス(LNG)の価格も変動し
さらに火力発電の燃料として使用されているため、電気料金も変動するのです。
石炭価格の推移
燃料調整額とのの比較
燃料調整額 と比較するため、石炭の燃料費率の高い、北陸電力の推移も比較として並べています。
天然ガス同様、石炭価格の上下の数か月後に 燃料調整額 も上下していることが分かります。
石炭価格の推移の特徴
石炭価格も、2021年12月以降値上がりが続いていますが、
2022年11月以降は、天然ガス以上に大きく値下がりの傾向にあります。
「天然ガスと石炭の価格」がなぜ「電気料金」に影響する?
日本の電源構成における割合が非常に高い
天然ガス(LNG)や石炭の価格高騰が、なぜここまで電気料金の値上がりに直結するのでしょうか。
それは、
からなのです。
日本の電源構成
日本の電源構成は、下記のような比率になっています。
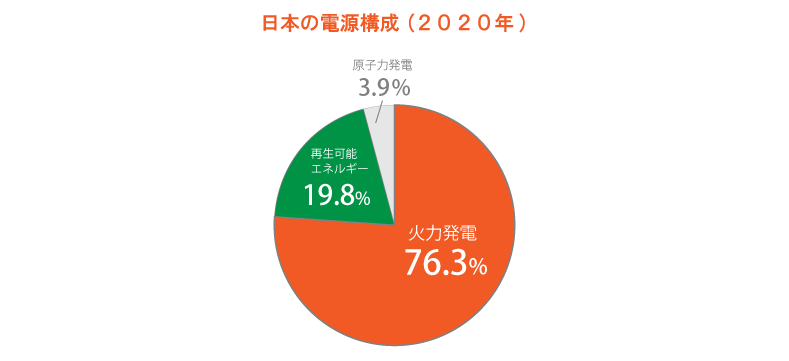
出典:資源エネルギー庁「時系列表(令和4年4月15日公表)」
このように「日本の電力の76.3%は火力発電で賄われています」
火力発電の燃料別比率
さらに火力発電を燃料別に見て行くと、
「天然ガス(LNG)が51.1%」「石炭が40.6%」を占めているのが分かります。
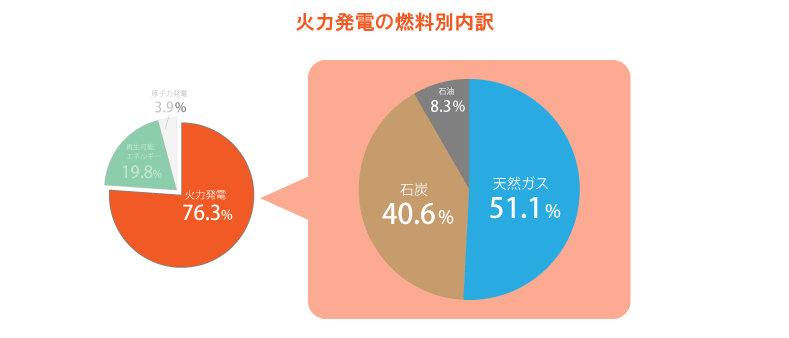
「天然ガスと石炭」は、日本の電源構成全体の「70%」を占める
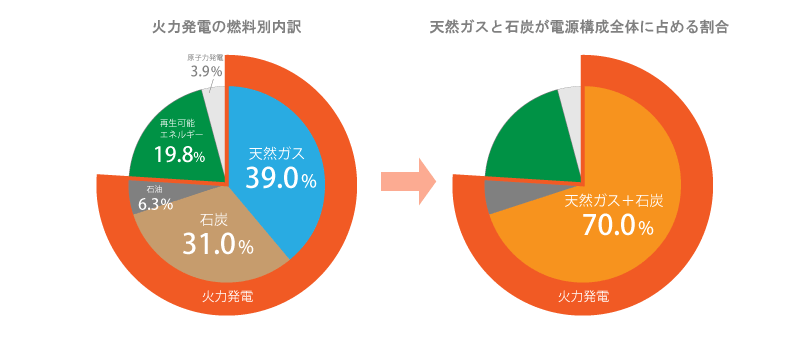
さらに、電源構成全体を燃料別に見てみると、左図のような構成になります。
天然ガスと石炭の占める割合は、右図のように
日本の電源構成全体の「70%」を占めています。
日本で電気を創る燃料の70%が値上がりしているため、電気料金への影響は大きいのです。
天然ガス(LNG)と石炭の「価格変動の原因」
2021年から続く天然ガス(LNG)と石炭の価格高騰は、主に下記3つが原因と言われています。
またその反対に、2022年11月からの値下がりの原因は下記と言われています。
順番に解説していきます。
価格高騰の原因
[原因1] ウクライナ情勢による影響
ロシアによるウクライナ侵攻を受け、アメリカやEUが経済制裁を実施しています。
ロシアからの天然ガスや原油、石炭の輸入を制限する、
またはロシアが輸出を制限する動きが生まれてきています。
ロシアの化石燃料のシェアは非常に大きい
化石燃料の産出国というと、中東をイメージする方が多いかもしれませんが、
実はロシアが占める割合もとても大きくなっています。
ロシアは、下のグラフのように
天然ガスの輸出額が1位、石炭の輸出額3位、石油の輸出額2位と
化石燃料の輸出額で上位を占めており、またシェアも大きいことが分かります。
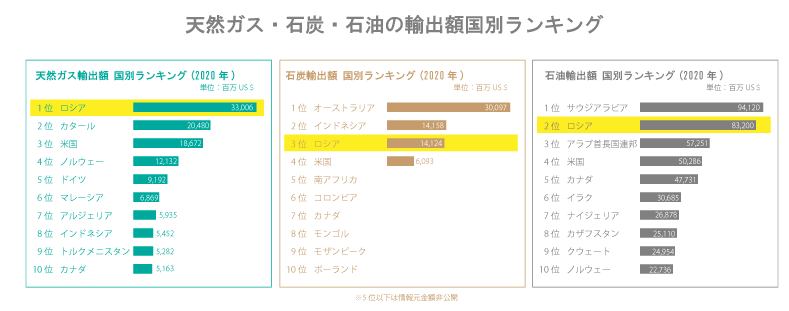
こうした化石燃料の輸出国としてのシェアが大きいロシアの天然ガスや原油、石炭の輸出が制限されることで、価格高騰の大きな原因になっています。
原因2.脱炭素社会の影響で「天然ガス(LNG)の需要が増加」
天然ガス(LNG)の大きな特徴の一つは「CO2排出量が他の化石燃料より少ない」点です。
全世界的に進められている脱炭素社会への流れから、
従来の石炭や石油から、CO2排出量の少ない天然ガス(LNG)に切り替える流れが
特に中国を中心に進んでおり、天然ガス(LNG)の需要が増加し、価格高騰の一因になっています。
原因3.円安の影響
天然ガス(LNG)や石炭価格の高騰は、円安による影響も受けています。
出典:新電力ネット「為替レート(USドル/円)の推移」
ただし、2022年10月をピークとして、11月以降は少し落ち着いていましたが
2023年6月からまた円安に大きく傾いています。
為替の面から言えば、2021年初期と比較して「約1.5倍」まで上向いていますので
天然ガスや石炭の輸入においては、いまだに大きな影響があると言えます。
値下がりの原因
[原因] 暖冬による燃料需要の低下
2022年は、ヨーロッパやアメリカが暖冬であったため、
11月頃から、天然ガスと石炭の需要が減り、値下がりにつながっています。
燃料調整額 は、燃料費の価格変動の3~5カ月後に反映されますので
2022年11月の値下げが、2023年3月以降には 燃料調整額 の値下がりにつながり
電気料金の値下がりにつながっているのです。
このように、複数の要因が重なって、天然ガス(LNG)と石炭が変動しており、
電気料金に大きな影響を与えています。
2.国内の電力供給力不足
続いて、価格高騰の原因となっているのが「国内の電力供給不足」です。
国内の電力供給量を見てみると、
2010年と比較して2020年には「12.9%」も減少していることが分かります。
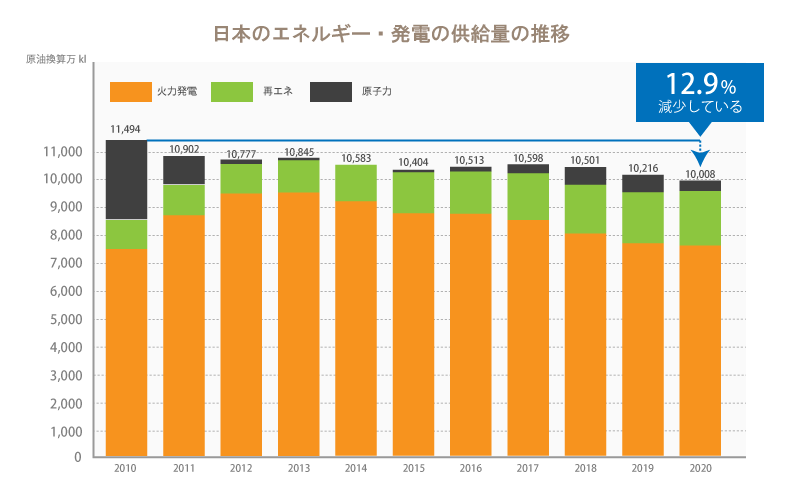
出典:資源エネルギー庁「集計結果又は推計結果(総合エネルギー統計)」を元に作成
それでは「国内の電力供給不足」の原因を見て行きましょう。
原因1.原発停止による影響
前述の国内供給量のグラフから、原子力発電の供給量の推移を抜き出したものが下記のグラフです。
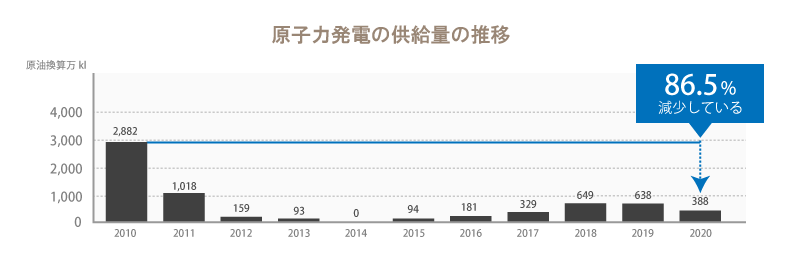
図のように、2011年の東日本大震災を契機に、原発は停止が続いており、
再稼働している発電所もありますが、2010年と比較すると「86.5%」減少しています。
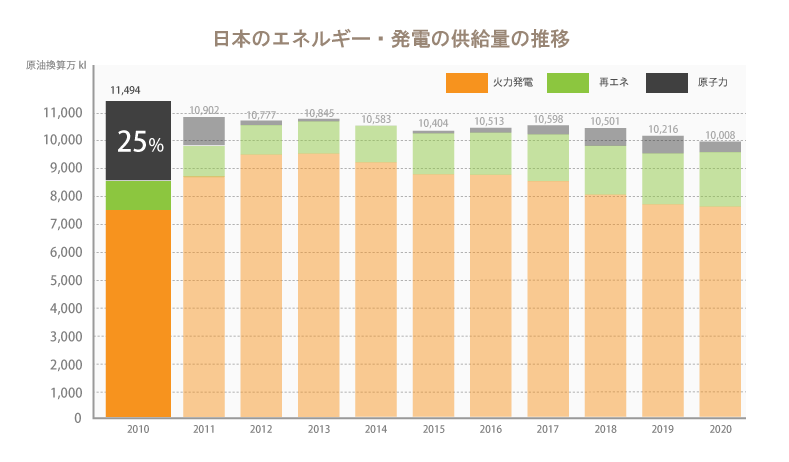
また、2010年の全体に占める原子力発電の割合は「25%」に上っていました。
実に全体の4分の1を占めていた原子力発電の大半が無くなったため、全体の供給量にも大きな影響を与えているのです。
原因2.火力発電の縮小
規模が縮小しているのは原子力発電だけではありません。
火力発電も規模を縮小しています。
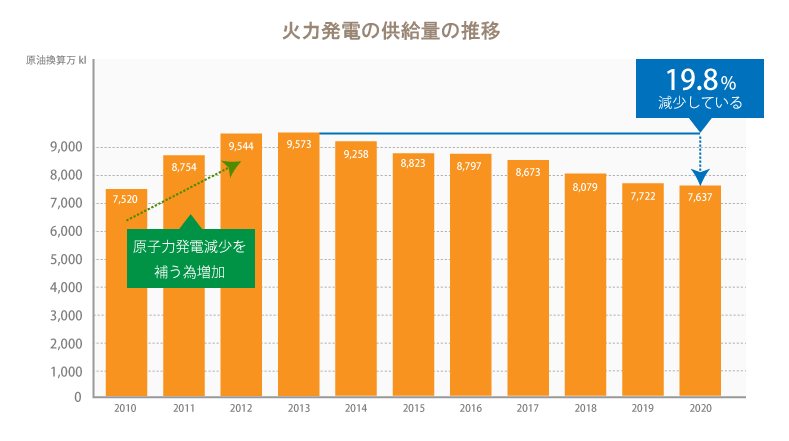
図のように、最も高かった2013年と比較して、2020年には「19.8%」減少しています。
2010年から2013年にかけては増加していますが、
これは前項で解説した原子力発電の減少を補うために火力発電の稼働を増やした結果です。
しかしながら、原子力発電が減少しているにもかかわらず、
2013年以降は右肩下がりに火力発電の供給量が減少しています。
古い火力発電所の休廃止
2016年の 電力自由化 によって、電気料金の競争が激しくなったことから、
大手電力会社が採算性の悪い「老朽化した火力発電所」の休廃止を進めたことが、
火力発電減少の要因のひとつです。
再エネの導入拡大
また、火力発電は、燃料を燃焼して発電するため「CO2排出量が多い」点が大きなデメリットです。
「CO2削減」に向けて、CO2を排出しない「再エネの導入拡大」が進んだことも
火力発電減少の要因のひとつです。
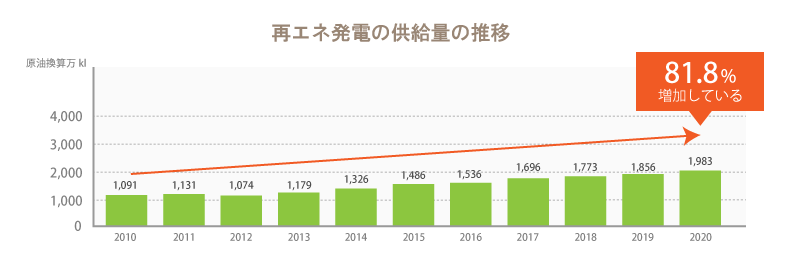
再エネは天候や気候にも左右され、安定した電力供給ができないというデメリットがあります。
その悪天候時などの供給不足は、従来は火力発電が補っていましたが
相次ぐ火力発電所の休廃止によって補いきれなくなって来ています。
供給不足から価格上昇に
このように、原子力発電と火力発電が減少し、再エネ発電は増加していますが
最初にご紹介したように、全体の電力供給は不足しています。
供給量に余裕があれば、電気料金も値下がりにつながりますが
供給量もひっ迫している為、
電力需要が上がると 日本卸電力取引所(JEPX)に流通する電気が減り、価格上昇に繋がるのです。
3.再エネ賦課金の価格変動
3つ目の要因が「再エネ賦課金 の価格変動」です。
再エネ賦課金 については冒頭で詳しく解説しましたが、電気料金の推移に影響を与えて来ています。
電気料金値上げへの企業の対応策
ここまで、電気料金の高騰から始まる推移や原因について解説してきました。
冒頭でもお伝えしたように、2024年は電気料金の値上がりが予想されます。
それでは、企業はどのような対策を取れば良いのでしょうか?
企業の電気料金高騰への対応策
企業の電気料金高騰への対応策としては、
大きく分類すると下記のようなものが代表的です。
対応策2. 社内で節電に取り組む
対応策3. 省エネに効果的な設備を導入する
これらの方法は、それぞれについて詳しく解説した記事がありますので
そちらをご紹介しながら、抜粋して効果的な方法をご紹介して行きます。
対応策1. 再エネを導入する
まずひとつめの対応策が「再エネを導入する」ことです。
再エネで自社で電気を創り、それを使用する手法です。
「電気代が高くなるなら、電気を買わない」という方法です。
自家消費型太陽光発電
その再エネ導入の代表的な手法が「自家消費型太陽光発電」です。
自家消費型太陽光発電 とは、自社の屋根などに太陽光発電を設置して、
発電した電気を自社で使用する手法です。
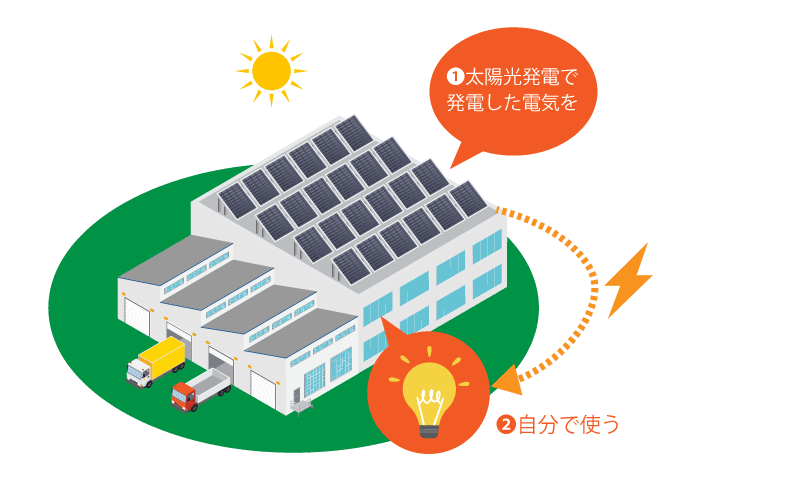
つまり、自社で太陽光発電を使って電気を創るので、発電した分の電気は買う必要が無くなります。
自家消費型太陽光発電 について詳しくは、下記の記事をご参照ください。
補助金制度も活用できる
自家消費型太陽光発電 導入には、ここ数年もさまざまな補助金制度が
国や都道府県、市区町村から出ています。
2024年3月現在、令和6年度の補助金制度も少しずつ公募が開始され始めています。
こちらに詳しくまとめていますので、よろしければご参照ください。
オンサイトPPA
前述のような 自社所有モデル の 自家消費型太陽光発電 は、自社で発電した分だけ電気を購入する必要が無くなるため、
電気料金削減には効果的な施策ですが「導入コストがかかる」点がデメリットでもあります。
導入コストをかけずに、自家消費型太陽光発電 を導入する手段として「オンサイトPPA」という手段もあります。
オンサイトPPA についても、下記記事に詳しく解説していますので
よろしければご参照ください。
対応策2. 社内で節電に取り組む
コストをかけずに行う省エネ方法としては、
地味ですが「人の手による省エネ」も有効な対応策のひとつです。
空調の「人の手による省エネ」
中でもより効果的な手法が、空調に対する「人の手による省エネ」です。
あらゆる業種において、最も電気使用量が多い傾向にあるのが「空調」でもあり
節電を行う際にも効果的でもあります。
当たり前すぎる施策に見えますが、その効果を具体的な数字にしてみると
「対応策としてあなどれない」ことが分かります。
人の手による空調の省エネの施策と効果一覧
人の手による空調の省エネの施策と、その効果一覧を下記にまとめてみました。
| 施策 | 省エネ効果の目安 | 頻度等 |
| フィルターの清掃 | 冷房時で約4% 暖房時で約6%の省エネ | 2週間に1度が目安 |
| 室外機の温度環境や障害物の見直し | 室外機の風通しが悪いと電気代は1.5倍に。 | |
| 熱交換器(フィン)の清掃 | 長期間行わなかった場合に比べて約27%の節電 | ・工場/店舗・・・約3年 ・事務所/オフィス・・・約5年 ・福祉施設/医療施設・・約5年 |
| 部屋に応じた適正温度の設定 | 室温の目安は「夏期 28℃、冬期20℃」で 1℃最適化するだけで約10%の削減が可能。 | |
| 冷水出口温度設定値の変更 | 冷水温度を7℃から9℃へ上げると 使用電力は8%削減 | |
| 外気導入量の削減 | ・オフィスビル・・・節電効果5% ・卸・小売店・・・節電効果8% ・食品スーパー・・・節電効果4% ・医療施設/福祉施設・・・節電効果2% ・製造業・・・節電効果8% | |
| 残熱利用による運転時間の短縮 | 約6%の省エネ (8時間勤務のオフィスで30分間空調停止した場合) | |
| 分散起動 | 冬の商業施設で約9%の削減効果 | |
| ナイトパージ | 約5%の省エネ (ナイトパージシステム 利用) | |
| ブラインド等で遮光する | ブラインド無しの場合と比較して10.6%の省エネ効果 |
こうして具体的な効果を数字で見ると、あなどれない効果があることが分かります。
これらの施策について詳しくは、下記の記事でひとつひとつ解説していますので
よろしければこちらも参考にしてみてください。
対応策3. 省エネに効果的な設備を導入する
続いて有効な施策が「省エネに効果的な設備を導入する」ことです。
空調への省エネ
前項でもご紹介したように、
空調は、あらゆる業種において、最も電力消費量が多いカテゴリになります。
空調機器を最新機種に更新する
「省エネに効果的な機器を導入する」というと
「空調機器を最新機種に更新する」という手段が最も効果は大きいのですが、
大きなコストがかかるという大きなデメリットがあります。
空調機を買い替えずにできる省エネ方法
そこで、空調機器を買い替えずにできる、比較的コストを抑えて行える省エネ施策を
前項でご紹介した「空調の省エネ」の記事から、いくつかご紹介します。
1. 断熱塗装
空調機器そのものではなく、断熱塗装を建物に施すことで
空調機器の負担を下げることができます。室内温度を7℃下げた例もあります。
2. 空調を効かせるエリアを仕切る
ビニールカーテン等で空調を効かせるエリアを絞ることで
空調に使用する電気料金を減らすことができます。
3. エネルギーマネジメントシステムによる空調制御
エネルギーマネジメントシステムを導入することで、外気温などとも調整して空調を制御し
電力消費を効率的にする手法もあります。
4. α-HT(流体攪拌装置)
配管に挿入するだけで、最大30%の省エネ効果が得られる機器として
最近注目されているのが、α-HT(流体攪拌装置)です。

図のように、配管に挿入して冷凍機油を攪拌(かくはん)することで
圧縮機の負担を下げる機器です。
業種ごとの省エネテクニック
ご紹介した内容以外にも、業種ごとの省エネテクニックをまとめた記事もありますので、
よろしければお役立てください。
「電気料金値上がり対策」が「企業の競争力強化」に
電気料金の値上がりは「サービスや商品価格の値上げ」や「利益の減少」に繋がってしまいます。
現在、原材料費の高騰も大きな問題になっていますが、
こちらは、企業単位で具体的な対応を行うのは難しいと言えます。
「電気料金値上がり」は、まだ対応策がある点が救いではあります。
「電気料金値上がり」に対策しておくことは、価格競争力や利益増強など
企業の競争力強化にも繋がるのです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
2024年3月現在の電気料金の値上がり状況がご理解頂けたのではないかと思います。
直近では、再エネ賦課金 の値上りや、政府の激変緩和措置の終了などによって
大きく電気料金が値上がりとなる可能性も高まっていますが、
長期的にも、燃料価格などが値上がりしていく可能性が高いと考えられています。
対応策も本記事でいくつかご紹介していますが、
各対策についての詳細を解説した記事もあわせて参考にして頂ければ幸いです。
本記事が、御社の電気料金値上がり対策のお役に立てれば幸いです。