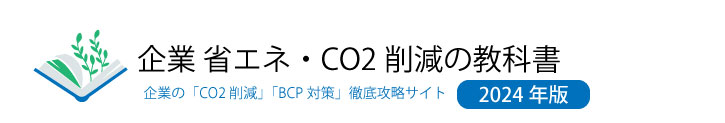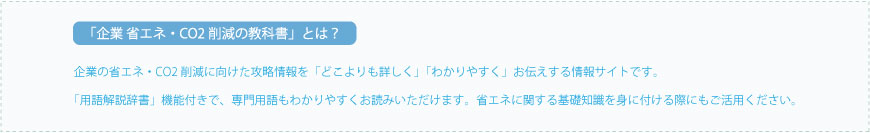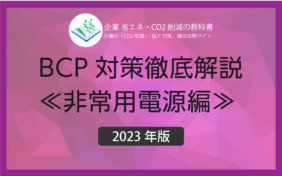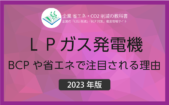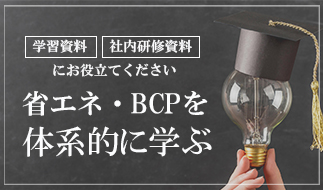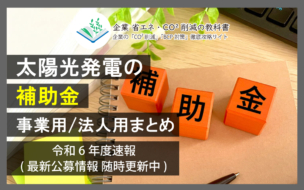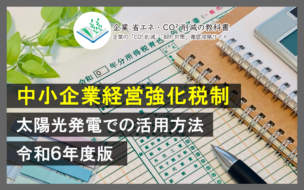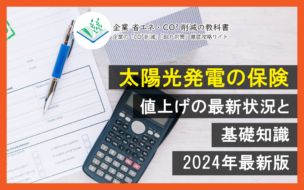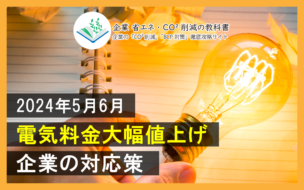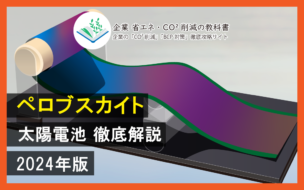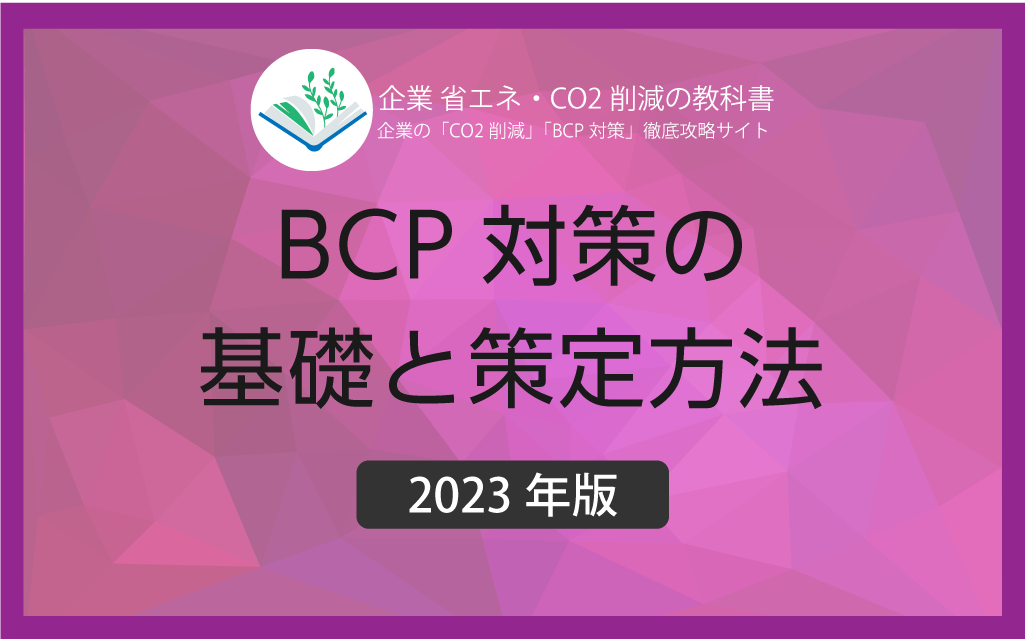
※2023年4月12日 最新情報に更新しました。
2011年の東日本大震災に始まり、
2018年以降は大型台風や豪雨などの大規模災害が頻発しています。
企業が、自然災害などの予期せぬ緊急事態から、
事業を守っていくために行うべきなのが「BCP対策」です。
「BCP対策」という言葉はよく耳にするけれど、
このように「良く分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか?
このページでは
「どうやって策定していくのか」
BCP の基礎知識だけでなく
これから BCP対策 を策定していく方に参考になる情報をわかりやすく解説いたします。
ぜひ御社の危機管理や事業継続戦略にお役立てください。
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
BCP対策(事業継続計画)とは?
まず BCP対策 とはどういう意味なのでしょうか?
BCPとは?
この BCP対策 の「BCP」とは、
「Business Continuity Plan」の略で「事業継続計画」という意味です。
その名の通り「事業を継続するための計画」のことなのですが、緊急事態に限った計画として用いられる為「緊急事態においても事業を継続するための事前計画」と解釈すると分かりやすいでしょう。
2.企業が被害を受けた際に
3.その後も「事業を継続していく為」に
4.予め対策として立てておく計画
それが「BCP」の意味で、その為の対策を「BCP対策」と言います。
BCPにおける「緊急事態」とは?
BCP対策 における緊急事態は、地震などの災害を指して言及されることが多いですが、
事業存続を脅かすあらゆる不可避な事態を指しています。
・自然災害(地震/台風/集中豪雨/水害/落雷など)
・感染症(コロナウィルス/新型インフルエンザなど)
・事故(設備の大規模事故や従業員の巻き込まれる事故)
・戦争や紛争、テロ
・その他事業継続を脅かす緊急事態すべて
BCPとBCM、防災の違い
BCP に取り組み始めると「BCM」や「防災」という似た言葉が出てきます。
意味をはき違えてしまうとうまく理解できませんので、これらの違いについて押さえておきましょう。
BCPとBCMの違い
BCP対策 において、似た言葉として BCM という言葉が良く出てきます。
BCM は「Business Continuity Management」(事業継続マネジメント) の略で
BCP「Business Continuity Plan」(事業継続計画)とは、少し意味が違ってきます。
BCPが事業継続の「計画」であるのに対して、
BCMは事業継続の「マネジメント」を意味します。
つまり事業継続に向けた計画に対して、その体制をマネジメントするのが「BCM」です。
この「マネジメント」を意味する BCM が、
BCP を組織に浸透させる体制つくりには重要になってきます。
防災とBCPの違い
BCP と「防災」は非常に似ており、意味を混同される方も多くいらっしゃいます。
その違いも確認しておきましょう。
このように、目的が少し違ってきます。
但し BCP の中には「従業員や地域住民の人命を守る」「社屋や設備を守る」
といった要素も含まれますので、BCP の中には 防災 も一部含まれています。
近年のBCP対策の歴史~対策すべき事態の広がり~
次に、BCP対策 の必要性が近年どのように変化しているのか?
流れを追っていきましょう。
2011年:東日本大震災
「BCP対策」は欧米では1970年代、日本国内でも1980年代から議論が始まり、
主にシステムの分野での対策を中心に取り組まれていました。
しかし BCP対策 が国内で注目されるようになったのはやはり
「東日本大震災」が大きなきっかけです。
被災した企業が数多く倒産に至った経緯などから
「BCP対策」が日本国内でも注目されるようになりました。
2018年:西日本豪雨
東日本大震災以後、BCP対策 は主に地震に焦点を当てて取り組まれてきました。
しかしながら2018年の「西日本豪雨」や
2019年の「令和元年8月の前線に伴う大雨」「令和元年台風第15号」「令和元年台風第19号」など
台風や水害による被害や大規模停電なども発生し、企業に大きな被害を及ぼしました。
このことから BCP対策 は地震だけでなく水害など他の自然災害にも目を向けられ始めました。
2020年:コロナウィルスの国内感染拡大
そしてさらに BCP対策 に新たな概念を加えたきっかけが
「コロナウィルスの感染拡大」です。
それまでの地震や水害への BCP対策 の浸透により、
食料の備蓄や施設の耐震、非常用電源の確保などへの取組みは強化されていましたが
「感染症」への対策を充分に実施していた企業は少なく、
マスクやアルコールの備蓄、テレワーク体制づくりや行政からの要請による休業など
想定外の事態に日本社会全体が困惑しています。
2020年以降は、こうした「感染症」に対する BCP対策 の重要性が高まり、
充分な対策が必要になってきました。
災害が企業に与えた影響、連鎖倒産
東日本大震災の関連倒産件数は「1,946件」
東日本大震災では、2011年~2019年の期間での関連倒産が「1,946件」に及んでおり、
企業への影響の大きさが分かります。
さらに東日本大震災における倒産件数1,946件のうち、
事業所などが直接損壊を受けた「直接型」は202件(同10.6%)で
取引先・仕入先の被災による販路縮小などが影響した
「間接被害型」が1,701件(構成比89.3%)となっています。

出典:東京商工リサーチ「“震災から8年”「東日本大震災」関連倒産状況(2月28日現在)」
災害時の企業への影響は自社だけでなく、取引先まで広く及ぶのです。
コロナウィルス感染が及ぼす影響
現在大きな被害を出しているコロナウィルス。
2023年4月10日時点で5542件の企業倒産が判明しています。
上記の東日本大震災時の直接型が202件ですので、実に27倍もの数に至っているのです。
一説では「戦後最大の全世界的な不況」になるのではないかとも言われています。
「この状況下で大型地震が起こったら?」
確かに目の前の状況への対応が急務ですが、
今後の事業運営の中でも、こうした事態に対応できる BCP を意識していくことが重要です。
BCP対策3つの目的
BCP対策 の概略や重要性がお分かり頂けたところで、
次に「BCP対策 3つの目的」について解説して行きます。
1.従業員を守る、事業を守る
1-1.従業員を守る
まず最も大切になってくるのが「従業員を守る」ことです。
災害や感染などから、従業員の生命や健康を守る。
これがまず最も重要な目的です。
【地震対策】建物の倒壊を防ぐための耐震や免震への取組み
【自然災害対策】避難場所/避難経路の確保。避難訓練の実施
【感染症】感染を防ぐための通勤やテレワークの整備
1-2.事業を守る
続いて「事業を守る」ことが重要です。
「事業を守る」ことは、従業員の生活や取引先の事業継続にも大きく関わってきます。
また「社会に与える影響」も考慮しておく必要があります。
・被災時に優先して残す事業を選定して対策を検討しておく。
・非常用電源を整備し、操業停止期間を最小限に食い止める。
・テレワーク環境下でも事業継続できるようシステムや体制を構築しておく。
2.企業価値を高める
BCP対策 は従業員や事業を守ることが主な目的ですが、
それ以外にも大きなメリットがあります。
BCP対策 にしっかりと取り組んでおくことは
「企業としての競争力を高める」ことにも繋がるのです。
順番に解説していきます。
東日本大震災での倒産は「間接被害型」が89.3%
前述のように、東日本大震災による倒産の89.3%は間接倒産によるものです。
つまり、取引先が被災した場合その原因で自社が倒産するリスクも大きいのです。
どの企業も間接被害は避けたい
取引先を選ぶ際「災害に遭ったら倒産するリスクが高い」企業を選びたくないのは当然です。
つまり他の企業にとっても
「災害に遭ったら倒産するリスクが高い」企業との取引は極力避けたい。
または「リスクを分散するために大きな取引は避けたい」と考えるのが自然です。
BCP対策は企業競争力を高める
つまり BCP対策 をしっかり行っている企業は、対策していない企業よりも取引先として選ばれやすく
大きな取引を受注しやすくなります。
すなわち「企業価値を高める」ことに繋がるのです。
大型地震に加えて、水害や感染症などあらゆる緊急事態が近年頻発しています。
今後はより一層「BCP対策 にしっかり取り組んでいるかどうか」が取引先選定の大きな指標になってくると予想されます。
3.CSR
続いて重要になってくるのが「CSR」です。
BCP対策 をしっかり行い従業員や サプライチェーン を守る姿勢を社会に示すことは、
企業イメージの良化にも繋がります。
中でも「地域社会への取組み」が分かりやすい例です。
DCP対策~災害対策における地域への貢献~
BCP対策 と近い言葉に「DCP対策」という言葉があります。
これは「地域継続計画(District Continuity Plan)」の略で、
要するにBCP対策が企業であるのに対して「地域」における災害時の継続計画を意味しています。
例えば企業が再エネを導入し災害時の電源を確保した際に、それを地域の方々に開放することで、地域貢献を実現することができます。
この DCP対策 は必ずやらなければならないものではありませんが、
特に地域との関わりが深い企業の場合「いざという時に何もしなかった」ことが
企業イメージを損なうことに繋がる可能性もある為、注意が必要です。
BCPの策定方法
BCP の概略から目的までお分かりいただけたところで、
次に「BCP の策定方法」について説明していきます。
BCP 策定には大きく分けて「コンサルタントに依頼する」「ガイドラインを参考にしながら自社で作る」の2種類の方法があります。
順番に見ていきましょう。
1.外部コンサルタントや行政書士に依頼する
「BCP対策 について細かく熟知するのは難しい」「時間も割けない」という方には、
BCPコンサルタントや行政書士に依頼し、打合せながら BCP対策 を策定するという選択肢があります。
1-1.BCPコンサルタントに依頼する
BCPコンサルタントに依頼する場合、行政書士に比べてシステム面に明るいという特徴があります。
経営コンサルティングがメインで積極的にBCPコンサルティングには取り組んでいない企業もあれば、
策定の補助だけでなくアドバイスまで行ってくれる企業など、サービスにはさまざまなタイプがあります。
御社に合った方式で一緒に BCP を策定してくれるコンサルタントを見つけていくと良いでしょう。
費用
費用面は100万円~200万円と行政書士より高くかかるのが一般的です。
BCPコンサルタントのサービス例
1-2.行政書士に依頼する
次に行政書士に依頼する場合ですが、コンサルタントに比べて法務には強く、
システム面では少し弱い傾向があります。
社内にシステムに明るい人材がいるようでしたら、行政書士に依頼する選択も良いでしょう。
費用
費用面は30万円~40万円とコンサルタントより安い点がメリットです。
外部に依頼するメリット・デメリット
以下に、外部に依頼するメリット・デメリットをあげておきます。
メリット
・最適な BCP対策 を策定しやすい。
・時間がかからない
・誤った策定や漏れを防ぎやすい。
デメリット
・費用がかかる。
こんな方は外部依頼がおすすめ
・設備費用も想定しながら、策定にも費用がかけられる。
・策定を急ぎたい。
・選任者を置いて進める体制が無い。
このような企業の方は、外部に依頼し打合せながら進めていくとスムーズです。
2.BCPガイドラインを参考にする
続いて、自社で独自に策定する方法です。
自社で策定する場合には、中小企業庁から出されているガイドラインを参考にしながら進めていくことができます。
中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」
中小企業庁から「中小企業BCP策定運用指針」が公表されています。
こちらも経済産業省の「事業継続計画策定ガイドライン」同様に一連の流れが解説されていますが、
「入門コース」「基本コース」「中級コース」「上級コース」と
策定する方の知識に合わせて選択できるようになっています。
外部に依頼するか?自社で作るか?
外部に依頼する場合も自社で策定する場合も、まずは中小企業庁の中小企業BCP策定運用指針をひと通り読んでみることをおすすめします。
その上で自社で策定できるかどうか?判断できるという点と
外部に依頼する場合にも、自社で経営者や担当者が予め理解しておく必要があるからです。
まずは本記事で大枠をとらえて頂き、一歩深堀りを進めて頂ければと思います。
感染症対策に向けたBCP策定
上記にご紹介したガイドラインですが、
こちらにはまだ今回のコロナウィルスのような感染症への対策は盛り込まれていません。
ゆくゆく感染症を盛り込んだガイドラインも公表されるかもしれませんが、
今回のコロナウィルス感染を受けて、自社で「やっておくべきだったこと」を
BCP 策定に盛り込んでおくことも重要です。
・社内及び施設内での感染を防ぐための殺菌/滅菌機器の導入
・マスクや消毒液の備蓄
・テレワーク体制における業務変更のガイドライン策定
・テレワークを行う為のシステム導入
・社内のデジタル化/ペーパーレス化
・デジタル印の導入
・既存事業のEC化
まとめ~実効性のある計画策定を
いかがでしたでしょうか?
BCP対策 について、大枠や目的、策定方法などについてもお分かり頂けたのではないかと思います。
世にあるテンプレートをそのまま使えば形にはできますが、形にするのがゴールではありません。
自社の環境を踏まえて実効性のある計画にすることが非常に重要です。
緊急事態に備えた設備の導入、食料などの備蓄、また実地訓練なども行い、
実際の災害に対して機能して初めて BCP を策定した意味があります。
BCP は「転ばぬ先の杖」。
その杖はしっかりとしたものを用意しておきましょう。
BCP対策に欠かせない「非常用電源について」も詳しい記事がありますので、
本記事と一緒に合わせてお読みください。