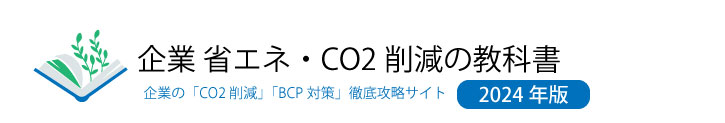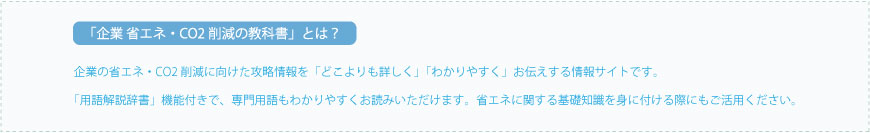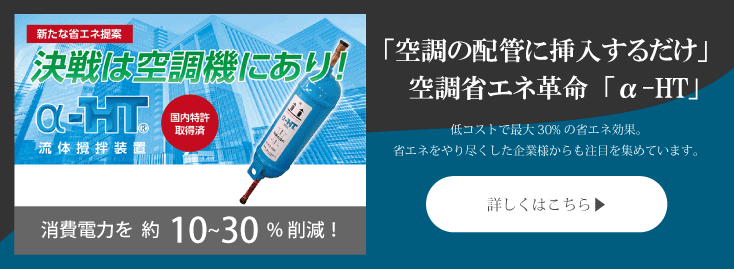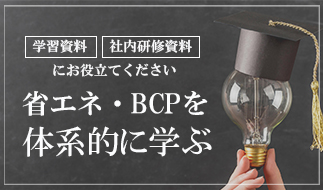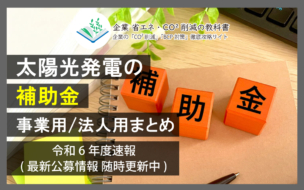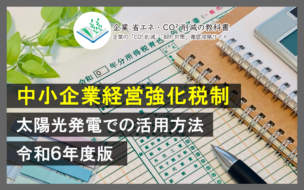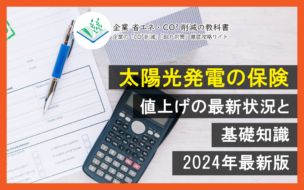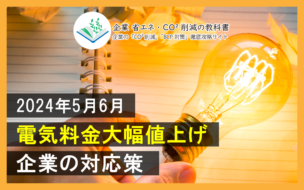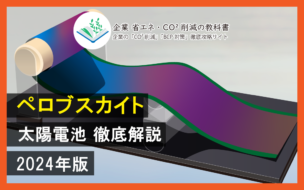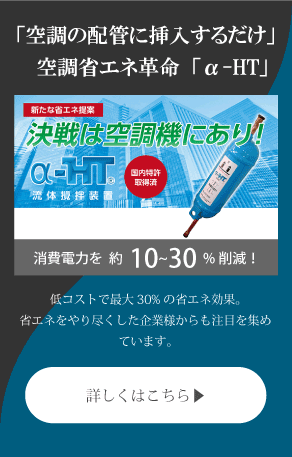※2023年9月12日 最新情報に更新しました。
2021年から続く「電気料金の値上がり」は、2023年に入ってから少し値下がりしていますが
まだまだ以前ほどの価格には収まっておらず、企業にとって頭の痛い問題です。
そんな「電気料金削減」や「CO2削減」の土台として
「使用エネルギーの見える化」に活用できるのが
「エネルギーマネジメントシステム」です。
「どんな効果があるの?」
「どうやって省エネに繋げるの?」
「どのように導入するの?」
など、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の基礎知識から、活用方法や製品例まで
わかりやすく解説して行きます。
ぜひ御社の省エネの参考していただければと思います。
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
目次
「エネルギーマネジメントシステム」とは?
それではまず、エネルギーマネジメントシステム とはどんなものなのでしょうか?
「エネルギーマネジメント」とは?
まず、エネルギーマネジメントシステムの解説の前に
「エネルギーマネジメント」について理解しておく必要があります。
エネルギーマネジメントとは、
2.分析して最適な運用に改善していくことで
3.エネルギーの利用状況を改善し、省エネなどを行うこと
を言います。
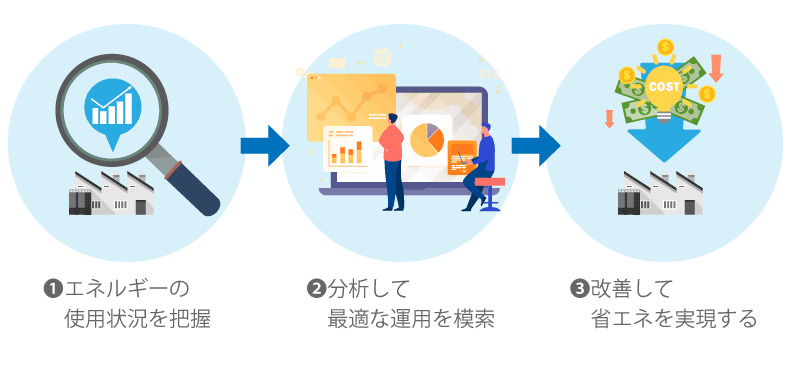
つまり、名称そのままで「エネルギー」を「マネジメント」する活動のことを言います。
改善すべきポイントをおさえることが重要
こうした改善活動を続けて、効果的に省エネを行っていくためには
的確に改善すべきポイントをおさえることが重要になってきます。
そのためには「いつ」「どこで」「どのような」改善すべきポイントがあるのか?
・各設備ごとの時間ごとのエネルギー利用状況
なども把握できるかどうかが大きな鍵になってきます。
人の手で把握するのは困難
しかしながら人の手だけでは、そような細かいエネルギー使用状況を把握するのは困難です。
そこで、エネルギーの利用状況を細かく効率的に取得するためには
システムを使って自動取得する必要があります。
「エネルギーマネジメントシステム」が重要な役割を果たすことになります。
「エネルギーマネジメントシステム」とは?
エネルギーマネジメントシステム とは、
施設内の各設備の使用エネルギーの「見える化」を自動的に行ってくれるシステムのことです。
エネルギーマネジメントシステムは
Energy Management Systemの頭文字から「 EMS 」とも呼ばれます。
設備ごとのエネルギー利用状況を把握できる
エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することで、
設備ごとのエネルギー利用状況を把握することが可能になります。
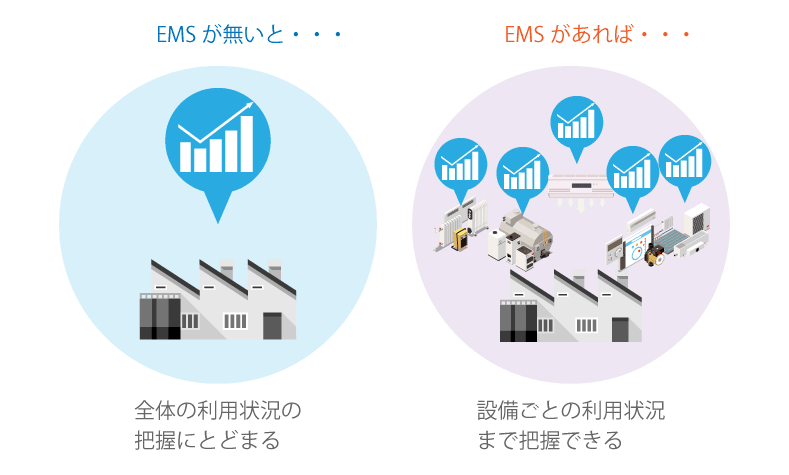
エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入することで、
工場内などの施設内の設備の「いつ」「どこで」「どのように」
エネルギーが使用されているかを「自動的に」「見える化」できるようになるのです。
「エネルギーマネジメントシステム」の役割
ただし、エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、
導入するだけで省エネが実現できるソリューションではないので注意が必要です。
エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、あくまで
使用エネルギーを「見える化」するためのツールです。
「見える化」の重要性
しかしながら「見える化」は、省エネを進める上で大変重要なポイントになります。
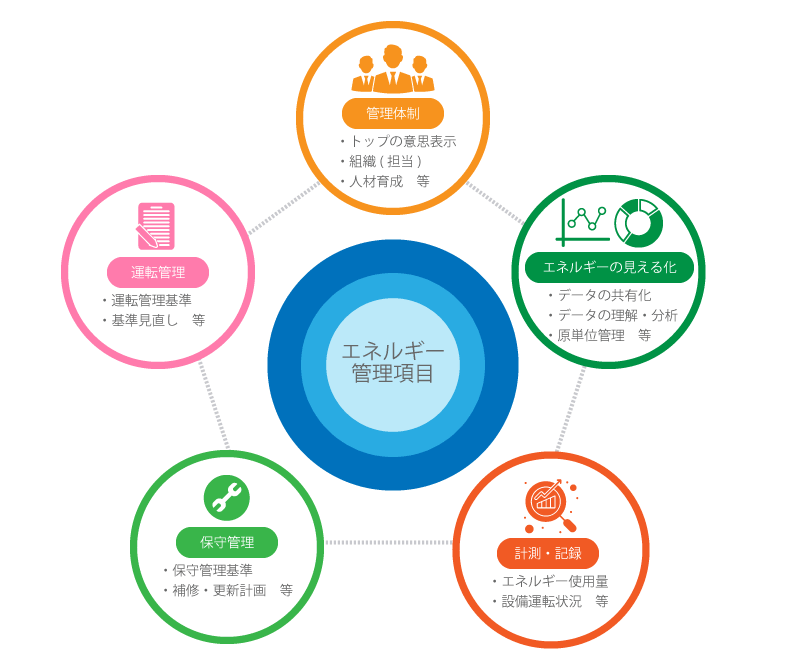
出典:一般財団法人 省エネルギーセンター「ビルの省エネルギーガイドブック2022」を元に作成
上の図は、エネルギー管理を進める流れをまとめたものです。
このフローを見ても分かる通り、エネルギー管理と省エネ活動においては、
「見える化」がとても重要な役割を果たしており、
「見える化」を土台に、さまざまな省エネ活動が行われることが分かります。
特に規模の大きな施設や事業ほど、
エネルギーマネジメントシステム(EMS)の果たす役割がとても重要になってきます。
EMSは省エネの土台
エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、
他の省エネ機器のように、それそのものが省エネ効果を出すものではありません。
しかしながら、様々な機器を省エネに導いていく為の「土台」となるシステムとして
重要な役割を担っているのです。
EMSのメリット・デメリット
それでは次に、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の
メリット・デメリットについて見て行きましょう。
エネルギーマネジメントシステムのメリット
1.エネルギー消費の把握を自動化できる
エネルギーマネジメントシステム(EMS)は自動的にデータを取得する為、
人の手をかける必要がありません。
2.正確な情報を得ることが出来る
人の手で行う場合、ヒューマンエラーがどうしても起こってしまいます。
システムを用いることで、そうしたエラーも無く正確な情報を取得できます。
3.リアルタイムで情報収集できる
省エネにおいて「どの時間帯にエネルギーが多く使われているか?」の把握は重要です。
設備単体で見た際には無駄が少なく見えても、時間帯によっては無駄が出ていることがあるからです。
これも人の手で行う事のは困難ですので、システムを用いる必要があります。
4.エネルギー効率の悪い機器を特定できる
老朽化や故障などで、エネルギー効率が悪くなった機器を特定することが出来ます。
そうした機器を買い替える、修理するなどで省エネを実践できます。
5.社内で成果を共有しやすい
「見える化」で数値化やグラフ化することによって、
経営層や、協力を仰ぐべき社内にも分かりやすく成果を共有できます。
エネルギーマネジメントシステムのデメリット
1.初期費用が高額になるケースも・・・
大規模な設備導入と比較すればコストを抑えられることも多いのですが、
規模の大きな工場や事業所、計測が必要な機器が多数に及ぶ施設に導入する場合には、
初期費用が高額になる可能性があります。
2.運用には専門知識が必要
さらに、運用には専門知識が必要になる点も大きなデメリットのひとつです。
見える化した、エネルギーの使用状況から問題点を適切に見つけ、
改善策を見出すための知識がある人材の採用や、育成が必要になってきます。
EMSによる4つの省エネアプローチ
エネルギーマネジメントシステム(EMS)によって「見える化」したデータを分析し改善策を検討していく中で、考えられる方法が4つあります。
1.ダウンサイジング
EMSによって既存の設備よりも低容量の設備へ買い替えする必要性が見つかることがあります。
このことにより、コストダウンや設備のスリム化などが行えます。
2.チューニング
EMSによって見つかった改善点により
設備の運転時間設定や温度の調節などコストをかけずに省エネを実現することも可能です。
チューニングを行うだけでも、大幅にコストダウンできるケースもあります。
3.コミッショニング
現場の運用性能を分析して必要な調整や改修、運転の最適化を行うことで、性能を検証して実現することです。
4.ピークカット
ピークカット は最も取り組まれている、電気の基本料金を抑える方法です。
私たちの使用している電気の基本料金は、過去一年間で最も多く使った時間帯の買電量で決まります。
そこで「買電量が最も多くなる時間帯」の買電を抑えることで基本料金を抑えることができます。
これを「ピークカット」と言います。
※ピークカット については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ピークカットは、抑えられるコストも大きいため多くの企業が実践しています。
エネルギーマネジメントシステムの種類
続いて、エネルギーマネジメントシステム の種類について解説して行きます。
エネルギーマネジメントシステム は、導入する施設によって呼び方が変わります。
実際のサービス導入時のためにも、覚えておきましょう。
FEMS(フェムス)
FEMS は、Factory Energy Management System の略で「フェムス」と読みます。
工場に対する EMS のことをこのように呼びます。
従来行われてきた受配電設備のエネルギー管理に加え、
工場における生産設備のエネルギー使用や稼働状況を把握することでエネルギーの動きの合理化や向上をはかり、
生産と連動した最適化を行う エネルギーマネジメントシステム です。
BEMS(ベムス)
BEMS は、Building Energy Management System の略で「ベムス」と読みます。
事業所やビル、店舗などの空調・照明などに行う エネルギーマネジメントシステム(EMS)です。
建物全体のエネルギーの動きを「見える化」することに加え、
建物の設備機器などを最適な形で制御することによる エネルギーマネジメントシステム です。
HEMS(ヘムス)
HEMS は、Home Energy Management System の略で「ヘムス」と読みます。
HEMS(ヘムス)は、住宅で使用する エネルギーマネジメントシステム(EMS)です。
HEMS(ヘムス)は、家庭用の EMS ですので、企業向けのシステムではありませんが、簡単にご紹介しておきます。
CEMS(セムス)
CEMS は、Community Energy Management System の略で「セムス」と読みます。
CEMS(セムス)は、地域全体のエネルギーを管理するための
エネルギーマネジメントシステム(EMS)です。
地域全体の太陽光などの発電所や、電気を使用する家庭や企業などの
エネルギーを管理するシステムです。
大手各社のEMS製品紹介
それでは エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入する場合、
どのような製品があるのでしょうか?
エネルギーマネジメントシステム(EMS) は、導入する設備によって呼び名が変わります。
製品によってはそれぞれ特化したものもありますので、理解しておきましょう。
大手各社の EMS の製品紹介
それでは代表的な大手各社の製品の一例をご紹介します。
FEMS や BEMS など、御社に合った製品はどのようなものがあるのか?確認してみましょう。
EMS全般
東芝三菱電機産業システム株式会社:エネルギーマネジメントシステム
FEMS(工場向けEMS)
BEMS(ビル/店舗向けEMS)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
エネルギーマネジメント について、工場や企業に注目したマネジメントの基礎知識や方法など
ご理解いただけたのではないかと思います。
それに加えて制御を行うシステムや設備のこと
・EMSを用いることで、人の手を使わず自動で正確な情報が取れる。
・EMSには設備ごとに違った呼び名をされることがある。
「省エネの教科書」では、企業に活用できる省エネの情報を、随時お伝えしていきます。
みなさまの省エネ活動にお役立て頂ければ幸いです。