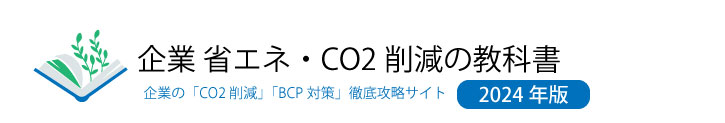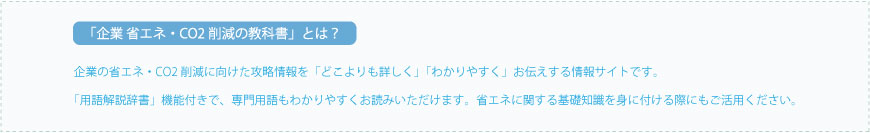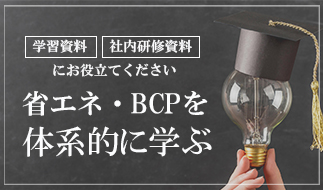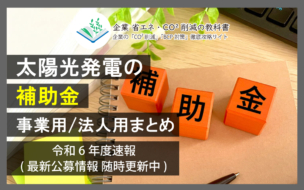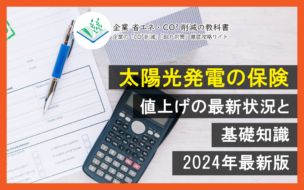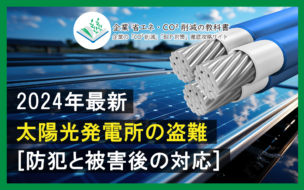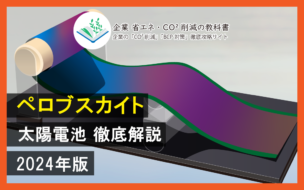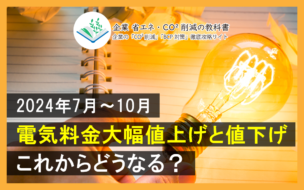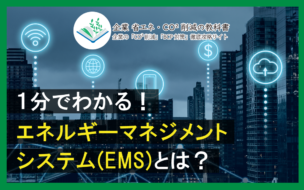新型コロナウィルスやウクライナ情勢などの不安定な社会情勢を受けて、
「安定した投資」を行いたい企業様や個人投資家の方が増えています。
そうしたニーズを満たす投資方法のひとつが「太陽光発電投資」です。
しかしながら、FIT(固定価格買取制度)の値下がりなどが原因で
と聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、太陽光発電投資 の基本的な情報から、メリットやリスク、
2023年現在も行える「太陽光発電投資」について、わかりやすく解説して行きます。
これから、太陽光発電投資 をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
太陽光発電投資とは?
まず、太陽光発電投資 とは、どのようなものなのか?
簡単に解説していきます。
太陽光発電投資のしくみ
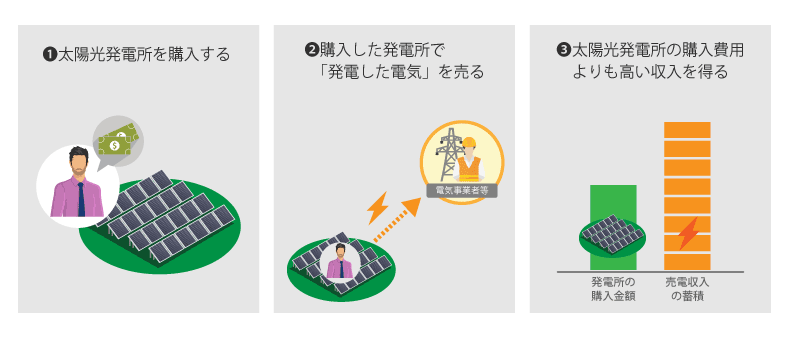
一般的な 太陽光発電投資 は、図のように
2. 購入した発電所で「発電した電気」を売る
3. 太陽光発電所の購入費用よりも高い収入を得る
という投資方法です。
FIT(固定価格買取制度)
この「太陽光発電投資」は、FIT(固定価格買取制度)が始まったことで
人気の投資方法になりました。
FIT(固定価格買取制度)とは?
FIT(固定価格買取制度)とは、太陽光発電などの再生可能エネルギーで発電した電気を
「決まった単価」「決まった年数」で、
電気事業者 が買い取ってくれる、国による制度です。
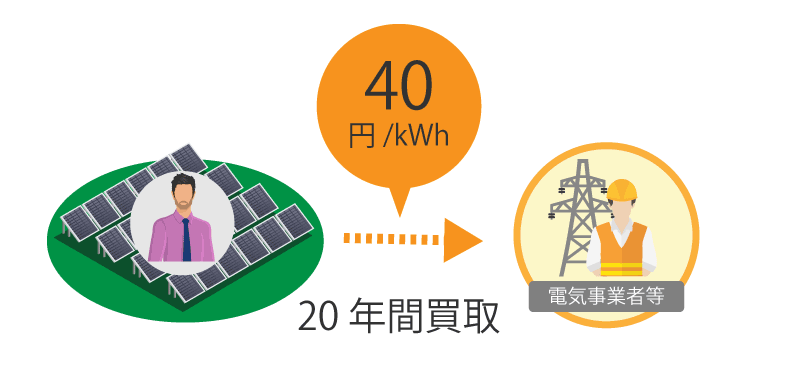
上のイラストは、FIT(固定価格買取制度)が始まった2012年度の例です。
しくみになっています。
例えばこの場合、年間50万kW発電する太陽光発電所を1,000万円で購入した場合、
20年間で2,000万円の売電収入を得ることができ、購入金額の倍の収入を得ることが出来るのです。
FIT は、「固定価格買取制度」を意味する「Feed-in-tariff(フィードインタリフ)」の略です。
太陽光発電投資の利回り
太陽光発電投資 を行う際に「どれほどの収益性があるか」を判断するのに必要な指標が
「利回り」です。
利回りとは?
太陽光発電投資における「利回り」とは
「年間売電収入」の割合
のことを言います。
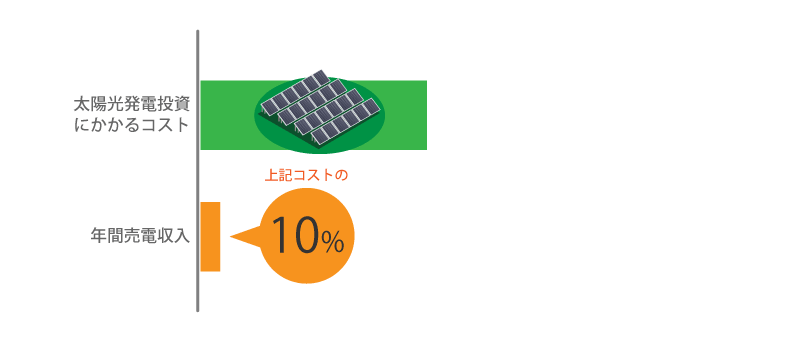
たとえば上図のように、年間売電収入が「太陽光発電投資 にかかるコスト」の10%の場合
「利回り」は「10%」ということになります。
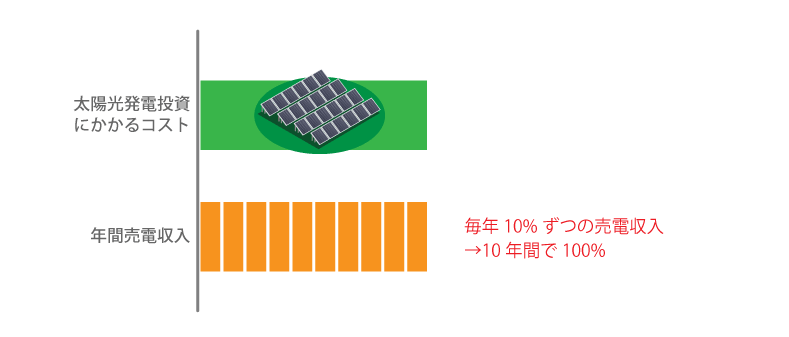
利回り10%の場合、10年間運用すると「10%×10年」で「100%」になるため
「太陽光発電投資 にかかるコスト」を10年間で回収できることになります。
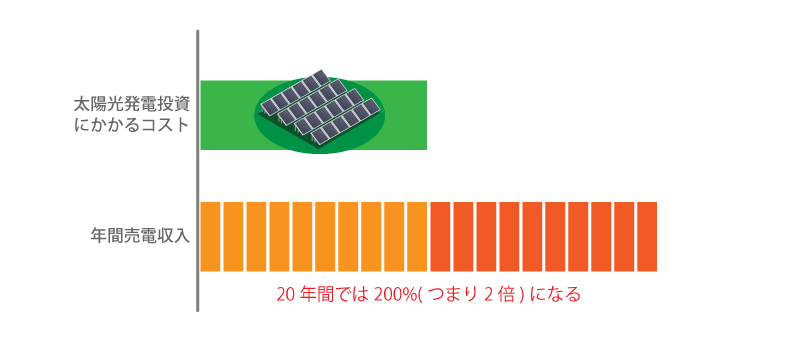
そして20年間運用すると
「太陽光発電投資 にかかるコスト」の2倍の売電収入を得ることができることになります。
つまり、利回りが高いほど、
「初期費用の回収が早く」「投資に対する収入も大きくなる」のです。
実質利回りと表面利回り
この「利回り」で注意しなければならないのが
「実質利回り」と「表面利回り」の2種類がある点です。
実質利回りと表面利回りの違い
前述した「太陽光発電投資 にかかるコスト」に何が含まれているかの違いです。
「実質利回り」とは?
実質利回りの場合には「太陽光発電投資 にかかるコスト」は
「発電所の初期導入費用」だけでなく
「メンテナンス費用」や「税金」「保険料」「修繕費用」などの
「ランニングコスト」も含めて計算された「利回り」です。
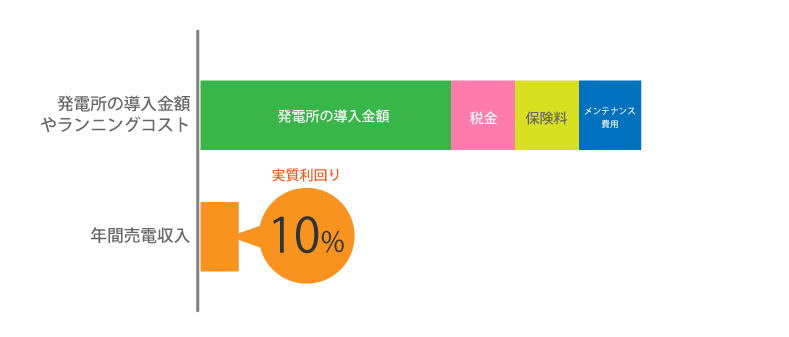
この実質利回りは、実際に 太陽光発電投資 を行った際の利回りに近いものになります。
「表面利回り」とは?
それに対して「表面利回り」とは、
「メンテナンス費用」や「税金」「保険料」「修繕費用」などのランニングコストを含まず、
「発電所の初期導入費用」だけを費用として計算された利回りです。
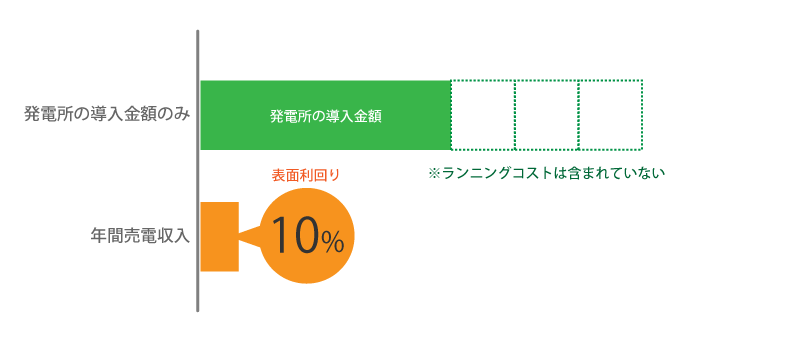
表面利回りは、実際の 太陽光発電投資 よりも収益性が高く見えてしまいます。
太陽光発電投資 物件を販売する企業などが、表面利回り で提示する背景としては
上記のランニングコストが、発電所オーナーによって異なってくるため計算に入れていない
という面もあります。
「利回り」の指標が大きく違ってくる
このように「実質利回り か」「表面利回り か」によって
利回り として提示されている指標の収益性が大きく変わってきてしまいます。
物件を比較するときの注意
別の企業などが売り出している 太陽光発電投資 物件においても、
A社は 実質利回り、B社は 表面利回り で算出しているなど、
利回り の根本的な基準が異なるケースもありますので、物件の比較には注意が必要です。
「〇〇費用は含まない」
また、利回り の算出において「〇〇費用は含まない」と記載されている場合もあります。
太陽光投資物件を選ぶ場合には、こうした利回りの計算基準もしっかり確認しておくことが重要です。
太陽光発電投資のメリット
太陽光発電投資 のしくみをおさえたところで
次に、太陽光発電投資 のメリットを見て行きましょう。
安定したローリスクな投資
太陽光発電投資 の最も大きなメリットが「安定したローリスクな投資」である点です。
前述したように、FIT(固定価格買取制度)により、売電単価が固定されているため
安定した収入を見込むことができます。
株式投資や不動産投資と比較しても、この安定性が大きな魅力になります。
高利回り
FIT(固定価格買取制度)の年度によっては固定買取単価も高く
7%~10%の高利回りの物件もあります。
利回りの高さも、株式投資や不動産投資と比較しても 太陽光発電投資 のメリットと言えます。
太陽光発電投資のデメリットとリスク
しかしながら、太陽光発電投資 にもデメリットやリスクはあります。
天候に左右される
太陽光発電による発電量は、天候に大きく左右されます。
FIT(固定価格買取制度)によって、売電単価は固定されていますが
となりますので、売電単価が固定されていても
天候によって発電量が想定より悪くなると、売電収入も下がってしまいます。
NEDOによる日射量データベースの活用
こうした「天候による発電量の変化」によって収益を損なわないために
NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術開発機構)による日射量データベースを元に
発電所の発電量を予測し、利回り を算出するのが一般的です。
NEDOによる発電所データベースは、日本国内837地点の発電量データベースを持ち
太陽光発電投資 における日射量の予測の精度も高くなっています。
参考:NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術開発機構「日射量データベース」
自然災害などによる故障
太陽光発電所へのリスクとして考えておかなければならないのが
「自然災害などによる故障」です。
「火災」「地震」「落雷」「風災」「雹災/雪災」「水災」などの自然災害だけでなく
「鳥などによる落石」や「盗難」なども
リスクとして考えておく必要があります。

故障などに備えるためには
こうした故障などのリスクに備えるためには
2. いざという時のために保険に加入しておく
などの対策をしておくことが望ましいです。
1. 定期的なメンテナンスで異常を早めにキャッチする
メンテナンスを定期的に行うことで、自然災害や動物の侵入などによって起こる
「故障の予兆」などを早めにキャッチし、大きな故障になる前に対処することができます。
▼「メンテナンス」について詳しくはこちらの記事をご参照ください
2. いざという時のために保険に加入しておく
さらに、実際に故障してしまった場合に備えて保険に加入しておくことも有効な対策です。
上記に挙げたような、自然災害などによる「発電所への被害」に対する保険だけでなく
台風などで飛散したパネルが人に当たるなどの「第三者への被害」に対する保険や
故障による発電所の発電量低下に対する「収入低下」に対する保険なども検討しておくと良いでしょう。
▼「太陽光発電の保険」について詳しくはこちらの記事をご参照ください
廃棄の問題
さらに考えておかなければいけないのが、FIT(固定価格買取制度)終了後の
パネルなどの処理に関する問題です。
主な選択肢は上記になるかと思いますが、
経年劣化などでソーラーパネルの発電能力が低下している場合、
廃棄などの選択肢を考えておく必要があります。
太陽光パネルの廃棄に関する法律
太陽光パネルには、有害物質である鉛、カドミウム、セレンなどが含まれています。
産業廃棄物として適切に廃棄しなければ法律違反となり、懲役刑や罰金が科せられることもあります。
廃棄費用の積立
そのため、太陽光パネルの廃棄の際には専門の業者に依頼する必要があります。
廃棄費用の積立を予めしておくと良いでしょう。
出力抑制
次に 太陽光発電投資 のリスクとして頭に置いておきたいのが、
「出力抑制」です。
出力抑制とは?
出力抑制 とは、電力消費量を供給量が上回った際に
各発電所の発電量を抑える措置のことを言います。
太陽光発電が 出力抑制 の対象になる可能性はそれほど高くありませんが、
九州の離島地域を中心に、実際に太陽光発電への 出力抑制 が行われています。
出力抑制 の対象となり、発電量が制限されてしまうと
その分の売電収入は少なくなってしまいますので、注意が必要です。
FITの売電単価の推移
さまざまなデメリットやリスクがあるものの、
FIT(固定価格買取制度)によって、高利回りで安定性のある投資として
太陽光発電投資 は魅力的な投資であると言えます。
しかしながら、この FIT(固定価格買取制度)の売電単価は年々下がっており
条件も付いて厳しくなって来ています。
1.売電単価が年々低下
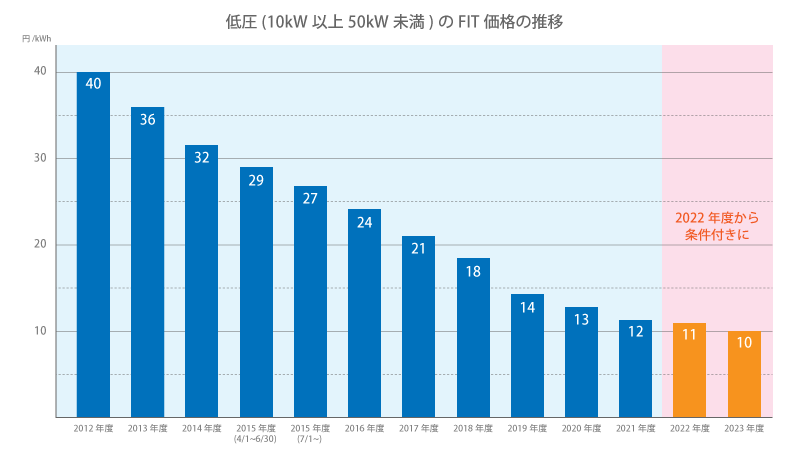
上のグラフは、FIT(固定価格買取制度)開始からの「低圧(10kW以上50kW未満)」の売電単価の推移です。
FIT(固定価格買取制度)による 太陽光発電投資 は、
発電所の初期導入費用の価格や工事期間から、高圧(50kW以上2000kW未満)よりも
低圧(10kW以上50kW未満)の方が人気があります。
その低圧の売電単価も
開始当初は40円/kWhから、2023年には1/4の10円/kWhまで下がっています。
売電単価に関するよくある誤解
売電単価に関するよくある誤解として、
例えば、2012年に40円/kWhの売電単価で太陽光発電所を購入した場合でも、
毎年下がる売電単価と同じ価格に毎年下がって行くと勘違いされる方もいらっしゃいます。
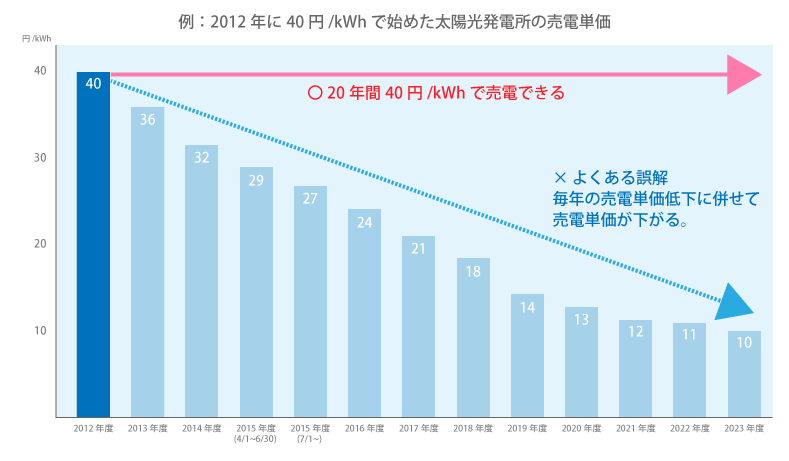
しかし2012年に40円/kWhの売電単価で太陽光発電所を購入して売電収入を得はじめた場合
上図のように、20年間は40円/kWhの単価で売電することができます。
2013年度に開始した方は36円/kWhで20年間、
2014年度に開始した方は32円/kWhで20年間、固定の売電単価で 太陽光発電投資 を行うことができます。
2.低圧の全量買取ができなくなった
2021年度までは、低圧の投資用の太陽光発電所で発電した電気を
すべて売電できる「全量買取」が可能でしたが
2022年度からは、さまざまな条件が付き「全量買取 ができなくなりました」
2022年度からの低圧FITの条件
2022年度から低圧の FIT に新たについた条件は下記の内容です。
売電単価の低下もさることながら、全量買取 ができなくなったことで
「低圧のFITを活用した売電は難しくなった」と言われるようになりました。
2023年現在でも可能な太陽光発電投資
このように、太陽光発電投資 で特に人気だった、
「低圧の FIT」を活用した 太陽光発電投資 は難しくなってしまいました。
しかし2023年現在でも、下記のような方法で 太陽光発電投資 を行うことができます。
順番に特徴を解説して行きます。
1. 高圧発電所での太陽光発電投資
高圧の発電所でも、太陽光発電投資 を行うことができます。
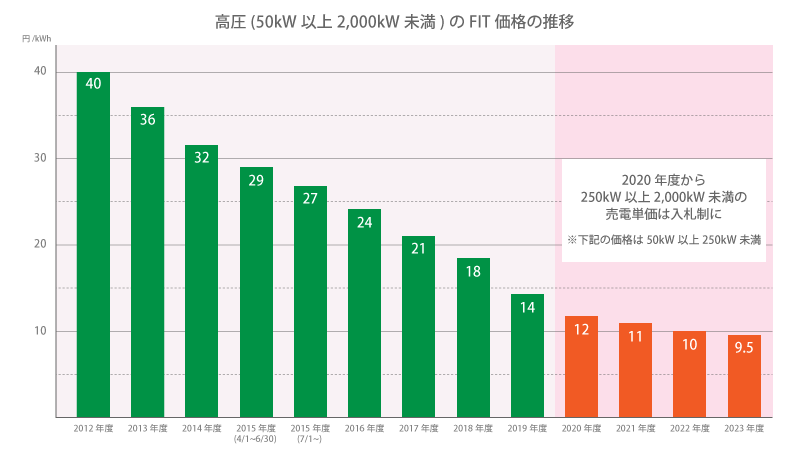
図のように、高圧における売電単価も、低圧以上に値下がりしています。
しかしながら、高圧においては自家消費率などの条件は無く
全量買取 での 太陽光発電投資 を行うことができます。
導入費用が高額
しかしながら、高圧の発電所は低圧の発電所と比較して規模が大きくなるため
「導入費用が高額」になり、億単位の投資が必要になってしまいます。
低圧と比較すると、導入のハードルは高くなってしまうのが、大きなデメリットです。
2. 中古の太陽光発電所を購入する
中古の太陽光発電所を購入して 太陽光発電投資 を行うこともできます。
FIT(固定価格買取制度)での 太陽光発電投資 を行う企業の中には、
節税目的で導入して、投資費用を回収したら売却する企業も多いため
中古の投資用太陽光発電所が市場にも出てきます。
中古の太陽光発電所のメリット
中古の太陽光発電所を購入する場合、下記のようなメリットがあります。
2. 売電実績が明確
1. FITの売電単価が高い
中古の太陽光発電所で、FIT 売電を行っていた場合には
売電を始めた時期によっては、売電単価が高いことがあります。
例えば、2023年から新規に FIT で低圧の 太陽光発電投資 を始める場合には、
売電単価は「10円/kWh」ですが、
2012年から FIT で低圧の 太陽光発電投資 を始めた中古物件を購入すれば
売電単価は「40円/kWh」になるのです。
2. 売電実績が明確
中古の太陽光発電所の場合、すでに太陽光投資を行っている実績がありますので
具体的な売電収入の見通しが立てやすい点もメリットの一つです。
中古の太陽光発電所の注意点
ただし、中古の太陽光発電所を購入する場合、下記のような点に注意が必要です。
2. 近隣トラブルなどの問題点は無いか
1. FITの残り期間
中古の発電所を購入した場合、FIT の残り期間が少ないこともあります。
例えば、2012年から FIT で売電を始めた発電所の場合、
確かに売電単価は高いのですが、2023年に中古で購入すると、残り年数は「9年」になります。
売電収入を得られる期間も短くなりますので、
収益がどれだけ得られるのかをしっかり確認しておく必要があります。
2. 近隣トラブルなどの問題点は無いか
たとえ売電実績は良かったとしても、
近隣トラブルなどの書類上には見えにくい問題がある場合もあります。
そうした問題が無いか、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
3. FIP制度
FIT(固定価格買取制度)に代わる 太陽光発電投資 として、
2022年4月から始まったのが「FIP制度」です。
「FIP制度」とは?
FIP制度 とは「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略称で、再エネの導入が進む欧州などでは、すでに取り入れられている制度です。
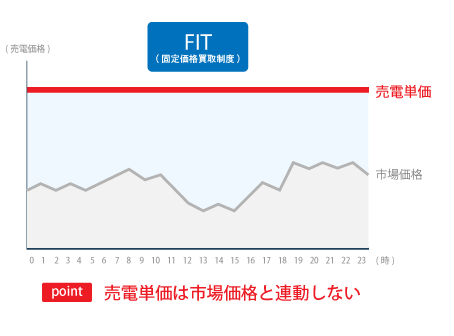
FIT(固定価格買取制度)の場合、
図のように、
売電単価は電力の市場価格の変動に影響を受けず、
固定の価格になります。
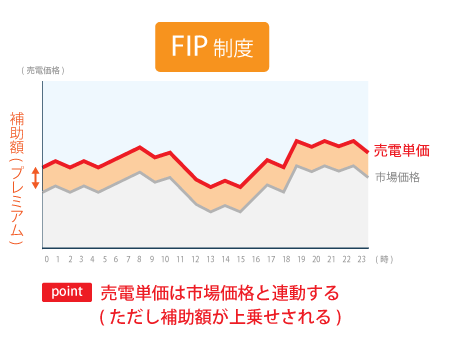
しかし FIP の場合には、市場価格と連動して価格が上下します。
但し、補助額が上乗せされるので、市場価格より高値で売電することができます。
「FIP制度」が誕生した背景
FIT(固定価格買取制度)は、再エネを普及するために始まった制度ですが、
最終的には再エネも市場価格に合わせて変動し「電力として自立」させる必要があります。
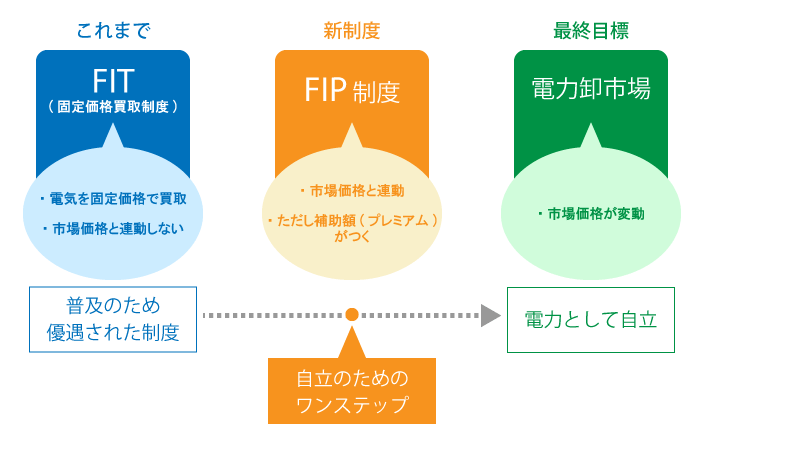
そのためのステップとして、FIT に続く売電の制度として、FIP制度 が始まりました。
「FIP制度」の現状
しかしながら、2022年に開始した「FIP制度」は、まだまだ参入企業も少なく
普及しているとは言いにくいのが現状です。
FIP制度 を活用して 太陽光発電投資 を行う場合、計画通りに発電しなければペナルティ料金が発生することになります。
そうした難易度の高さからも、現状はまだ FIP制度 での 太陽光発電投資 は少ないのが現状です。
「FIP制度」について詳しくはこちら
「FIP制度」については、詳しくは下記の記事で解説していますので
興味のある方はご参照ください。
4. 太陽光ファンド
高圧の 太陽光発電投資 ほど高額な導入費用をかけずに行える 太陽光発電投資 として
「太陽光ファンド」という方法もあります。
「太陽光ファンド」とは?
太陽光ファンド は、通常の 太陽光発電投資 とは異なり、
複数の出資者から資金を集め、太陽光発電投資 を行います。
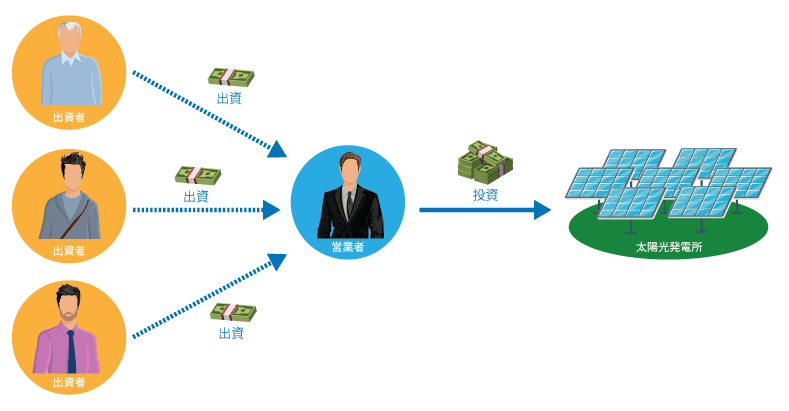
そして売電で得られた利益を、出資者に配当します。
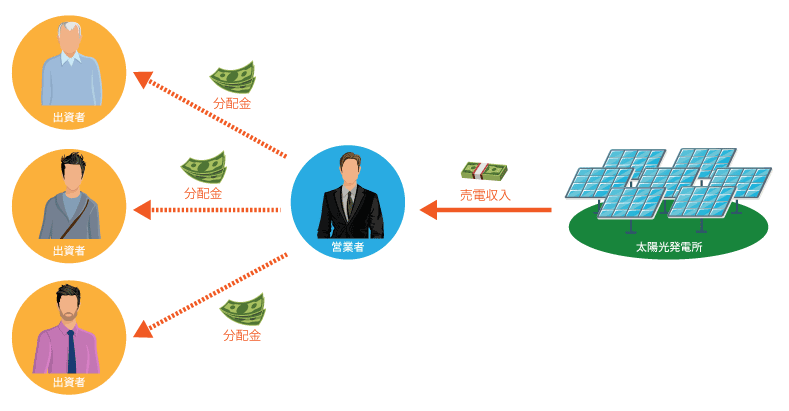
「太陽光ファンド」のメリット
この 太陽光ファンド には、さまざまなメリットがあります。
1. 導入費用を抑えられる
一つ目のメリットは「導入費用を抑えられる」点です。
前述のように、高圧以上の 太陽光発電投資 を行う場合、導入費用が高額になってしまいます。
太陽光ファンド の場合、複数の出資者で出資金を募って投資するため
初期投資の費用を抑えられます。
2. 利回りが高い
太陽光ファンド の種類にもよりますが、
一般的な 太陽光発電投資 と比較して「利回りが高い」傾向があります。
太陽光ファンド によっては、出資者だけでなく、金融機関からも出資を受けており
その場合、金融機関には、返済のみで高利回りの配当が必要無いため
その分、出資者の配当が高くなるためです。
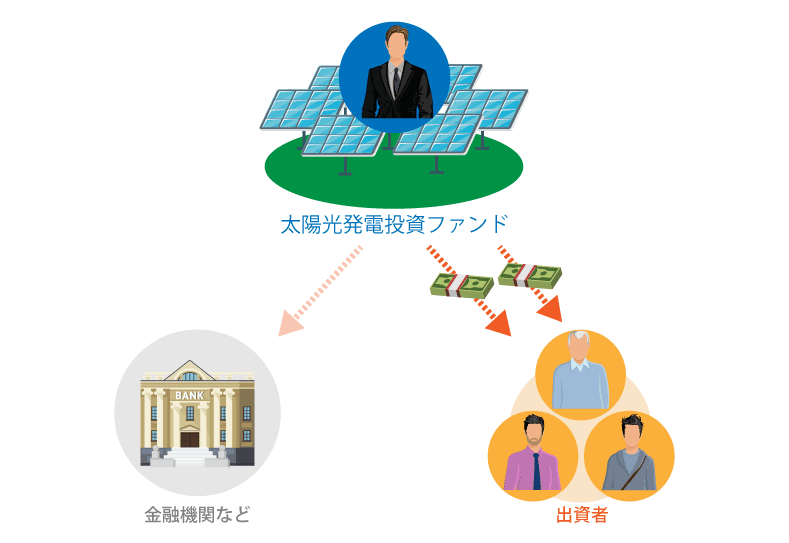
3. ローリスク
太陽光ファンド では、出資者と営業者が「匿名組合出資契約」を結びます。
「匿名組合出資契約」では、従来の 太陽光発電投資 では負わなければならなかったリスクを負う必要は無く、従来の 太陽光発電投資 よりもローリスクである点も特徴のひとつです。
「太陽光ファンド」について詳しくはこちら
「太陽光ファンド」について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
▼より詳しくはこちらの記事をご参照ください
まとめ
いかがでしたでしょうか?
太陽光発電投資 について、基本的なしくみやメリット・デメリットやリスク
FIT(固定価格買取制度)や売電価格の推移など
ご紹介して参りました。
低圧の FIT を活用した「太陽光発電投資」は、
2023年現在はなかなか実施は困難になっていますが
高圧の発電所での 太陽光発電投資 や、中古の発電所、
FIP制度 や 太陽光ファンド のような、
他にも 太陽光発電投資 の方法が残っています。
是非ご自身に合う方法を、検討してみてください。
本記事がみなさまのお役に立てることを祈っています。