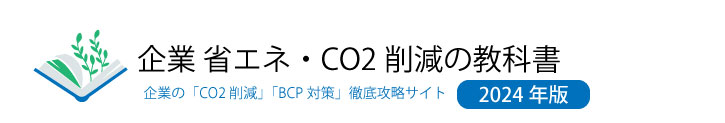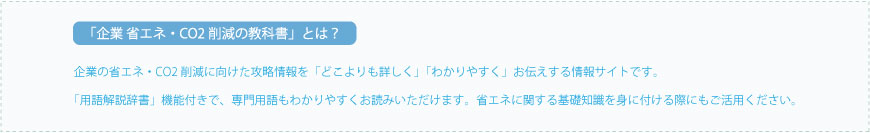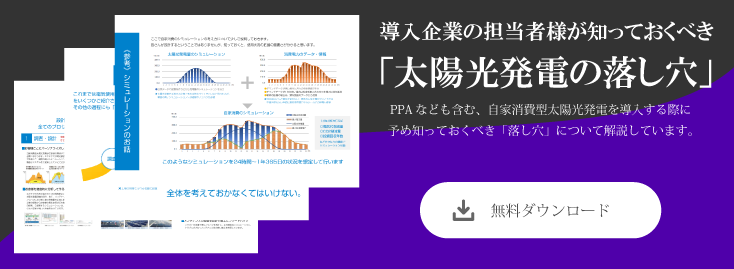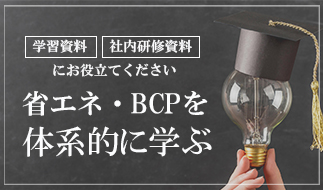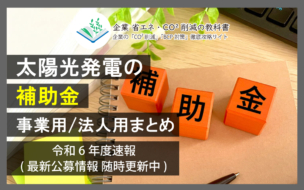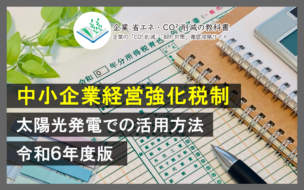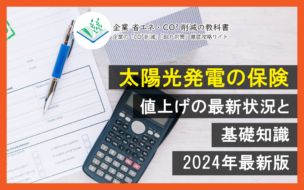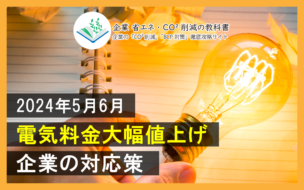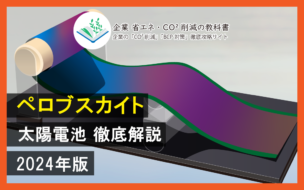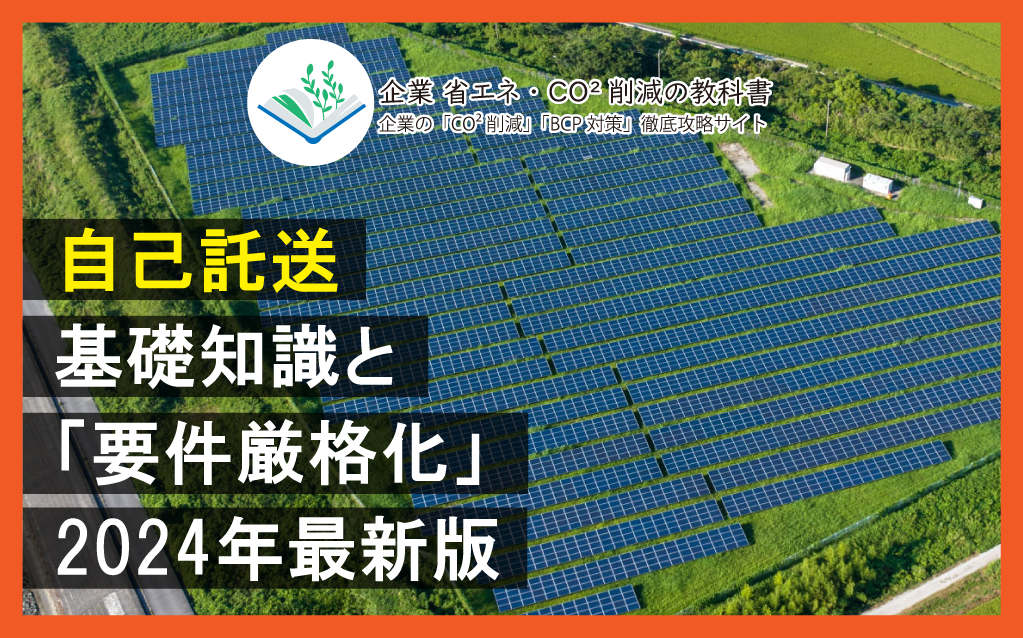
※2024年02月02日 最新情報に更新しました。
「大規模な再エネを導入する手段」として注目されてきた「自己託送」ですが、
2023年12月26日に「要件厳格化」と「当面の間の受付停止」が、資源エネルギー庁から発表されています。
この記事では、この「要件厳格化と受付停止」の内容を中心に
「自己託送の基礎知識」もあわせて解説して行きます。
本記事をお読みいただければ、
「自己託送 の基礎知識から要件厳格化の現状」まで、
幅広く理解していただけるようになるかと思います。
ぜひ御社の「自己託送 のご検討材料」としてお役立てください。
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
自己託送とは?
まず要件厳格化などのお話の前に、自己託送 とはどのようなものなのか、簡単に解説します。
自己託送とは?
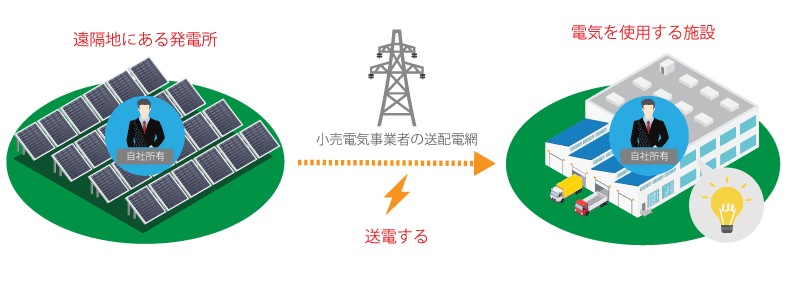
「自己託送」とは、上図のように
自家消費型太陽光発電のモデルになります。
※発電所の持ち主は、電気を使用する者(需要家 と言います)と原則的に同一である必要があります。
なぜこのようなモデルに?
太陽光発電システムは、より広い土地を用意出来れば、
ソーラーパネルの数を増やすことができ、発電量を増やすことができます。
従来の 自家消費型太陽光発電 は、屋根などの電気を使用する施設内に太陽光発電システムを導入していたため、敷地内の広さに限りがあれば、発電量にも限りがありました。
しかし、自己託送 のように電気を使用する敷地外に太陽光発電システムを導入する手法であれば、
大きな土地を選び、広さを限定せずに太陽光発電システムを導入できるため、
「規模の大きな太陽光発電所」を導入することが可能になります。
そうしたメリットから、自己託送 が注目されるようになりました。
自己託送を行う条件
ただし、自己託送を行うには、さまざまな条件が必要となります。
中でも、発電所の持ち主と電気を使用する「需要家」の関係が重要になってきます。
自己託送 は、あくまでも「遠隔地に置いた『需要家 所有の』発電所」からの送電になります。
そのため、
が、自己託送 を行う条件になります。
「密接な関係」とは、グループ会社など、親会社と子会社のような関係性などを言います。(細かくさまざまな条件が定められています)
実質的に「同じ会社」に近いような関係性にある場合には、自己託送 の要件を満たすことができます。
また後述しますが、2021年11月の法改正による規制緩和で、他者同士でも組合をつくることで「密接な関係にある」として 自己託送 が可能になりました。
再エネ賦課金がかからない
この 自己託送 は「再エネ賦課金 がかからない」点も大きな特徴であり、
後述する「要件厳格化」にも大きく影響してきます。
再エネ普及のために、太陽光発電などで創った電気を「優遇された価格」で買い取る
FIT(固定価格買取制度)が実施されてきました。
この「優遇された価格」と「一般的な電気料金」の差額は、「再エネ賦課金」として電気利用者が電気料金に加えて支払うしくみになっています。
再エネ賦課金の推移
(2012年度のみ8月分~4月分の期間になります)
出典:新電力ネット「再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移」を元に作成
再エネ賦課金 は、上記のような単価で推移しています。
年々高騰し、2022年度には1kWあたり3.45円になっていました。
単価でみると大きな数字に見えませんが、
例えば、年間300万kWの電気を使用する生産工場で換算すると「年間1,035万円」と
非常に大きな金額になることが分かります。
2023年度は、電気料金の値上りを要因として、1.4円/kWhまで値下りしていますが、
電気料金の高騰も少し落ち着いてきましたので、2024年度は2円台まで値上がりするのではと言われています。
自己託送は再エネ賦課金がかからない
他社などから電気を購入する場合には、本来「再エネ賦課金」を支払う必要があります。
しかし、自己託送 の場合には、あくまで「自分で作った電気を使っているだけ」になりますので
「再エネ賦課金」はかかりません。
「要件厳格化」と「新規受付停止」
このように、再エネ普及の一環として注目されてきた 自己託送 ですが、
資源エネルギー庁が2023年12月26日に開催した電力・ガス基本政策小委員会において
「要件厳格化」と「新規受付停止」を行うことを決定しました。
詳細:資源エネルギー庁「再エネ導入の拡大に向けた今後の自己託送制度の在り方について(2023年12月26日)」
「厳格化」に至った背景
特に「再エネ賦課金 の免除」を目的として、本来の 自己託送 の目的にそぐわない
導入方法が行われる例が増加したため、要件を厳格化することになりました。
「新規受付停止」
この決定を受けて、
自己託送 は「2024年1月1日から当面の間、新規受付停止」されることになりました。
これは、後述する「要件厳格化」の内容が定まるまでの間、
新規申請などを行うと混乱が生じるための措置になります。
新たに 自己託送 を行うことはできなくなっています。
※また最新情報が分かり次第、本記事を更新してお知らせいたします。
「要件厳格化」
「要件厳格化」とは、つまり「自己託送 を行う条件を厳しくする」ということです。
資源エネルギー庁が示した「要件厳格化」の案が、以下の4つです。
自己託送 の対象外にする。
自己託送 の対象とする。
「密接な関係」であることを要件に入れる。
※ただし、特に案2と案3については、
厳しすぎる制限になりかねない為、まだ議論の余地があるとされています。
それぞれ詳しく解説して行きます。
案1.他者が開発した発電所を借りて、名義上の管理責任者として行う自己託送は、自己託送の対象外にする。
発電所の持ち主は名義上だけで、実質的には他者が開発している発電所で行う 自己託送 は、
対象外にするという、厳格化案です。
問題提起されている自己託送の例
このような厳格化案が出されているのは、下記のような 自己託送 の事例が出ているためです。
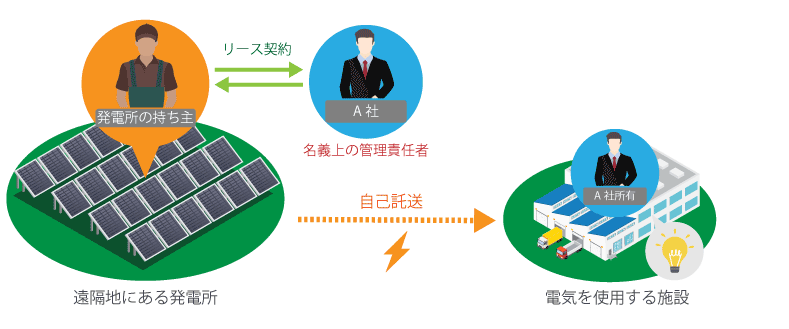
資源エネルギー庁「再エネ導入の拡大に向けた今後の自己託送制度の在り方について(2023年12月26日)」を元に作成
前述のように、自己託送 は本来、発電所の所有者と電気を使用する施設の所有者が同一である必要があります。
上図のような例の場合「電気を使用する所有者」が「名義上の管理責任者」にはなっているものの
実質的には、リースなどを通じて「別の第三者」が発電所の持ち主になっています。
これでは「自社同士で電気を送電する」という 自己託送 の本来のあり方ではないのではないか
という問題提起がされて、厳格化すべきではないかということになっているのです。
なぜこのようなケースが出ているのか
第三者が所有する発電所から電気を購入する形にすればよいところを
なぜわざわざ「名義上の管理者」になってまで、自社同士でのやり取りのようにする必要があるのでしょうか?
それは「再エネ賦課金 が免除される」ことが大きな理由です。
オフサイトPPAモデル
本来、他者の所有する発電所から送電を受ける場合には
下図のように「オフサイトPPA」という 自家消費型太陽光発電 のモデルで行うことになります。
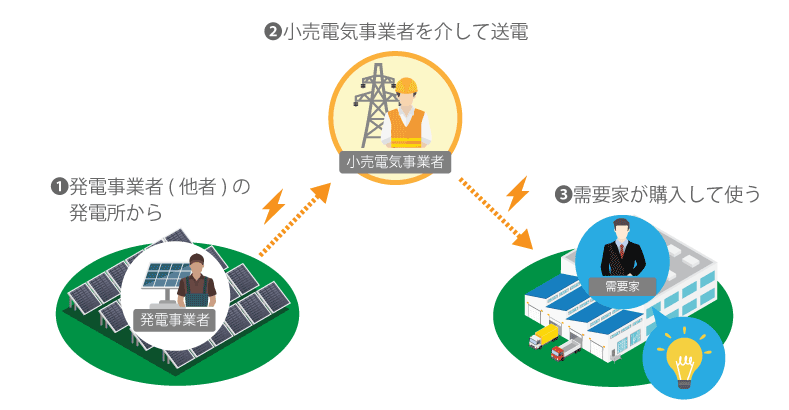
しかし、他者が発電した電気を直接購入する際には「再エネ賦課金」を負担する必要があります。
そこで、他者の発電所でありながら、
リース契約などで「需要家 が名義上の管理責任者」になることで 自己託送 にして
再エネ賦課金 を支払わなくて良い形にするといった手法が用いられることもあったのですが
こうした導入方法は「本来の 自己託送 の目的とは違うのではないか」ということで
要件厳格化の案として、上がる事になったのです。
再エネ賦課金負担の公平性
再エネ賦課金 をこのようなかたちで免れる方法が一般化してしまうと、
国民負担の公平性が損なわれ、その分他の電気使用者の負担が増えてしまうのではないかという懸念もあるのです。
案2.発電所の維持や運用を他者に業務委託している場合、自己託送の対象外にする。
続いて2つ目の案は「発電所の維持や運用を他者に業務委託している場合」です。
分かりやすくいうと、下記のような例になります。
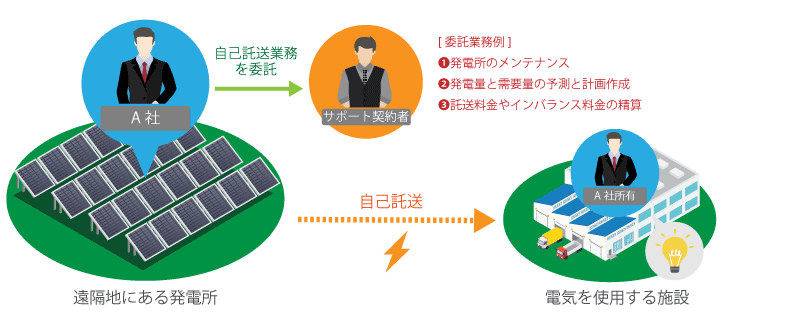
資源エネルギー庁「再エネ導入の拡大に向けた今後の自己託送制度の在り方について(2023年12月26日)」を元に作成
太陽光発電所の運用業務の一部を、外部に委託するケースです。
運用における主な業務委託例
自己託送 を行う際に「運用における主な業務委託」の例をいくつか解説します。
2.発電量と需要量の予測と計画作成
3.託送料金やインバランス料金の精算
1.発電所のメンテナンス
太陽光発電所には、定期的なメンテナンスが義務付けられています。
ただ、太陽光発電所は「発電所」ですので、電気工事の知識や資格のある者が行う必要があります。
2.発電量と需要量の予測と計画作成
自己託送 を行う際に困難なのが「発電量と需要量」を予測し、計画書を提出する必要がある点です。
自己託送 を行う際には、小売電気事業者 の送配電網を使用して電気を送電します。
しかしながら、電気の「発電量」と「使用する量(需要量)」を一致させなければ
電気の「需給バランス」が崩れ、最悪の場合には大規模な停電になってしまうケースもあります。
そのため、小売電気事業者 の送配電網を使用する際には
「予め、発電量と需要量を予測して、小売電気事業者 に報告しておく」必要があるのです。
そうした、発電量と需要量の予測にも、専門的な知識が必要で
現状は、多くの企業においては、専門の業者に委託するのが一般的です。
3.託送料金やインバランス料金の精算
続いて、よく外部委託されるケースになるのが「託送料金やインバランス料金の精算」です。
「託送料金」とは、小売電気事業者 の送配電網を使用する利用料のことです。
「インバランス料金」とは、前述した「発電量と需要量」の予測に対して
予測通りにならなかった際に、支払う必要がある「ペナルティ料金」のようなものです。
厳格化するかどうかは精査が必要
ただし「メンテナンス」や「発電量・需要量の予測」などについては、専門性が非常に高く
それらをすべて 需要家 が行うとするのは「過大な要求」ではないかいう意見もあり、
どのような業務の外部委託を制限するかは、まだ精査が必要です。
案3.余剰電力分を送電する場合にのみ、自己託送の対象とする。
続いては「余剰電力のみを自己託送の対象にする」という案です。
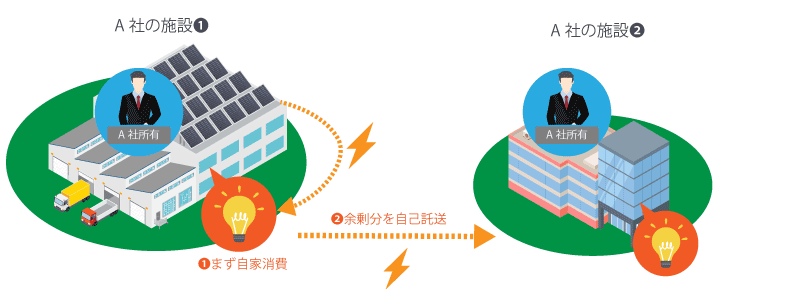
図のように、あくまで発電所のある施設で、発電した電気を自家消費し、
「余剰分」だけを同じ企業の別の施設に送電する場合のみ「自己託送 として認める」という案です。
自己託送のなりたち
自己託送 は、太陽光発電の遠隔地からの送電で活用するためのしくみと思われがちですが、
そもそもの成り立ちは、2012年に既設の火力発電で余った電気を他の需要地で使用するために開始された制度です。
そのため、原則的に「余剰電力」が前提となっている制度ではあります。
しかし、現状は全量送電されている
しかしながら、太陽光発電における自己託送においては、
現状は発電所のある場所では自家消費されず、大半が「全量送電」されているのが現状です。
まだまだ議論が必要な案
このように、現状では再エネの普及から、全量送電されるケースも多いため
一概に「余剰送電のみ」に限定することが適切かどうかは、まだ議論が必要です。
案4.電気を使用する施設内で他者に電気を共有する場合には「密接な関係」であることを要件に入れる。
続いての厳格化案は「電気を受けた後」に「他者に電気を融通する」場合に対する厳格化案です。
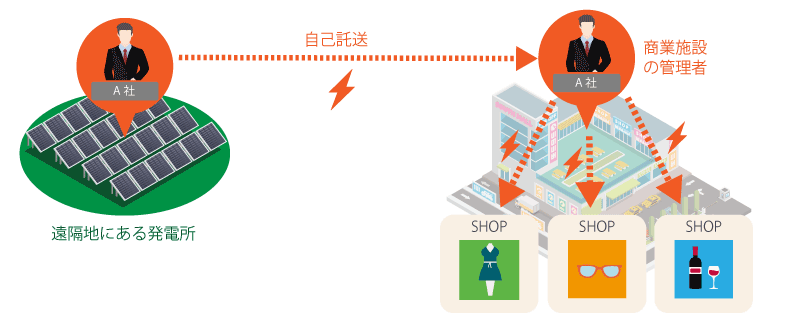
資源エネルギー庁「再エネ導入の拡大に向けた今後の自己託送制度の在り方について(2023年12月26日)」を元に作成
例えば、上図のように、自己託送 で電気を受けた 商業施設の管理者が、
テナントの店舗に電気を融通するなどのケースなどが該当します。
この場合、発電所を所有しているA社が、テナントに入っている店舗に
「電気を売っている」という形になってしまうので「自分で作った電気を使う」という
自己託送 の原則からはずれているのではないかということです。
テナントとも「密接な関係」を結ぶ必要があるのではないか
このようなケースの場合にも、テナントとの「密接な関係」を結ぶべきではないか
ということになってきているのです。
要件厳格化の時期は?
それでは、解説してきた4つの案は、実際に厳格化の対象になるのでしょうか?
また、その時期はいつごろになるのでしょうか?
わかりやすく表にまとめます。
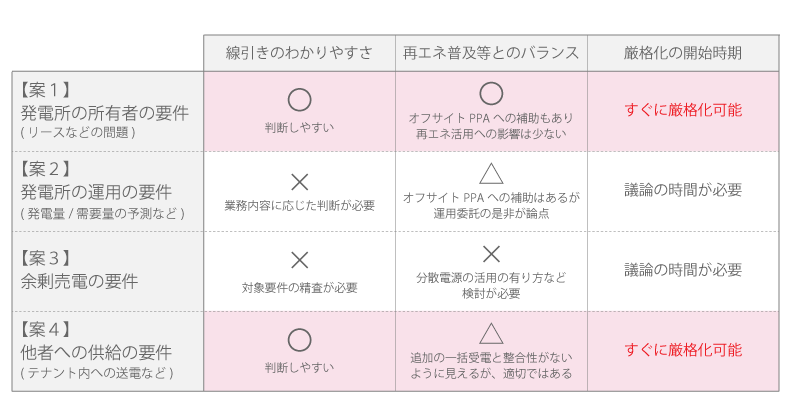
資源エネルギー庁「再エネ導入の拡大に向けた今後の自己託送制度の在り方について(2023年12月26日)」を元に作成
それぞれの案について、厳格化すべきかどうか考える上では
どこからどこまでを厳格化の対象にするのかという「線引きのわかりやすさ」と
再エネ普及などへの影響が出ないかどうかという「再エネ普及等とのバランス」から考えて行く必要があります。
案2,案3はまだ議論が必要
案3:余剰売電に限定するかどうか
案2,案3に関しては、どこまでを要件の範囲にするのか、また再エネ普及への影響なども考える必要があるため、まだ議論が必要であり、すぐに厳格化するのは難しいと考えられています。
案1,案4は早い段階で厳格化される可能性も
案4:他者への供給の要件(テナント内への送電など)
案2,案3に関しては、要件の線引きもしやすく、厳格化しても再エネ普及への影響も少ないと考えられているため、比較的早い段階に厳格化されるのではと考えられています。
厳格化の時期は?
厳格化の時期は、現在(2024年2月2日時点)まだ分かっていません。
ただ、先に案1と案4が厳格化されることになりそうですので、自己託送 を検討されている方は
案1や案4の内容が影響しないかどうか確認しておくと良いかと思います。
また、新しい情報などが分かりましたら、本記事を更新してお知らせしていきます。
気になる方はぜひブックマークをよろしくお願いいたします。
自己託送のメリット
まず初めに、要件厳格化の内容を中心に解説してきました。
続いて、自己託送 の基本的な特徴を「6つのメリット」から見て行きましょう。
要件が厳格化されるとはいえ、自己託送 にはさまざまなメリットがあります。
2. CO2排出量を「大きく」削減できる
3. 敷地内に太陽光発電を設置できない企業も導入できる
4. グループ全体に再エネを導入できる
5. 余剰電力を効率よく活用できる
6. 再エネ賦課金 がかからない
メリット1. 電気料金を「大きく」削減できる
自己託送 は、大規模な発電量となるため削減できる電気料金も大きくなります。
近年の「電気料金高騰」は、企業が抱える頭の痛い問題です。
自己託送で発電した電気を使用することで、電気料金を大幅に削減することができます。
また、あらゆる 自家消費型太陽光発電 のモデルの中でも、
自己託送 が最も電気料金削減効果が大きくなります。
電気料金高騰について詳しくはこちら
メリット2. CO2排出量を「大きく」削減できる
規模の大きな太陽光発電所を導入すれば、
電気料金だけでなくCO2の削減量も大きくなります。
施設の電気使用量や発電所の規模によっては、「CO2排出をゼロにする」ことも可能です。
メリット3. 敷地内に太陽光発電を設置できない企業も導入できる
・屋根の形状の問題で、ソーラーパネルを設置できない。
・施設が塩害地域にある。
上記のように、従来の 自家消費型太陽光発電 では充分な設置が難しい施設でも、
自己託送 で敷地外から送電することで再エネを導入することができます。
メリット4. グループ全体に再エネを導入できる
自己託送 で発電した電気は、複数個所に送電して使用することも可能です。
同じグループ内や、前述した「密接な関係」にある企業にも再エネを導入することで
グループ全体やサプライチェーン内にも再エネを導入することができます。
メリット5. 余剰電力を効率よく活用できる
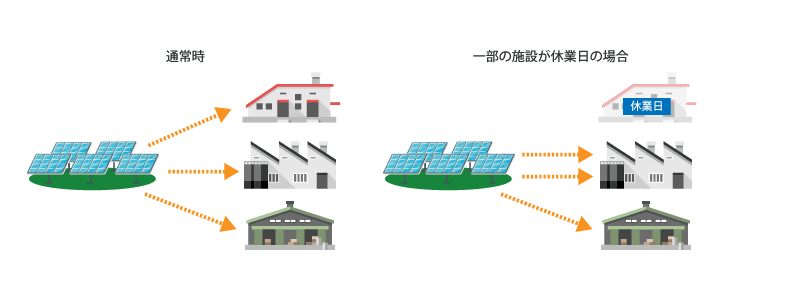
従来の オンサイト の 自家消費型太陽光発電 の場合には、
定休日に発電した電気を活用することは困難でした。
自己託送 であれば、定休日の施設に送る電気を、定休日ではない別の施設に送るなどして
余剰電力を効率よく活用することができます。
メリット6. 再エネ賦課金がかからない
冒頭でも解説した通り、再エネ賦課金 がかからないこともメリットのひとつです。
自己託送のデメリット
続いて、自己託送 のデメリットついても解説していきます。
2. 計画値の提出が必要
3. ペナルティを課せられる可能性がある
4. 非常用電源には活用できない
5. 託送料金がかかる
デメリット1. 導入費用が高い
まず、最も大きなデメリットが「導入費用が高い」点です。
発電所の規模が大きくなるケースが多い
自己託送 は低圧の発電所でも可能ですが、メリットにも挙げたように
「大幅な電気料金とCO2削減」を目的として導入する場合、
発電所の規模も大きくなり、導入費用も大きくなってしまいます。
また所有している遊休地などが無い場合には、新たに土地を購入する費用もかかります。
メンテナンス費用も高めになる傾向
自己託送 の場合、発電所のメンテナンス費用も、自社で負担する必要があります。
発電所の規模が大きいと、メンテナンス費用も割高になる傾向があります。
デメリット2. 計画値の提出が必要
冒頭でも触れましたが、自己託送 を行う際には「計画値同時同量制度」に従って
使う電気の量(需要量)と発電量(供給量)を30分単位で予測し、報告することが義務付けられています。
そうした報告を行う手間が生じる点も、自己託送 のデメリットのひとつです。
デメリット3. ペナルティを課せられる可能性がある
「計画値同時同量制度」に従って報告した計画に対して
計画通りにならなかった場合、その差分を「インバランス料金」というペナルティ料金を
支払う必要があります。
「計画値同時同量制度」「インバランス料金」について詳しくはこちら
「計画値同時同量制度」と「インバランス料金」について、
詳しくは下記記事で解説していますので、ご参照ください。
デメリット4. 非常用電源には活用できない
従来の 自家消費型太陽光発電 は、災害時の非常用電源としての活用も
目的として導入されるケースも多くありましたが、
自己託送 は、非常用電源としての活用には期待できない点がデメリットのひとつです。
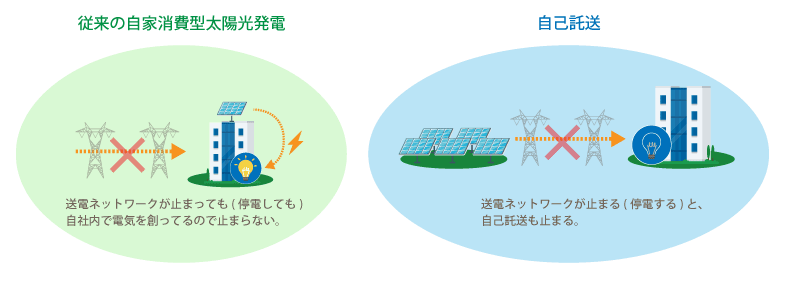
図のように、敷地内に設置した 自家消費型太陽光発電 は、送電ネットワークが災害などで止まっても、敷地内で発電/送電しているので、非常用電源として活用できます。
しかしながら、自己託送 の場合には、送電ネットワークが災害などで止まった際には、太陽光発電所からの送電も止まってしまいます。
このため、自己託送 は非常用電源としての活用には期待できないのです。
デメリット5. 託送料金がかかる
自己託送 は、さまざまな 自家消費型太陽光発電 のモデルの中でも
電気料金の削減効果が最も大きいのですが、
一般送配電事業者 の配送電網を使用して送電するため、
利用料として「託送料金」を支払う必要があります。
託送料金の料金相場
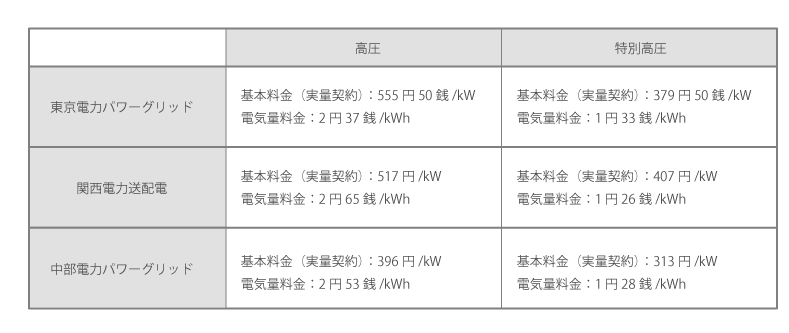
※2024年2月02日時点の託送料金を下記から参照しています。
東京電力パワーグリッド「主要な料金」
関西電力送配電「送電サービス料金等」
中部電力パワーグリッド「託送料金単価表(2024年4月1日実施)」
自己託送を行うための条件
続いて、自己託送 を行うための条件に付いて解説して行きます。
冒頭でも少し触れましたが、より詳しく見て行きましょう。
自己託送 を導入するためには、下記のような条件をクリアする必要があります。
2.発電所の所有者と電気を使用する者が「同一」または「密接な関係」があること
3.電気を使用する施設の契約電力が「高圧」または「特別高圧」であること
4.発電所と電気を使用する施設が同一電力エリアにあること
5.特定供給 の許可が必要なケースがある
順番に解説していきます。
1.売電目的ではないこと
自己託送 の発電所で発電した電気は、売電することができません。
ですので、FIT や FIP などとも併用することもできません。
2.発電所の所有者と電気を使用する者が
「同一」または「密接な関係」があること
自己託送 を行う場合には、原則的には「発電所の所有者」と「電気を使用する施設の所有者」が同じである必要があります。
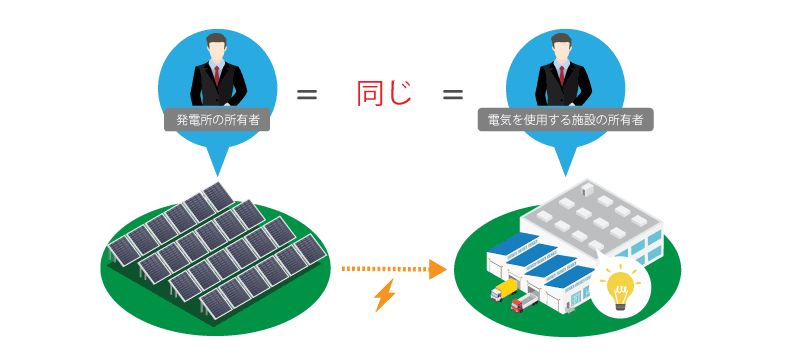
「密接な関係」
ただし、同じ企業ではなくても
両社が、グループ企業などの「密接な関係」にあると考えられる場合には、
自己託送 を行うことができます。
「密接な関係」の例
密接な関係として「自己託送に係る指針」で定められているのは、下記のようなものです。
A) 生産工程において代替が効かない関係
生産工程において原材料や製品のやり取りがある関係性で、
その原材料や製品が他の企業では代替えが効かない関係性の場合には、
密接な関係があるとみなされます。
B) 「親会社」「子会社」の関係
会社法上の「親会社」「子会社」の関係にある場合にも、密接な関係があるとみなされます。
C) 過半数の役員が派遣されている
一方の企業から、もう片方の企業に役員が派遣されており、その役員が役員全体の過半数を超えている場合にも、密接な関係があるとみなされます。
D) A,B,Cを合わせて見た時に「密接な関係がある」とみなされる場合
ここまででご紹介したA,B,Cの条件に単独では満たされていない場合でも
それぞれを合わせて見ることで「密接な関係がある」とみなされる場合には
密接な関係があると判断されます。
E) 長期的な関係
第三者への代替が困難な原材料、製品、役務等の提供が長期に行われている関係性にある場合にも、
密接な関係があると判断されます。
他社同士でも条件付きで自己託送が可能に
ただし、2021年11月の法改正によって、
上記の「密接な関係」にない他社同士でも組合を組むことで 自己託送 が可能になりました。
この法改正で可能になった 自己託送 を「自己託送(第三者所有モデル)」と呼びますが
本記事で解説すると長くなってしまいますので、省略します。
「自己託送(第三者所有モデル)」についての詳細は、下記記事を参照して頂ければ幸いです。
3.電気を使用する施設の契約電力が
「高圧」または「特別高圧」であること
自己託送 を行う場合、発電所側の契約電力は「低圧」「高圧」「特別高圧」いずれでも問題ありませんが、「電気を使用する施設側」の契約電力は「高圧」または「特別高圧」である必要があり、「低圧」では 自己託送 ができないので、注意が必要です。
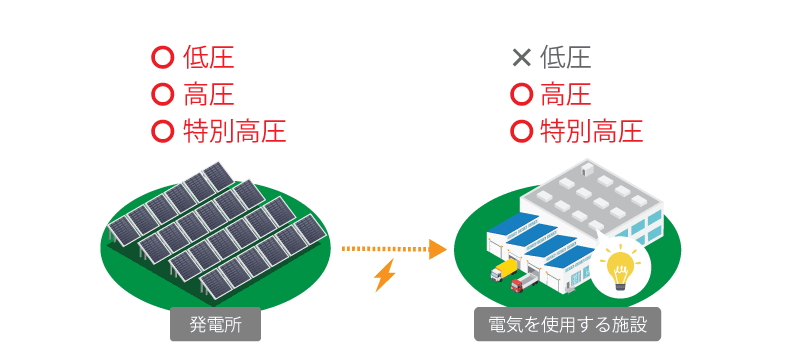
4.発電所と電気を使用する施設が
同一電力エリアにあること
自己託送 を行う際には「発電所」と「電気を使用する施設」が、
同一電力エリア内(同じ東京電力管内など)にある必要があります。
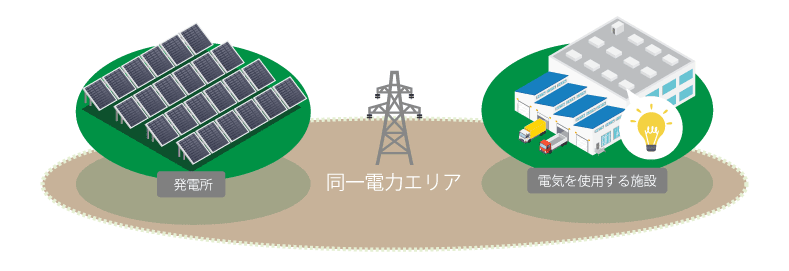
5.特定供給の許可が必要なケースがある
「密接な関係」にある企業を複数と絡めた 自己託送 を行う場合、
電気の送配電について、経済産業大臣から「特定供給 の許可」を得る必要があります。
「特定供給 の許可」については、少し複雑で説明が長くなってしまいますので
下記の別記事で、詳しく解説していきます。
よろしければご参照ください。
自己託送にかかる費用
「電気料金は大幅に削減できるけれど、託送料金はかかる」など、
自己託送 の電気料金には少し分かりにくい部分もありますので、解説して行きます。
月々の電気料金の内訳
自家消費型太陽光発電 のさまざまなモデルにおいて月々の電気料金の内訳を比較してみます。
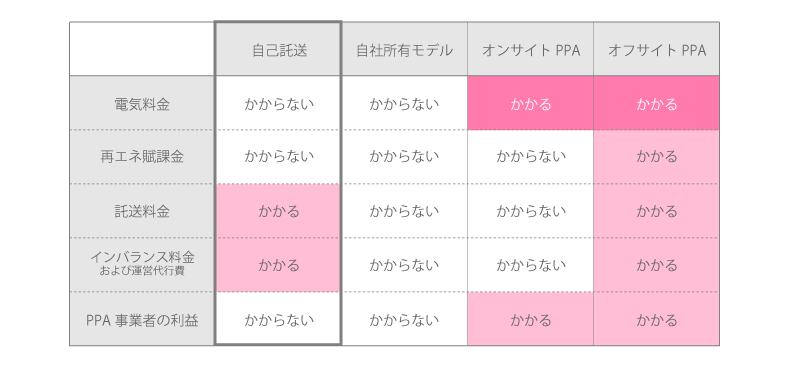
自家消費型太陽光発電には、自己託送 以外にも、自社所有モデル,オンサイトPPA,オフサイトPPA など、大きく分けて4つのモデルがあります。
これらの詳細解説はここでは省略しますが、各モデルの名称にカーソルを合わせて解説をご覧いただくか、下記サイトにて詳細をご確認ください。
企業省エネの教科書「自家消費型太陽光発電の「4つのモデル」」
このように比較すると、電気料金の単価は、自己託送 や 自社所有モデル の方が安い傾向があることが分かります。
単価でみると自社所有モデルの方が安いが・・・
電気料金の単価でみると、託送料金 や インバランス料金 がかかる分、
自己託送 の方が高くなりますが、
発電所の規模を大きくできるため、削減できる電気料金の総額は、自己託送 の方が大きくなります。
初期費用の内訳
続いて、導入費用などの費用についても見て行きましょう。
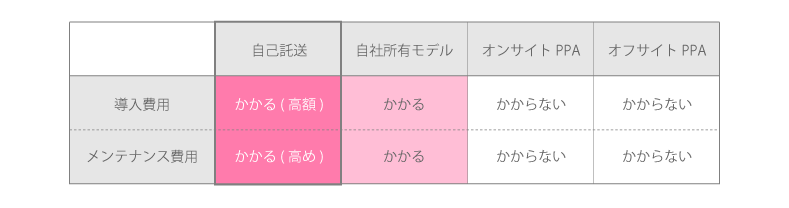
オンサイトPPA や オフサイトPPA などの PPAモデル については、初期費用などはかかりませんが
自社所有モデル と 自己託送 については、導入費用もメンテナンス費用もかかります。
また、規模が大きい分、自己託送 の初期費用は大きくなります。
自己託送 は、電気料金削減効果は全てのモデルの中で最も高くなりますが、
その反面、初期費用も大きくなることが分かります。
どんな企業に向いている?
それではこれまでご紹介した特徴から、自己託送 はどんな企業に向いているのか
確認して行きましょう。
1. CO2削減と電気料金削減を同時に目指す企業
これまで解説してきたように、自己託送 はCO2排出量と電気料金を大幅に削減することができます。
ただし、CO2排出量については、同様に オフサイトPPA でも大幅な削減が可能です。
オフサイトPPA はその反面、電気料金削減は限定的で、
電気料金が高騰している現状では少し安く抑えられますが、高騰前の価格基準と比較すると
割高になってしまいます。
こうした点から、CO2排出量だけなく電気料金も大きく削減したい企業は
オフサイトPPA よりも 自己託送 の方が適しています。
2. グループ全体に再エネを導入したい企業
自己託送 は、複数個所への送電が可能ですので、
同じ企業グループ全体に再エネを導入し、CO2排出量と電気料金を削減することができます。
3. 高額の先行投資ができる企業
前述のように、自己託送 には、多額の初期費用が必要になります。
そうした高額の先行投資が可能な企業である必要があります。
自己託送の事例
次に、実際に 自己託送 を導入した企業の事例も見てみましょう。
ソニーグループ「敷地外の牛舎からの自己託送」
ソニーグループは、敷地外の牛舎に設置した太陽光発電で発電した電力を事業所に託送する 自己託送 を行っています。
発電施設の建設を行った企業から、発電事業を譲渡されることで
「発電事業者と供給先の事業者とが同じ」とみなされ、自己託送 を実現しています。
詳細:サステナブル・ブランド ジャパン「ソニーグループ、注目の「自己託送制度」を利用した再エネ調達を強化」
東京建物「別拠点の余剰電力を自己託送」
東京建物では、自家消費型太陽光発電 を導入した3拠点から、自家消費の余剰電力を
別の拠点に 自己託送 する取組みを行っています。
自己託送 の計画報告や予測は、東京ガスの「ヘリオネットアドバンス」というシステムを用いて運用されています。
詳細:東京ガス「東京建物の物流施設で太陽光発電サービス「ソーラーアドバンス」を活用した自己託送を開始」
国内最大級となる自己託送発電所をエネテクが設計・調達・建設
本サイト「企業 省エネ・CO2削減の教科書」を運営する「株式会社エネテク」は
国内最大級となる 自己託送 太陽光発電所を設計・調達・建設、稼働後のメンテナンスまで行うことになりました。
詳細:日経BP「自己託送向けで最大級の太陽光、エネテクがEPC」
まとめ
いかがでしたでしょうか?
自己託送 について、要件厳格化の問題から基礎知識まで
ご理解頂けたのではないかと思います。
要件厳格化の可能性もありますが、自己託送 は大規模な「CO2削減」「電気料金削減」が可能になるという大きな魅力があります。
自己託送 導入を検討される際に、本記事がお役に立てれば幸いです。
また要件厳格化や新規受付停止について、最新の情報が分かり次第
本記事を更新してお知らせしていきますので、ぜひブックマークの方もよろしくお願いいたします。