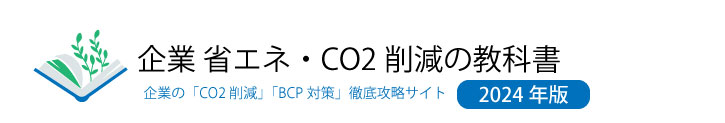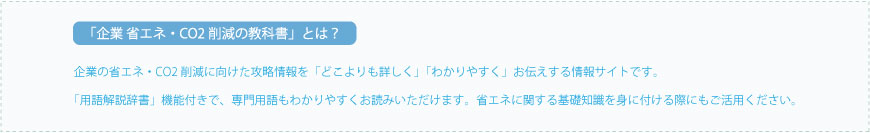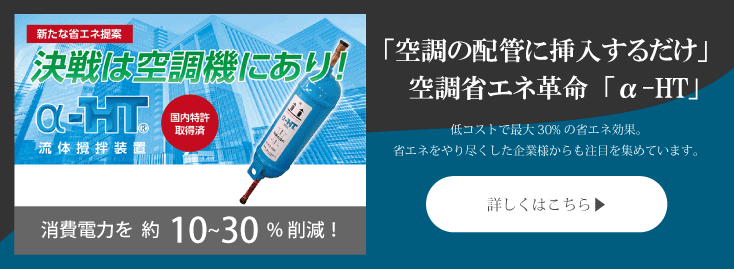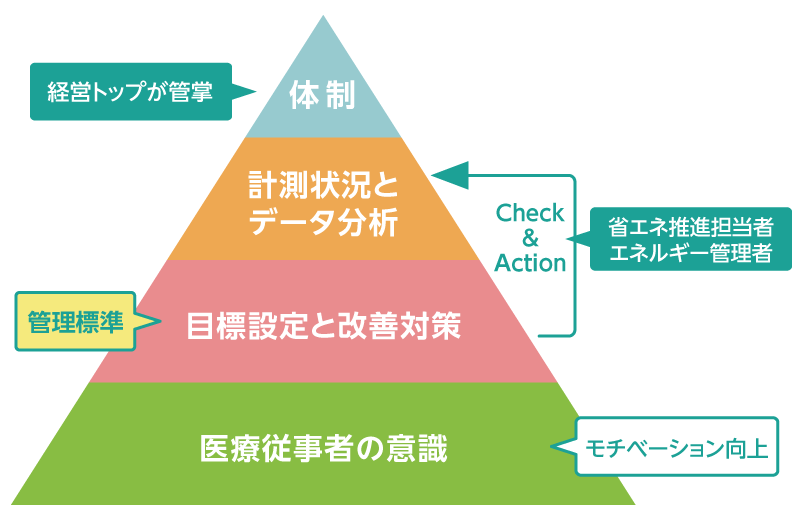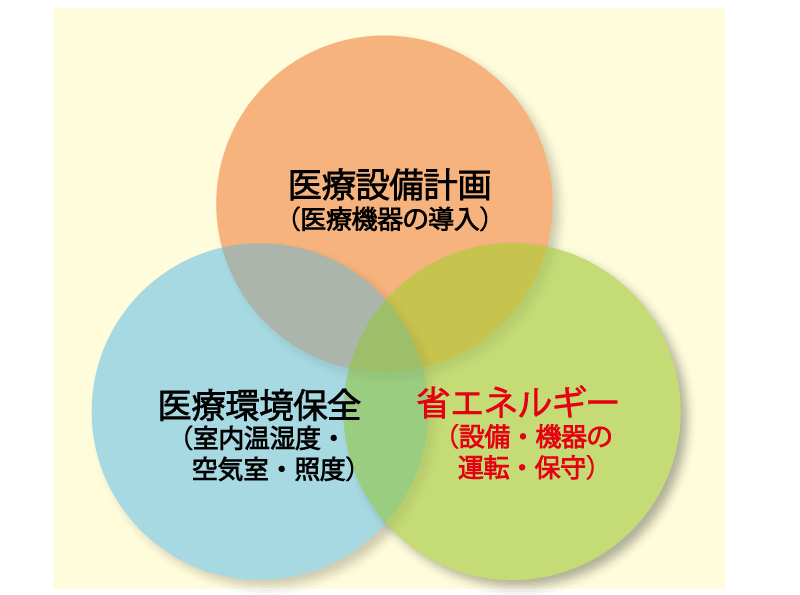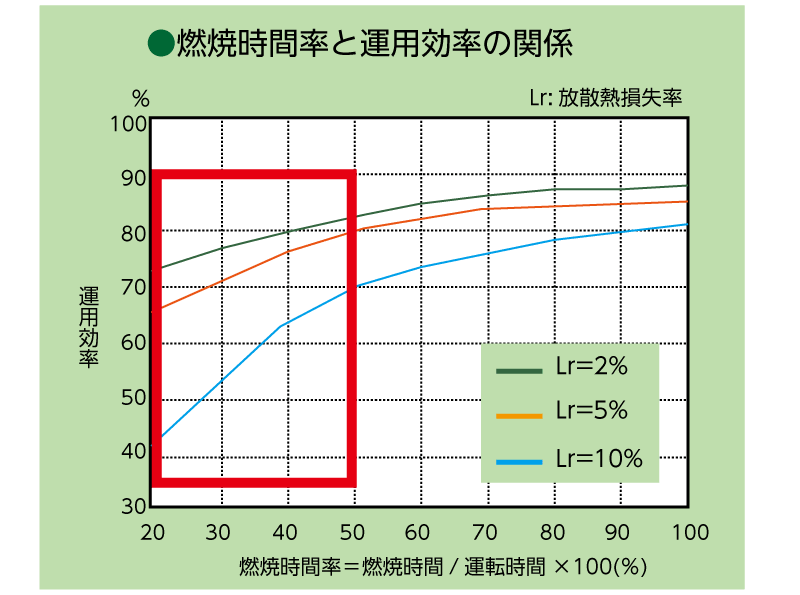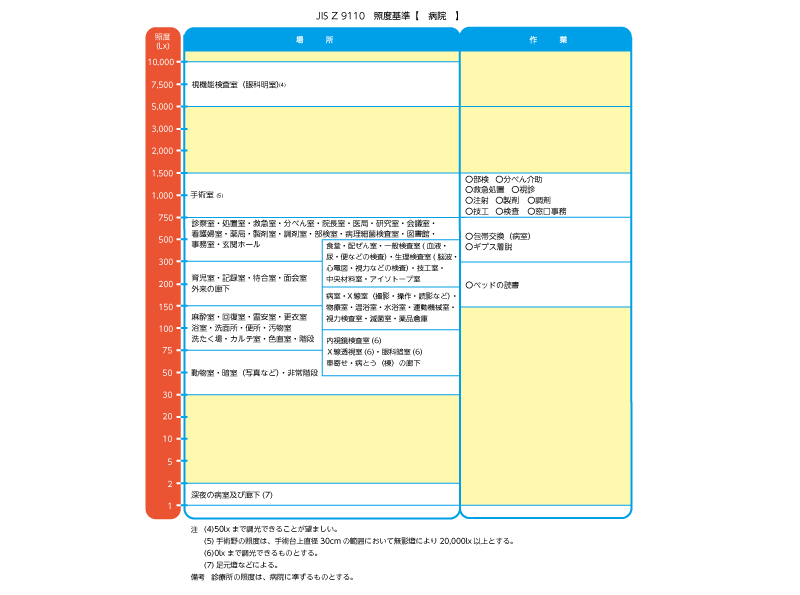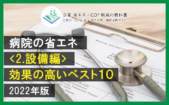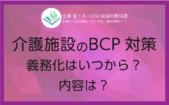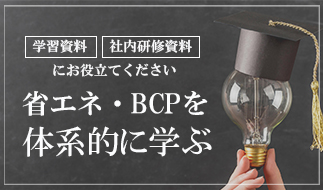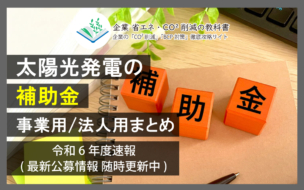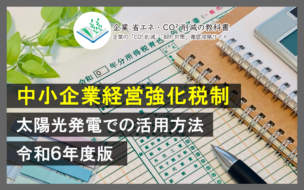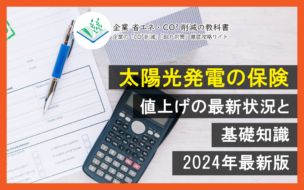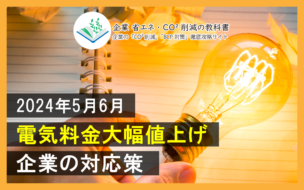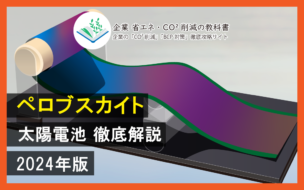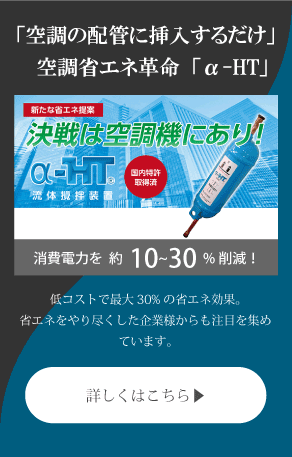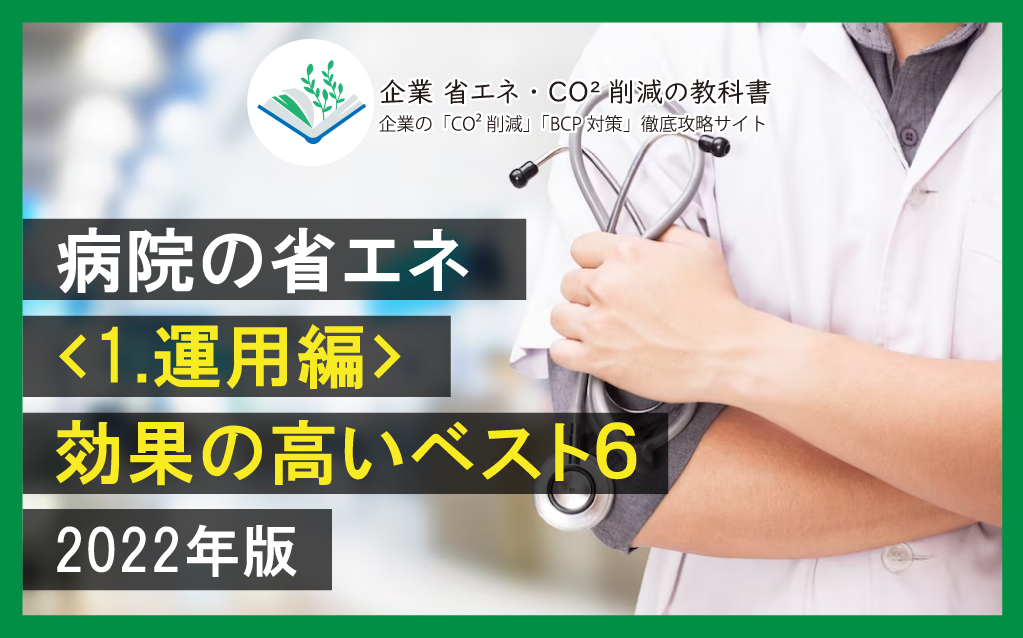
※2022年4月22日 最新情報に更新しました。
生命を預かる医療の現場。
さらに地域にとって不可欠な医療施設は、
同時に「地域の医療を維持するため」に「病院経営の維持」も必要です。
また、BCP の観点からも
「緊急事態における医療体制」を守るため、普段から省エネを心がけておくことが必要です。
まず「人の手による運用」で省エネに取り組んでいくと
大きな費用をかけずにコストを削減できます。
この記事では、
・具体的な「省エネ削減率」「削減金額」も記載。
・病院特有の環境保全も維持した省エネ方法
をご紹介します。
ぜひ貴院の省エネにお役立てください。
省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、
あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。
目次
病院の省エネはなぜ重要?
まず医療施設にとって「省エネ」はなぜ重要なのでしょうか?
1.省エネは固定費削減になる
「固定費削減」が病院経営のカギ
病院経営において重要なのが「固定費の削減」です。
売上が下がった際にも「変動費」は調整しやすく、出ていく金額を抑えることができます。
しかしながら「固定費」の比率が大きい場合、
売上減少時には赤字に転落しやすくなります。
固定費で2番目に多い「水道光熱費」
その固定費の中で最も多いのが「人件費」で、その次に多いのが「水道光熱費」です。
病院経営を健全に保つためにも、固定費の中で大きい「水道光熱費」の省エネは
重要な課題となって来るのです。
参考:幻冬舎GoldOnline「医療・介護施設に「水道光熱費削減」が強く求められるワケ」
2.BCP対策 として緊急時のエネルギーを抑える
医療施設は、地域社会の生命を守る為「災害時にも稼働できる」ことが必要です。
災害時に、限られた非常用電源で医療施設を維持していく為にも
普段から省エネに取り組んでおくことが重要になってきます。
3.環境問題における社会的責任
近年では、環境問題への取組みが重要視され始めています。
CSR という観点からも、省エネは重要な取り組みになります。
病院のエネルギー消費の特徴
続いて、病院ではどのようにエネルギーが消費されているのでしょうか?
見て行きましょう。
病院で使用されるエネルギーの比率
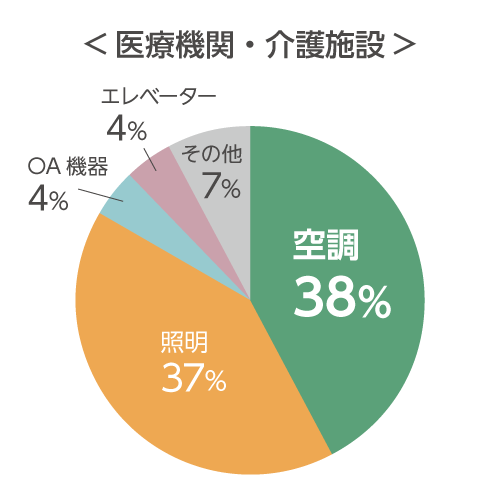
グラフをご覧いただくとお分かりの通り、
医療施設においては「空調と照明」の消費率が高くなっています。
他業種より大きい病院のエネルギー使用量
続いて、他業種とのエネルギー消費量の違いを比べてみましょう。
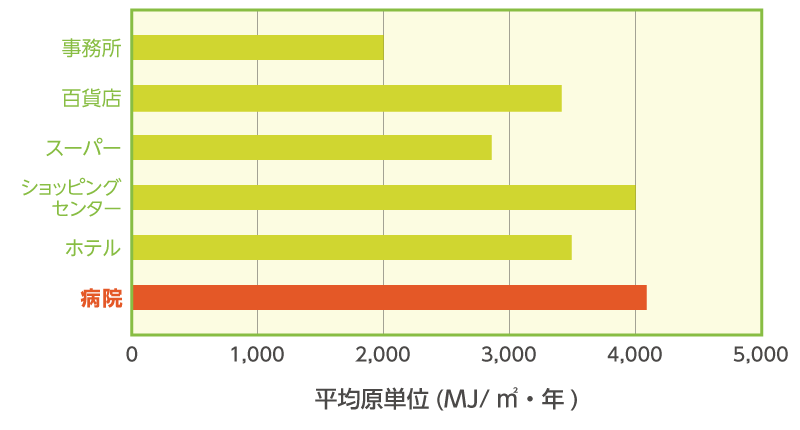
出典:(財)省エネルギーセンター平成15年度ビルのエネルギー使用に係る実態調査
ご覧の通り、病院の消費エネルギー量は他業種に比べて最も多くなっています。
使用エネルギーが多い理由
止められない機器が多い
言うまでも無く、病院は生命を守るための施設であるため
医療機器を中心に止められない機器が多数あります。
空調の設定温度が低い
後述しますが、病院における空調の設定温度は一般的な企業の水準と比べて
「夏は低め」「冬は高め」の室温設定が求められています。
この為、空調の消費エネルギーも大きくなってしまいます。
体の弱った方の為、空調の維持が必要
空調においても「快適さ」だけでなく、体の弱った患者さんの生命や体調を守るために必要であり、簡単に停止することができません。
患者さんの協力が必要
一般的な業種では、従業員が省エネを意識することが重要になってきます。
しかしながら、病院においては患者さんの協力も必要になってくる点も特徴です。
24時間稼働
営利向けの施設と異なり、病院は24時間体制で空調や照明、医療機器を稼働させなければなりません。
このように「生命を守る」観点から、
医療施設は他業種に比べて多くのエネルギーを消費しているのです。
病院の消費エネルギーの月次推移
次に地域別に月ごとの消費動向を見てみましょう。
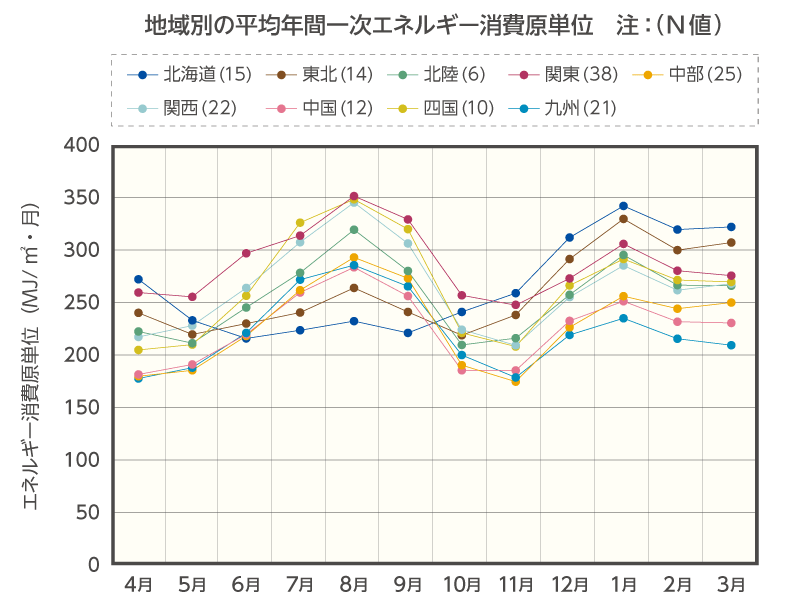
出典:(財)省エネルギーセンター平成16 年度アンケート調査
このグラフを詳しく見ていくと、北海道と東北は1月、
それ以外の地域は8月に消費エネルギーのピークが来ているのがお分かりいただけます。
このことからも、北海道や東北は冬季の暖房、それ以外の地域は夏季の冷房に対する消費エネルギーが高いことが伺えます。
病院の種類によっても消費エネルギーは違う
また、病院の中でも施設の性格によって、消費エネルギーは変わってきます。
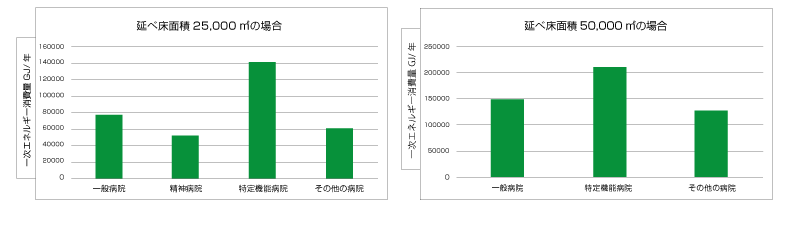
出典:(財)省エネルギーセンター平成16 年度アンケート調査の分布図より抜粋しグラフ化
ご覧いただくとお分かりの通り、同じ延床面積で比較しても
「特定機能病院」は他の病院よりも消費エネルギーが高い傾向があります。
効果の高い省エネ:ベスト6
病院におけるエネルギーの消費動向をお分かりいただいたところで、
「どれほどの費用が削減できるのか?」
具体的な数字で見て行きましょう。
「運用による省エネ」削減金額ランキング
| 順位 | 施策 | 省エネ率 | 年間削減金額 |
| 1位 | 空調設定温度の緩和 | 2.9% | ¥713,000 |
| 2位 | 冷温水発生器の適正台数運転 | 2.4% | ¥608,000 |
| 3位 | 省エネルギー体制の構築 | 1.9% | ¥478,000 |
| 4位 | 排気ファンの停止 | 1.1% | ¥286,000 |
| 5位 | ボイラーの適正台数運転 | 0.8% | ¥189,000 |
| 6位 | 照度の適正管理 | 0.4% | ¥90,000 |
| 合計 | 9.5% | ¥2364,000 |
※省エネ率・・・その施策で削減できた金額の割合
※調査した6病院の運用改善対策における改善金額の平均値を元に
5,000㎡の病院に当てはめ試算した効果です。
出典:東京都環境局 東京都地球温暖化防止活動推進センター「病院の省エネルギー対策」
運用による省エネだけで「9.5%」削減
「設備の買い替え」ではなく「運用の見直し」で10%近くの削減が可能になることが
このシミュレーションでは示されています。
やはりウェイトが大きいのは「空調」
また、上位1位2位を占めているのは「空調の運用改善」です。
1位2位を合わせると「5.3%」となり、全体の省エネ削減の半分以上を占めています。
それでは次の章から、削減金額が大きな施策から順に
「具体的な省エネの取組み」をご紹介いたします。
1位:空調の省エネテクニック12選
まずは1位の「空調設定温度の緩和」に繋がる施策についてご紹介します。
見直すべき12のポイントと省エネ効果
空調の省エネ施策と削減効果一覧
ご紹介する施策と削減効果は以下のようになっています。
(削減効果が算出できない施策は省略しています)
| 施策 | 省エネ効果の目安 | 頻度等 |
| 1.適正温度の見直し | 1℃最適化するだけで約10%の削減が可能。 (設定温度は各部門で異なる) | |
| 3.カーテンやブラインドで遮光する | ブラインド無しの場合と比較して10.6%の省エネ効果 | |
| 4.フィルターの清掃 | 「冷房時で約4%、暖房時で約6%」の省エネが可能 | 2週間に1回 |
| 5.室外機の環境チェック | 室外機の風通しが悪いと電気代は1.5倍に。 | |
| 6.熱交換器 の清掃 | 長期間行わなかった場合に比べて約27%の節電 | 約5年に1度 |
| 7.外気導入量 の調整 | 約2%の削減効果 | |
| 8.ナイトパージ | 約5%の省エネ (ナイトパージシステム 利用) | |
| 9.分散起動 | 冬の商業施設で約9%の削減効果 | |
| 10.残熱利用 による運転時間の短縮 | 約6%の省エネ (8時間勤務のオフィスで30分間空調停止した場合) |
それではひとつひとつ、施策の具体的な内容を見て行きましょう。
1.適正温度の見直し
室温設定を1℃見直すだけで「10%」の省エネに
環境省によると「室温を最適な温度に1℃近づけると10%の省エネが可能」と言われています。
※但し「室温」であり「エアコンの設定温度」では無い点に注意が必要です。
出典:環境省・温室効果ガス排出抑制等指針「空調設定温度・湿度の適正化」
医療施設の温度環境は他業種とは違う。
同じく環境省からは、室温について「夏期 28℃、冬期20℃」が推奨されています。
しかしながら、病院では各施設によって温度や湿度の設定が異なる為注意が必要です。
病院内各施設の温湿度
日本医療福祉設備協会の規格では、
病院内各所の温度と湿度は下記のような設計条件が定められています。
| 部門 | 室名 | 夏季 | 冬季 | ||
| 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | ||
| 病棟 | 病室 | 24℃~27℃ | 50%~60% | 22℃~24℃ | 40%~50% |
| ナースステーション | 24℃~27℃ | 50%~60% | 20℃~22℃ | 40%~50% | |
| デイルーム | 26℃~27℃ | 50%~60% | 20℃~22℃ | 40%~50% | |
| 外来 | 診察室 | 26℃~27℃ | 50%~60% | 22℃~24℃ | 40%~50% |
| 待合室 | 26℃~27℃ | 50%~60% | 22℃~24℃ | 40%~50% | |
| 調剤室 | 25℃~26℃ | 50%~55% | 20℃~22℃ | 40%~50% | |
| 緊急手術室 | 23℃~26℃ | 50%~60% | 22℃~26℃ | 45%~60% | |
| 中央診療部門 | 手術室 | 23℃~26℃ | 50%~60% | 22℃~26℃ | 45%~60% |
| 回復室 | 24℃~26℃ | 50%~60% | 22℃~26℃ | 45%~55% | |
| ICU | 24℃~26℃ | 50%~60% | 23℃~25℃ | 45%~55% | |
| 分娩室 | 24℃~26℃ | 50%~60% | 23℃~25℃ | 45%~55% | |
| 新生児・未熟児室 | 26℃~27℃ | 50%~60% | 25℃~27℃ | 45%~60% | |
| 一般検査室 | 25℃~27℃ | 50%~60% | 20℃~22℃ | 40%~50% | |
| X線撮影室 | 26℃~27℃ | 50%~60% | 24℃~25℃ | 40%~50% | |
| X線操作室 | 25℃~26℃ | 50%~60% | 20℃~22℃ | 40%~50% | |
| 水治療室 | 26℃~27℃ | 50%~65% | 26℃~28℃ | 50%~65% | |
| 解剖室 | 24℃~26℃ | 50%~60% | 20℃~22℃ | 40%~50% | |
| 供給部門 | 厨房 | 「病院給食システムの設計・管理指針」による | |||
| 洗濯室(作業域周辺) | 30℃以下 | 70%以下 | 15℃以上 | 40%以上 | |
| 材料部諸室 | 26℃~27℃ | 50%~60% | 20℃~22℃ | 40%~50% | |
| 管理部門 | 一般居室 | 26℃~27℃ | 50%~60% | 20℃~22℃ | 40%~50% |
出典:日本医療福祉設備協会規格「病院空調設備の設計・管理指針」
このように各施設によって設定温度や湿度も異なり、
一般的な建築物の「夏期 28℃、冬期20℃」よりも消費エネルギーが多くなってしまう基準になっています。
部門やスタッフ、患者さんに合わせた室温設定を
医療現場においては、部門やその場所にいる人に合わせた最適な温度を考える必要があります。
各部門、エリアに合った季節ごとの室温を見直し、
貼紙や室温計の設置など、室温を最適に保つ工夫や啓蒙が必要になります。
「室温」を調整することが重要
前述したように、空調の省エネの場合には空調の設定温度ではなく、
「室温」が重要になってきます。
空調機器個々の機能の違いや、その部屋の環境によっても室温は変わります。
その為、各部屋を室温計などで計測し、最適な設定温度を決めて行くと効果的です。
2.夏以外は外の冷気をうまく活用する
医療施設の場合、年間を通して冷房するエリアが多い特徴があります。
夏以外の冬季や中間期には、外気導入量 を増やすことで冷房の消費電力を削減できます。
3.カーテンやブラインドで遮光する
カーテンやブラインドで遮光することも、省エネには効果的です。
東京都地球温暖化防止活動推進センターによると
ブラインド無しの場合と比較して「10.6%の省エネ効果」があると紹介されています。
出典:東京都地球温暖化防止活動推進センター「ブラインドを省エネ対策に有効活用」
4.フィルターの清掃
「フィルターの清掃」も良く言われている省エネ方法です。
しかしながらその効果までご存知の方は少ないのではないでしょうか?
環境省の資料によると、フィルターの清掃を「2週間に1回」行うと
「冷房時で約4%、暖房時で約6%」の省エネが可能になります。
具体的な効果が分かると、積極的にやるべき施策であることが分かります。
「2週間に一度」を目安に、清掃をしていくと効果的です。
5.室外機の環境チェック
室外機周辺の環境も省エネには重要です。
室外機周辺の障害物を無くす
室外機周辺に物があると、ファンからの放熱の妨げになります。
何か物が置かれていないか確認し、除外するようにしましょう。
室外機の置かれている温度環境に注意
また、室外機の中には「熱交換器」という機器があり、
冷房時には空気を冷やす、暖房時には空気を温める役割を担っています。
室外機周辺は、夏は涼しく冬は暖かくしておくと省エネに繋がります。
温度調節には「すだれ」を活用
温度調節には「すだれ」を活用すると便利です。
夏はすだれで遮光し涼しい環境を作り、
冬は外して日当たりを良くすれば、季節ごとの切り替えが可能になります。
室外機周辺の環境が悪いと、電気代は1.5倍に
室外機周辺の環境が悪いと、電気料金が1.5倍になったという実験結果もあります。
参考:家電ウォッチ「エアコンの節電法、実際どれだけの効果がある?」
ぜひ一度環境を見直してみましょう。
6.熱交換器の清掃
熱交換器 の清掃も省エネには効果的です。
熱交換器とは?
熱交換器 とは、空調機器の室外機と室内機の中にある「空気を冷やす」機器です。
写真のように、フィルターを外すと見える「金属部分」が 熱交換器 です。

ここを掃除機などで清掃します。金属部分は曲がりやすいので注意が必要です。
力を入れる清掃が必要な状態であれば、専門業者に依頼したほうが良いでしょう。
参考資料:空調クリーニングのサービス例
ダイキンプロショップ「空調のプロに任せる業務用エアコンのクリーニング」」
省エネ効果は「約27%」
熱交換器 の清掃を長期間行わなかった場合と比較すると
「約27%の節電に繋がった」というデータもあります。
参考:ダイキンHVAソリューション東京株式会社「業務用エアコンの掃除・洗浄・クリーニングについて」
掃除の頻度は「5年に一度」
医療施設の場合、熱交換器 の清掃は「5年に一度」が目安です。
まず院内従業員で掃除機で清掃してみて、それでも落ちない汚れやカビなどがある場合
業者に依頼、または古い機種であれば買い替えを検討してみても良いでしょう。
7.外気導入量の調整
外気導入量 を削減することも、省エネには効果的です。
外気導入量とは?
空調には換気機能が付いています。
換気によって屋外から取り込む外気の量を「外気導入量」と呼びます。
外気導入量の削減は省エネになる
外気温が室温より高いときには、室内より暖かい空気を冷やす為、
冷房の消費エネルギーは大きくなってしまいます。
外気温が室温より低いときの暖房も同様です。
つまり、
このような施策を行うと効果的です。
とはいえ換気は重要
かといって、省エネの為に 外気導入量 を削減しすぎることも良くありません。
換気がされていなければ、院内の空気環境が悪化してしまいます。
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、
室内の空気質基準として、CO2濃度を1,000ppm以下にするよう定められています。
(※厳密にはビル管法は病院は対象外の法律ですが、医療施設への規定が無いため参考にします)
市販されている「CO2濃度計」で各施設を調査し、基準値を大きく下回っている
場合には 外気導入量 の削減をしていくと良いでしょう。
外気導入量削減による省エネ効果は「2%」
医療施設における 外気導入量 削減による省エネ効果は「2%」が目安になります。
出典:四国電力「用途別節電事例集~具体的な節電方法とその効果~」
8.ナイトパージ
ナイトパージとは?
ナイトパージ とは、夜間に外気を取り込むことで室内を冷やし、翌日の冷房起動時の負担を減らす省エネ手法です。
ナイトパージシステム
専用に「ナイトパージシステム」が備わっている空調設備もあります。
ナイトパージシステムが備わっている病院では、夜間の外気取り込みなどの施策を容易に行うことができます。
夜間の換気
ナイトパージシステム の備わっていない施設では、夜間に空調または窓を開けることで外気を取り込む施策が有効です。
「夜間に送風設定した空調を稼働させること」と「翌朝の冷房開始時の負荷」
どちらが省エネになるか検証し、運用を決めて行く必要があります。
ナイトパージの省エネ効果
国土交通省の実証実験では「約5%の省エネ」が確認されています。
出典:国土交通省 北陸地方整備局「冷房負荷低減のためのナイトパージの実証実験について」
9.分散起動
分散起動 とは、空調を同時に起動するのを避け、
タイミングをずらすことでピーク時の使用電力を抑える省エネ手法です。
朝に気温が下がる冬に特に大きな効果があります。
他業種の事例になりますが、冬の商業施設では約9%の削減効果が確認されています。
10.残熱利用による運転時間の短縮
残熱利用とは?
「残熱利用」とは、就業の15~30分前に空調を止めることで、効いている空調の残熱で残り時間の温度環境をある程度維持する手法です。
削減効果
削減効果は、その部門の稼働時間や止めるタイミングの早さによって異なりますが
仮に8時間の稼働時間の部門が仮に30分前に停止した場合、単純計算で「約6%」の削減が可能になります。
各部門での活用方法
外来部門/供給部門/管理部門/厨房
24時間体制ではなく、稼働時間が決まっているエリアでは
「残熱利用」を他業種のように活用できます。
病棟
病棟においては、24時間体制となっているため難しい面があります。
できる方法としては、深夜や早朝の涼しくなる時間帯の少し前に空調を止めるといった手法があります。
11.24時間空調エリアと他エリアとの空気出入りを制限
病棟などの24時間空調エリアと、外来部門などの空調の稼働時間が決まっているエリアとの間に空気の出入りがあると、空調に無駄が生じてしまいます。
これを避ける為、24時間空調エリアと他エリアの堺となるドアは、こまめに閉めることを徹底する必要があります。
12.高度な安全性を求められるエリアの省エネ
差圧の設定見直し
病院においては「感染症病室」など高度な安全性を求められるエリアが多くあります。
しかし、その差圧が必要以上の設定になっているとエネルギーの無駄を生んでしまいます。
差圧の設定が高くなり過ぎていないか確認しておきましょう。
手術室/中材などの無菌エリア
無菌エリアの夜間非使用時には、循環風量を清浄度が保てる最小限に設定しておきましょう。
省エネ管理を自動化する
番外編にはなってしまいますが、空調の省エネ改善において、覚えておくべきキーワードがあります。
「ゼロエナジーバンドコントロール」「エネルギーマネジメントシステム」
このふたつは本来システムや設備に分類されますが、
運用を助けるためのテクノロジーでもありますので、運用編で少し触れておきます。
人の手で行うのが難しい空調管理
「運用による空調の省エネ」についてご紹介してきましたが、
実際に精密に実施しようとすると、従業員の皆さんの負担も大きくなります。
近年では、システムによる制御やIoT等も発達し、
こうした運用管理を助けるテクノロジーが普及してきています。
ゼロエナジーバンドコントロール
ゼロエナジーバンドコントロールとは?
ゼロエナジーバンドコントロールとは、空調の温度調整に「幅」を持たせることで、省エネを実現する手法のことです。
また、そうした手法を用いた機器や制御ソフトのことを指すこともあります。
詳しく例を挙げて解説します。
従来の空調機器
従来の空調機器では、例えば設定温度を28℃にした場合、
少しでも28℃から温度が変わった場合には空調が稼働し28℃になるまで動作します。
ゼロエナジーバンドコントロールができる空調の場合
対して、ゼロエナジーバンドコントロール が付いている空調では、
空調が稼働するまでの「幅」を持たせ(例えば2~3℃)から外れた時のみ
空調が稼働する仕組みになります。
こうして空調の停止時間を増やすことにより、空調費用の削減を行う仕組みです。
人の手では行えない細かなコントロールができる
こうした細かな設定コントロールは、人の手による運用では難しい為、
空調機器の買い替えの際には、こうした機能を持っているかどうかも判断材料にして頂ければと思います。
エネルギーマネジメントシステム
エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?
エネルギーマネジメントシステム(略して EMS とも呼びます)とは、
院内のエネルギーの使用状況をIoT技術などで収集し、
リアルタイムで見える化してくれるシステムです。
また自動制御機能が付いている製品もあり、
使用電力が多くなる時間帯に電力消費をセーブする機能や
空調の最適化を自動的に行ってくれるシステムもあります。
自動化するメリット
こうして自動化することで、人の手では不可能な精密なコントロールを
リアルタイムで行うことができ、より大きな削減を可能にします。
また消費されている電力状況が明確になる為、
無駄が発生している箇所を正確に把握することができます。
エネルギーマネジメントシステムについて詳しくはこちら
2位:冷温水発生器の見直し
続いて、2位にランクインしているのが「冷温水発生器の見直し」です。
こちらも実際には「空調の省エネ」に分類される省エネ施策です。
冷温水発生器とは?
「冷温水発生器」とは、簡単に言ってしまうと、空調で空気を冷やすために使用する「冷水」
または空気を温めるための「温水」を作り出す機器です。
似た機器として「冷凍機」がありますが、こちらは簡単に言ってしまうと「冷温水発生器」の「冷水」だけを作る機器と理解すると分かりやすいです。
「冷温水発生器」も「冷凍機」も、屋上や屋外に設置され、病院全体の空調の為に一元化されているのが一般的です。
7℃から10℃に見直し
この冷水の温度を7℃から9℃に上げることで、使用電力は8%削減できると言われています。
3位:省エネルギー組織体制の構築
続いて3位にランクインしているのが「省エネルギー組織体制の構築」です。
省エネルギー組織体制とは?
「空調の省エネ」の章で、運用方法をご覧いただいてお分かりの通り、
省エネを実践していくためには、細かな運用が必要になります。
その為、院内スタッフから患者さんに至るまで
多くの方々が「省エネ」について「共通認識」を持って取り組んで頂く為の体制が
「省エネルギー組織体制」です。
省エネ体制の構築はなぜ重要か?
すべての省エネ運用に影響する
「省エネルギー組織体制の構築」は、ご紹介したランキングでは「3位」になっています。
しかしながら、1位の空調の省エネをはじめとして、
全ての省エネ運用は省エネルギー組織体制のもとに削減が実現できています。
つまり全ての省エネを実現する上で、省エネルギー体制は土台として重要な役割を果たしているのです。
病院の省エネ組織体制の構造
それでは、病院の省エネルギー体制はどのような構造になっているのでしょうか?
具体的に見て行きましょう。
省エネ体制の運用構造
病院の省エネ体制は、図のようなピラミッド構造で運用されます。ひとつずつ見て行きましょう。
1.体制を構築
重要なのは「経営層のリーダーシップ」
まず体制づくりで重要なことは「経営層のリーダーシップ」です。
省エネ担当者に任せるのではなく、経営層がリーダーとして積極的に省エネ組織を統括し、推進していくことが省エネ体制づくりで最も重要なポイントです。
各部門の省エネ責任者を任命する
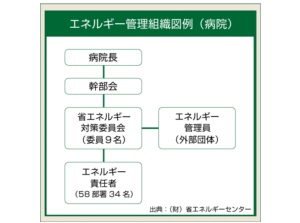
図のように、病院長、幹部会をトップとした組織を作ります。
省エネルギー委員は各部門から委員を選出し、省エネ対策委員会を設置。
さらに各部門の省エネ活動責任者を配置し、省エネの指針に沿った活動を実行していきます。
薬剤師を委員長として、医師、看護師、事務部門等、各部門代表者を委員に任命。
環境委員会を設立し、月一回の会議を通じて問題の見直しや取組みの確認を行う。
2.計測状況とデータ分析
現状のエネルギー消費状況を可能な限り見える化
まず現状のエネルギー消費/かかっている光熱費を可能な限り見える化/数値化します。
まず現状を見える化しなければ、取り組むべき削減計画を立てるのも困難です。
見える化が困難、または煩雑な場合には
この時点で「エネルギーマネジメントシステム」導入を検討しても良いかもしれません。
3.目標設定と改善対策
目標設定
現状のエネルギー消費状況を踏まえ、省エネ可能な「運用面」「設備導入面」の対策を検討します。
本記事でご紹介しているように、それぞれの対策で現状できていないものを実行に移すことで
どれほどの省エネが可能か分析して目標設定をします。
改善対策
日、月ごとにエネルギー消費量の計測・記録を行い、その実績を委員会で評価します。
実施できていない取組みの要因を分析し、実施できるよう環境を改善。
またエネルギーの無駄を発見したら、改善策を話し合います。
4.医療従事者の意識
委員会等で決定した目標とそれに対する取り組みを病院内に周知します。
ここでは「医療従事者」となっていますが、病院の場合には患者さんへの周知も必要になってきます。
このような流れで、経営層をリーダーとして、
患者さんも含めた「病院全体」で省エネを推進していきます。
病院の省エネのバランス
上記にご紹介した「省エネ体制」の構築は、比較的どの業種でも同じような取り組みを行っています。
しかし「医療施設の性質」から、
「医療設備計画」「省エネ」「医療環境保全」の3要素のバランスをとる必要があり、
この点に注意が必要です。
病院施設管理の3要素のバランス
医療設備計画(医療機器の導入)と省エネのバランス
医療機器の導入においても、省エネの観点を入れておく必要があります。
高機能であるがゆえにエネルギー消費が増えるケース
高機能医療機器の新規導入においては、消費エネルギーが増えてしまうこともあります。
最新機器への買い替えが省エネになるケース
その反対に、古い機器を買い替えることで省エネを推進できるケースもあります。
医療環境保全(室内温湿度・空気質・照度)と省エネのバランス
空調の項でもご紹介したように、空調や照度においては患者さんや医療環境を守ることを基本として、省エネを進めて行く必要があります。
あくまで環境保全を優先しながら、過剰な設定になっている箇所に省エネを施していきます。
4位:ボイラーの省エネテクニック5選
続いて第4位は「ボイラーの運用見直し」です。
ボイラーは多くのエネルギーを消費する設備ですので、
小さな省エネ改善でも大きな削減効果が得られる点が特徴です。
ここでは5つの省エネ改善テクニックをご紹介します。
1.台数の見直し
ボイラーの稼働台数を見直すことが省エネに繋がります。
少し分かりにくい話ですので「燃焼時間率」のお話から順に解説していきます。
「燃焼時間率」とは?
ボイラーの省エネを考える上で、効率的に燃焼されているかどうかの指標として
「燃焼時間率」という基準があります。
別名で「点火率」とも呼ばれ、
「燃焼時間率=燃焼時間÷運転時間×100%」の数式で算出されます。
つまり、ボイラーを運転している時間の中で燃焼されている時間の割合を示す値です。
「点火率」という別名からも示されているように、
「頻繁に着火と消化を繰り返していないか?」という指標にもなります。
「燃焼時間率」が下がると「頻繁に着火と消化を繰り返している」とみなされ
運用効率が下がり、エネルギーの無駄が生じやすくなってしまいます。
燃焼時間率と運用効率の関係
実際に 燃焼時間率 と運用効率の関係性を見てみましょう。
グラフの赤枠の箇所に注目して頂くとお分かりの通り、
燃焼時間率(横軸)が50%を下回ると、運用効率(縦軸)も大きく下がっています。
燃焼時間率 が50%以下になると、運用効率が下がる。
すなわちエネルギーの無駄が生じてしまうのです。
運用効率の低下と台数のコントロール
それではこの「運用効率の低下」と本題の「台数」がどう関係するのでしょうか?
必要な蒸気量が「少ない」ときに台数が多いと・・・
必要な蒸気量が少なく、稼働しているボイラーの台数が多いときには
「頻繁に着火と消化を繰り返している」状態が起こりやすくなります。
つまり「燃焼時間率」が下がり「運用効率」も下がってしまい、
「エネルギーに無駄が生じている」状態になってしまうのです。
稼働台数の適正化
こうした運転効率を考え、台数を適正化していくことで省エネが可能になります。
削減率は10%。年間削減額は333,000円の試算
東京都環境局の試算によると、台数の適正化での省エネ率は10%、
年間の削減額は5,000㎡の病院で「333,000円」と紹介されています。
2.空気比の見直し
ボイラーにおける空気比を下げる手法も省エネには効果的です。
「空気比」とは?
「空気比」とは、燃料を完全燃焼させる為に「理論上」必要な空気量(理論空気量)と
実際に燃焼用に送り込まれた空気量の比率を表したものです。
省エネ法 で定められている基準値としては、ビルで一般的に使われているボイラ(都市ガス燃料、蒸発量30t/h以下)の場合「1.15~1.25」が提示されています。
これはつまり、
「理論上必要な空気量」の1.15倍~1.25倍の空気量を実際には送り込んでください。
という意味になります。
「空気比」の注意点
空気比は、低くなるほど燃料のロスが少なくなり省エネに繋がります。
ただし少なすぎてしまうと「不完全燃焼」になってしまう為、注意が必要です。
「空気比」は「排ガス中酸素濃度」から求めることができる
空気比は「排ガス中酸素濃度」から算出することができます。
つまり「排ガスの中に含まれる酸素の濃度」から「送り込まれた空気比」が算出できるのです。
「排ガス中酸素濃度:6%」=「空気比:1.35」
「排ガス中酸素濃度:3%」=「空気比:1.2」
空気比を1.35から1.2に下げることで「4%」の省エネ
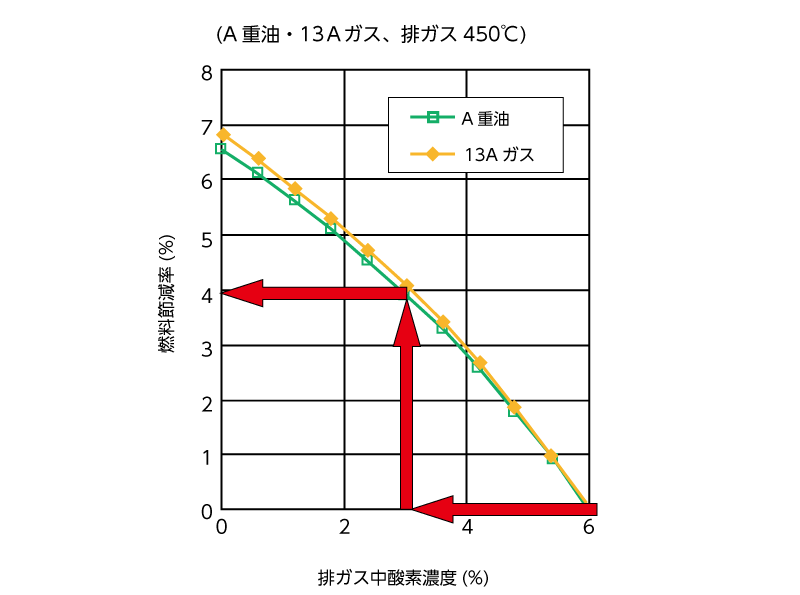
出典:財団法人省エネルギーセンター「病院の省エネルギーポイント」
図のように「排ガス中酸素濃度6%(空気比1.35)」から「排ガス中酸素濃度3%(空気比1.2)」に下げた場合、燃料が「4%」削減できることが分かります。
3.スチームトラップをチェック
スチームトラップ(ボイラー内の弁の役割を担う箇所)にゴミが詰まっていたり、故障があるとエネルギーのロスが生まれます。
定期的に見直しましょう。
4.蒸気漏れの定期チェック
見えない箇所に「蒸気漏れ」が起きていると、エネルギーの大きなロスになります。
こちらも定期的な見直しをしておきましょう。
36%の削減に成功した事例も
東京都環境局で紹介されているホテルの改善事例では、削減率36%に至った例も紹介されています。
5位:排気ファンの停止
不要な排気ファンを停止することも、省エネ効果の高い施策です。
人があまりいないフロアでは、CO2濃度が高くなる危険性も低いため、排気ファンの常時運転が必要ないケースもあります。
こうした「換気が不要な個所」「削減できる箇所」を見直すことも重要です。
6位:照明の見直し
冒頭にご紹介させて頂いたように、病院における消費電力が空調に次いで多いのが「照明」です。
こまめな消灯
病院における照明の省エネは、医療従事者や患者さんの行動範囲を考慮する必要がありますが、
明らかに必要のない場所は消灯するように、貼紙などで啓蒙しておくと効果的です。
時間帯や季節に応じた照明の管理
外来部門の時間帯に合わせた照度調整
特に外来部門では、患者さんが来院する時間帯以外の省エネが重要です。
閉院中は消しておく照明のスイッチには分かるようにラベルなどを貼っておくと
消し忘れ防止に効果的です。
季節ごとの照度調整
特に朝や夕方は、季節によって日光の明るさが変わります。
消灯時間、点灯時間を季節によって決めて管理すると効果的です。
電球のこまめな清掃
電球の清掃ができておらず、埃や汚れが残っていると照度が下がってしまい、
余計な照明をつけてしまうようになってしまいます。
電球の掃除は半年に一度
照明の掃除は「半年に一度」が目安になります。
1年以上掃除してい場合、照度が20%下がると言われています。
参考資料:病院の照度基準(JISZ9110)
下記に、病院内の各施設で推奨される照度をご案内します。
省エネにおける明るさ調整のご参考になさってください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
運用で削減できる省エネについて、ひと通りご理解頂けたのではないかと思います。
簡単に振り返ってみましょう。
・病院の消費エネルギーは他業種と比較しても大きい。
・地域や病院の種類によっても消費エネルギーは異なる。
効果の高い省エネ:ベスト6
| 順位 | 施策 | 省エネ率 | 年間削減金額 |
| 1位 | 空調設定温度の緩和 | 2.9% | ¥713,000 |
| 2位 | 冷温水発生器の適正台数運転 | 2.4% | ¥608,000 |
| 3位 | 省エネルギー体制の構築 | 1.9% | ¥478,000 |
| 4位 | 排気ファンの停止 | 1.1% | ¥286,000 |
| 5位 | ボイラーの適正台数運転 | 0.8% | ¥189,000 |
| 6位 | 照度の適正管理 | 0.4% | ¥90,000 |
| 合計 | 9.5% | ¥2364,000 |
費用のかからない「運用による省エネ」でも、大きな削減効果が見込まれます。
その反面、医療従事者のみなさんの手で行う為、難しい部分もあります。
次の記事では≪設備編≫として、
費用はかかりますが、効果がより大きく、院内の皆さんの負担も少ない
設備導入による省エネを中心にご紹介いたします。